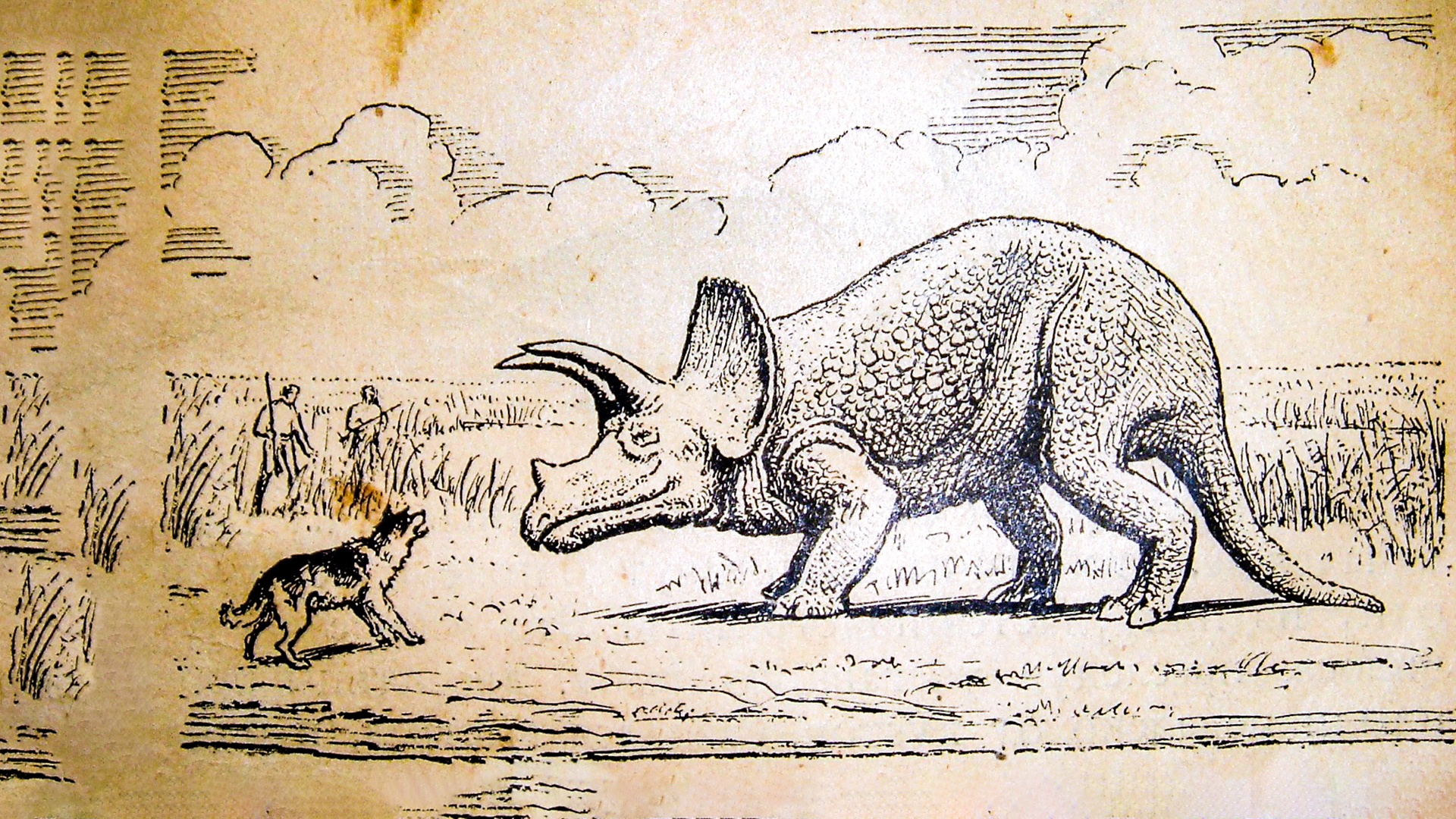映画『オネーギン』をお薦めする5つの理由

1.『エフゲニー・オネーギン』の映像化は稀
映画化されたというその事実だけで、注目に値する。トルストイの『アンナ・カレーニナ』は10数回も映画化されてきたが、プーシキンの傑作『エフゲニー・オネーギン』に取り組む映画監督は稀だ。
というのも、この作品を舞台や映画用に再構成するのは至難の業なのである。最大の困難は、『オネーギン』が全編を通して詩で書かれており、その文面をどう改編しても、天才的な原作への冒涜になりかねないからだ。むしろ、チャイコフスキーのオペラ『エフゲニー・オネーギン』の方が、詩を音楽に合わせたおかげで調和的に感じられる分、映像化される事が多い。
加えて、『オネーギン』は複雑かつ多面的な構成の物語である。最も映像化されやすい本編のラブストーリーのかたわら、本筋からの哲学的な逸脱も多い。また、風景や、農村から上流階級に至るまで生活様式の描写も多く、「ロシアの生活の百科事典」と呼ばれるのも不思議ではない。こうした作品の特徴については、「アレクサンドル・プーシキンの『エフゲニー・オネーギン』を読むべき5つの理由」という記事で詳しく述べられている。
2. プーシキンの文章が活かされている映画

映画が公開されるにあたり、最大の関心事の一つだったのが、プーシキンの詩が実際に映画の中で使用されるかどうかであった。例えば、レイフ・ファインズとリヴ・タイラーが主演した1999年のイギリスの映像化作品には、プーシキンの原作の詩は殆ど登場しない。
本作の脚本を手掛けたアレクセイ・グラヴィツキーは、19世紀の小説のキャラクターたちは、「現代人には理解困難」な言葉遣いであると判断した。そのため、会話は散文に書き直されたが、元のテキストの表現やフレーズを極力使用した。出来は上々だったが、熱烈なプーシキンファンにとっては受け入れ難い事かもしれない。
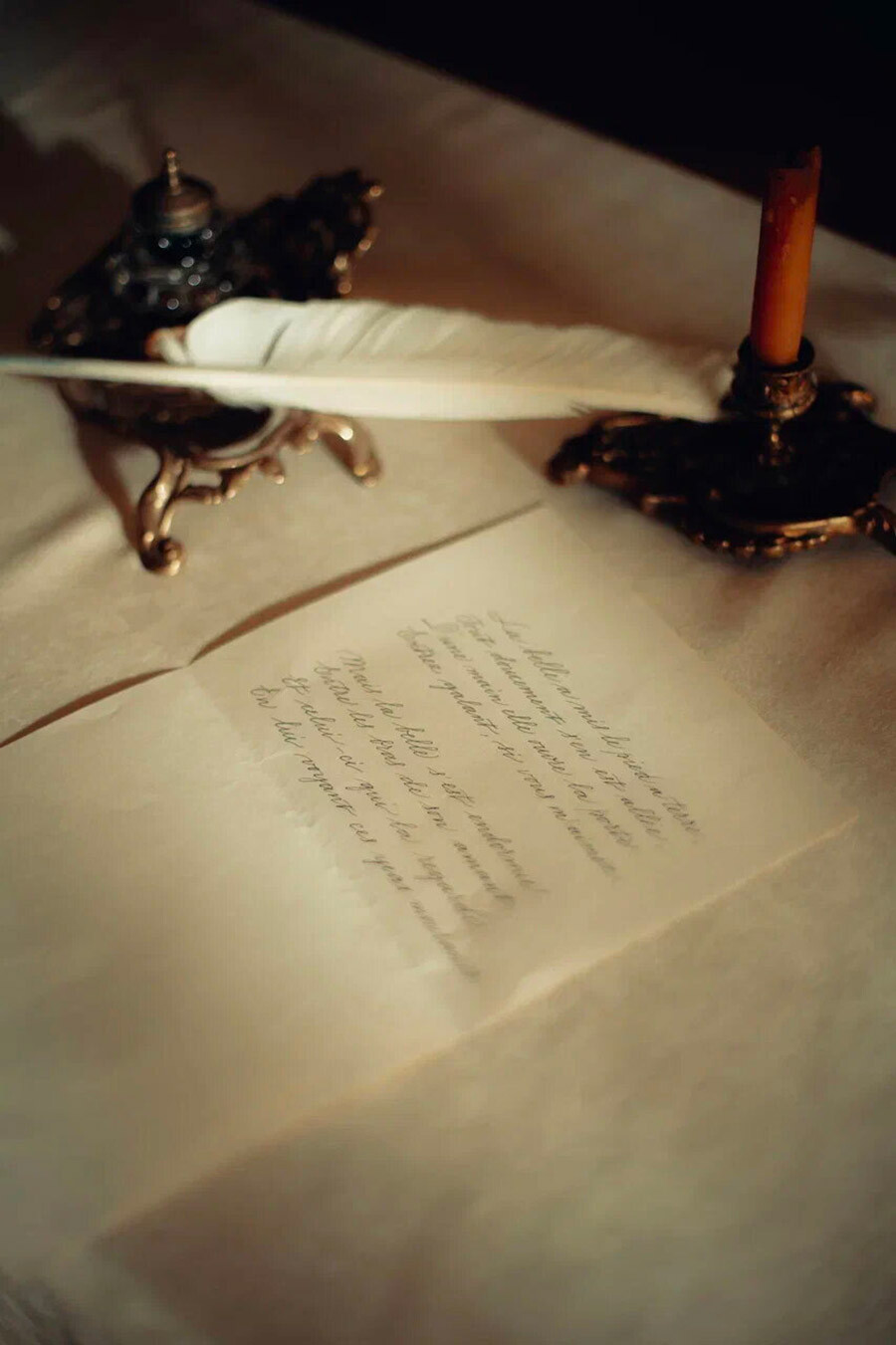
映画の中では、語り手による余談の中で詩が使われている(この語り手は原作にも登場し、プーシキン自身の分身でもある)。
また、作中の偉大な場面である、タチアナからオネーギン宛の、そしてオネーギンからタチアナ宛の手紙の中の愛の告白にも、原作の詩が登場している。
3. 原作のテキストにより近く

映画の大部分は原作のメインストーリーの再現であり、原作に極力忠実かつ、細部まで気を配っている。オネーギンの若年期とサンクトペテルブルクでの生活は簡潔にまとめられているが、作中の「田舎編」や、オネーギンとレンスキーやラーリンらの出会いはかなり詳細に映像化されている。オデッサ旅行中に、オネーギンがレモン汁をかけた牡蠣を食べるエピソードも挿入されている。
ここには、ソ連映画からの輝かしい伝統も垣間見える。ソ連映画では、原作のテキストには常に大きな敬意が払われてきた。中には非常に「忠実な」映像化作品もあったため、試験前に数多の古典文学を読破できなかった学生たちが代用に映画を鑑賞することも少なくなかった(『オブローモフの生涯より』、『戦争と平和』、『犬の心臓』などが代表例)。
従って、プーシキンの原作をよく憶えていない人も、映画を見て記憶を蘇らせるのも良いだろう。
4. 国内の美しいロケ地

監督兼プロデューサーのサリク・アンドレアシャンは毀誉褒貶の激しい人物で、評論家は深みのある作品を期待していなかった。彼の履歴で目立つのは軽いコメディ映画約20作品で、ユーモアの質も高級とは言い難い。
従って、『オネーギン』についても、当初から偏見を持たれていた。しかし観客は自らの目で作品の出来を確かめるべく映画館に詰めかけ、公開後の最初の週末にはロシアとCISで配給のトップに躍り出た。興行収入は3億ルーブルを突破し、アンドレアシャンのキャリアで最大のヒット作となった。
映画の魅力の一つは、そのロケ地にもあるだろう。画面の美しさに免じて、観客は作品の欠点に目をつむったと、一部の評論家が意地悪く指摘するほどだ。
原作の『エフゲニー・オネーギン』は、多様なロシアの姿を描いていることでも名高い。四季を活写し、サンクトペテルブルクの世俗やモスクワの古い街並み、そして村の生活の描写が有名だ。
映画『オネーギン』でも、ロシアの風景描写に力を入れている。オネーギンが滞在した叔父の屋敷があるプスコフ地方の自然の風景は、実際にプーシキンが原作を執筆していた場所でもある。ラーリン家のシーンは、プーシキノゴリエ(プーシキンの山)地区のペトロフスコエ屋敷で撮影された。かつてプーシキンの祖父が所有していたもので、プーシキン自身もたびたび滞在していた。

サンクトペテルブルクとツァールスコエ・セロー宮殿の映像も美しい。一部のシーンはガッチナ宮殿とエラーギン宮殿で撮影された。もっとも、登場人物が貴族とはいえ、王室の邸宅に住まわせたのは、さすがにやりすぎとも言えよう。
5. 年上の役者を起用したのはなぜか
ネット上では、オネーギンの配役について激しい議論が交わされた。問題は、年齢である。原作では26歳の設定だが、演じたのは41歳のヴィクトル・ドブロヌラヴォフだった。

しかしプーシキンの原作では、オネーギンは人生に疲れきった老人のように描写されている。そうした観点からは、年上の俳優は適当な配役とも言えるだろう。ドブロヌラヴォフは貴族的な容姿の持ち主であり、19世紀の貴族として見栄えもする。加えて、ドブロヌラヴォフはモスクワのヴァフタンゴフ劇場の舞台版『エフゲニー・オネーギン』でオネーギン役をもう10年も演じている。役に入り込む時間は十分にあったわけだ。
また、原作での登場当初は17歳程度だったタチアナ・ラーリナを28歳のエリザヴェータ・モリャクが演じたことも、物議をかもした。最も、物語終盤にはタチアナは年齢を重ねるため、より「らしく」見えた。全体的に、モリャクは読書に耽溺する生真面目な令嬢の役を上手く演じたと言えるだろう。