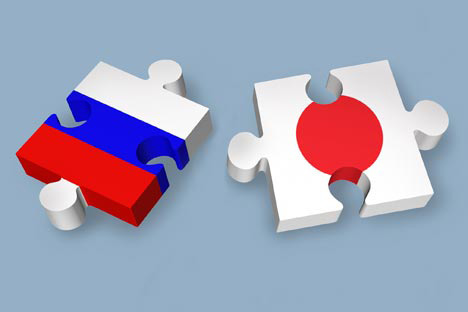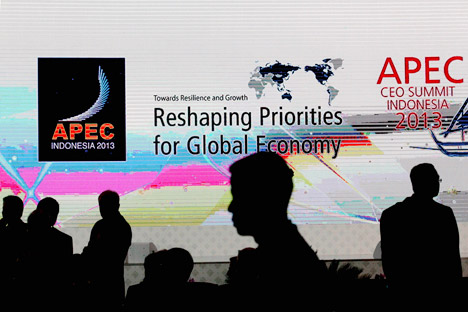「平和条約締結に関する作業を実務的に進める」とは?

写真提供:ロシア新聞
大統領の発言によれば、外務省間の交渉はすでに行われており、11月には、両国の外務および国防担当大臣による「2+2」会合が予定されている。ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は、プーチン・安倍会談は極めて前向きなものであったとし、「テーマが多岐に亘っているため、専門家らは、ひじょうに限られた時間内で、両国の首脳が与える指示を詳細に分析することができていない」と述べた。
同報道官はまた、会談では「平和条約に関する活動を強化する」必要性についても触れられた点を指摘し、「ペテルブルグでは、『勝者も敗者もない(引き分け)』という日本的な考え方が平和条約問題解決のための最良の哲学的ベースとなりうる、と述べられた」と語った。つまり、双方は、それが最良のアプローチであることを改めて確認したことになる。
「引き分け」とは何を意味するか
「勝者も敗者もない(引き分け)」という考え方は、すでに9月のG20サミットにおけるプーチン・安倍会談ののちに示されたものの、会談の参加者自身もドミトリー・ペスコフ大統領報道官も、そうした原則の意味を詳しく説明することはしていない。
モスクワ国立国際関係大学・国際関係学部・東洋学講座主任のドミトリー・ストレリツォフ氏は、『勝者も敗者もない(引き分け)』という考え方には何も新しいものはないとみなし、こう述べる。
「それは婉曲法であり、『私たちは平和と善隣のうちに共存すべきである』というのと同様に何も意味してはいないフレーズです。領土問題の具体的解決は、双方を満足させるような形では、見いだせません」。
「“歴史的勝利”と引き離す可能性」
一方、インターファクス通信のヴャチェスラフ・チェーレホフ記者の解釈は異なり、同氏は、今回のAPECサミットに関する自身の論説記事のなかで、ロシアが領土問題の解決を第二次世界大戦における歴史的勝利と切り離して考える可能性を『引き分け』の原則と関連づけており、勝利における自国の役割のみならずロシアの役割をも強調したがる中国の立場とそうした解釈が相容れない点を指摘している。
将来の平和条約調印に関するロ日対話の活発化、および、相互関係における「勝者も敗者もない(引き分け)」という考え方の双方による受容は、ロシア側から日本側への領土問題における譲歩の原則的可能性に関する議論を呼び起こした。
露側に譲歩の用意はあるのか
雑誌「ナツィオナーリナヤ・オボローナ(国防)」の編集長でロシア国防省付属社会評議会のメンバーであるイーゴリ・コロトチェンコ氏は、ロシアの指導部に領土問題で譲歩する用意があるとはみなしていない。
領土問題における譲歩を支持する者たちは、そうした譲歩に踏み切ることで日本との経済全般およびエネルギー分野の協力拡大による経済的利益に与れるものと考えている。
たとえば、2013年1月、モスクワのカーネギー・センターは、ドミトリー・トレーニン氏とユワル・ウェーバー氏の「ロシアの太平洋の将来。南クリル(南千島)をめぐる問題の解決」という分析的報告を発表した。
そのなかでは、とくに、ロシア経済への日本の国家および民間の大規模な投資と引き換えに、歯舞および色丹をただちに、択捉および国後を50年後に、日本へ引き渡す、という案が示されている。そして、その50年の間に、両島には、この地域の特恵を保障するための経済特区、云わば「アジアの香港」が創設される、という。立案者らの考えでは、そのようにして、「シベリアおよび極東の発展へのアジアの資本の誘致」を保障することができ、これによって、それらの地域に「新しい開かれた非採掘経済創出のための牽引力とモデル」を作りだすことが可能となり、さらには、「目下、北大西洋地域で拡大しつつあるような」安全保障共同体の太平洋版を構築することができる。
ドミトリー・ストレリツォフ氏は、こう述べる。「日本とロシアは、あらゆる協力が互恵の原則に基づいて発展すべきであることを認識しており、平和条約の有無にかかわらず、双方にとって利益となるならば、両国は協力を発展させるはずです」。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。