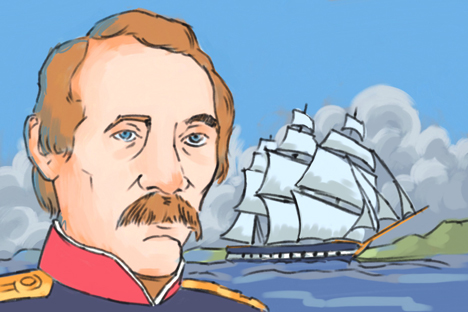可能性の小窓 開く
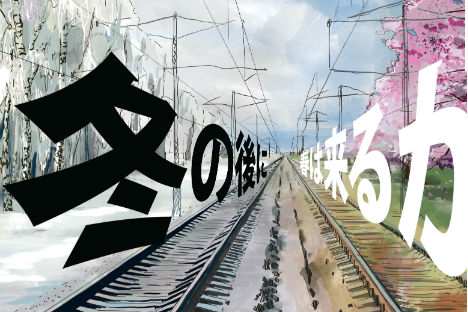
2012年、日露間にはさわやかな海陸風が吹いた。ロシアにおけるプーチン大統領の3度目の就任、日本における自民党の政権復帰は一時忘れられた安定性と堅実性の感覚を両国関係に付与した。
それまでロシアではドミトリー・メドベージェフ氏が大統領を務め、日本では民主党が内閣を形成しており、両国関係にとって試練となった。
12年末から14年初めまでに明らかな進展が達せられた。領土問題をめぐる歩み寄りは見られなかったが、雰囲気は和らいだ。
日本の路線は民主党時代に見られた多方面への急激な突進から解放された。ロシア側のアプローチも落ち着いたものとなった。
つまり、自国の外交面の強硬さを誇示する対象に日本を選んだメドベージェフ氏とは異なり、プーチン氏は対日穏健路線を堅持する姿勢を示した。
90年代と00年代の「島をめぐる」外交は手の込んだ言葉の軽業といった観を呈した。もっとも、00年代前半にロシアは何度かグッドウィル(善意)があれば妥協する余地はあり、1956年にソ連が歩み寄る用意のあった分割のパラメータを再び話し合うこともできるとのシグナルを発した。
しかし、日本はロシアと妥協する必要はなく、より多くを期待すべきであると考えた。プーチン氏もこのテーマに対する関心を失ってしまった。
双方がアプローチするためには何が生じるべきなのか。日本にとってもロシアにとっても、島々は主権と威信の問題である。
それに、国境の見直しが全般的な現象となりつつある今日の状況において、その種の事象は他の係争にとっての先例を創りだす。
係争の領土の多くが第二次世界大戦の所産であり、新たな画定が間接的に同大戦の結果に疑問を付すだけになおさらである。
しかし、問題を地域的文脈で捉えるならば、柔軟性の根拠は現れてくる。
中国の存在感は増しており、これはロシア以上に日本を不安がらせている。ロシアにとっても、馴染みのない状況を創りだしている。
対露制裁での日本の緩さをロシアは認識
ウクライナ危機、ならびにG7や日米同盟の規律に従うという日本にとっての必要性はプロセス全体を凍結した。
ロシアは日本が象徴的な制裁に留めて必要最低限のことを行った点に注意を向けた。
それでも、ロシアを抑制する米国の路線をトーンダウンさせることはできても無視はできず、かねてから協議されていたプーチン大統領訪日問題も宙に浮いた。
現在、日露関係にとって、新たな「可能性の小窓」が開かれた。プーチン氏も安倍氏も新たなチャンスを忍耐強く待っており、再び、プーチン大統領訪日について語られている。
ロシアと日本は客観的に互いを必要としている。その一方でアジア圏が、自分のルールで行動する利益集団へのグローバル世界での断片になってしまうリスクが存在している。
「可能性の小窓」は現代において非常に短命でありえる。
フョードル・ルキヤノフ、「世界政治の中のロシア」誌編集長
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。