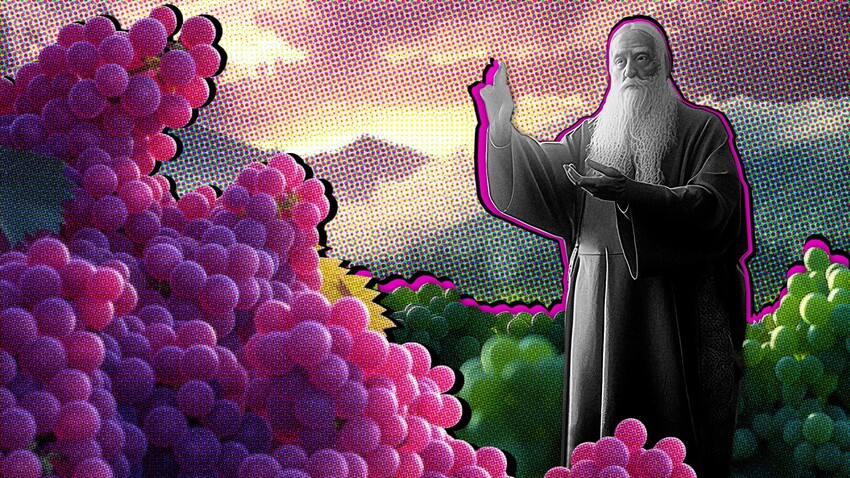
はるか東方の「オポン王国」(「日本」の意味)の領域に、ある国が存在する。そこでは人々が70の大きな島と無数の小島に住んでいる。そして彼らは、総主教と4人の府主教により治められている。「世俗の裁判はない。すべての民族と人々を統治するのは聖権である」
これは、トポゼロ修道院(アルハンゲリスク県)の修道士マルクが19世紀初めにヴェロヴォージェについて書いたものであり、彼自身もその地を訪れたという。彼の書は、「旅人、すなわちオポン王国への道」と題されていた。

アルタイのブフタルマ川周辺。ヴェロヴォージェが位置すると考えられた地域。
Dmitry A. Mottl (CC BY-SA)修道士は、この地を真の「地上の楽園」だとした。ここの住民は、殺したり盗んだりしない。「この地では、略奪、窃盗その他、法に背く行いは存在しない」
なるほど、「冬には、大地がひび割れる厳寒が襲う。また、少なからぬ雷雨と地震がある」。しかし、ヴェロヴォージェは豊かで肥沃である。
「ありとあらゆる種類の果実が生る。ブドウと『ソロチンスコエ・プシェノー(米)』も生る」。「彼らは数え切れぬほどの金と銀、宝石と高価なビーズを持っている」。しかし、 ヴェロヴォージェは、自らを閉ざしており、誰とも戦争しない。「オポンの民は、いかなる者も自分たちの土地に入るのを許さず、誰とも戦わない」
ヴェロヴォージェには、信仰ゆえに追放された者たちが住んでいる。修道士マルクによれば、この国は、「ローマの異端者の迫害から」逃れてきたアッシリアのキリスト教徒によって建てられたという。「多くの者が極北の航路あるいは陸路で」やって来た。そして、ここヴェロヴォージェで、「アッシリア語が用いられる170の教会を見出した」。
ヴェロヴォージェに留まるためには、そこへ辿り着いた人々は、二度目の洗礼を受ける必要があり、その後は当地を離れることは許されない。 マルクによれば、彼自身はそうしなかったが、「私と共にいた二人の修道士は、永遠に留まることに同意し、聖なる洗礼を受けた」。

ブフタルマ川とベレル川
alt-fox (CC BY-SA)ヴェロヴォージェ伝説は、おそらく18世紀後半に、ロシアの古儀式派のさまざまな流派や集団に現れ、口伝えに伝承されたものだろう。書物『旅人』には、一つの伝説のみが記されている。ただし、本文に出てくるピョートル・キリロフ(彼は巡礼を歓迎し世話した)と修道士ヨシフは実在の人物であり、19世紀初めにアルタイの古儀式派の村に住んでいた。そして、ヴェロヴォージェには地理的な言及もある。
17世紀後半、ロシア正教会が「上からの」宗教改革、いわゆる「ニコンの改革」により分裂すると、「ニコン派」と関わりたくない古儀式派は、ロシア各地に逃れた。最も熱烈な人々は、遊牧民に対して築かれたシベリアの要塞線を超えて、現在のノヴォクズネツクとセミパラチンスクのはるか彼方に至り、アルタイにまで達した。
アルタイの僻遠の地――ブフタルマ川沿岸とウイモン渓谷――に定住したロシア人は、「石の民」、つまり山岳民と呼ばれるようになった。当時の言語で「石」は「山」を意味していたからだ。「石の民」の中核は、ニジニ・ノヴゴロドの古儀式派だったが、彼らのコミュニティにはさまざまな地域の人々が含まれていた。彼らは、様々な経路でブフタルマ川の谷に辿り着いた。

「石の民」(アルタイの古儀式派)
Blomkvist, Grinkova, 1927この地域への定住は1720年代に始まった。この地には実際、政府は存在せず、ロシアと中国の曖昧な国境線のはざまに位置していた。住民は狩猟、農耕、漁をし、蜂蜜をつくり、近隣のカザフ人、アルタイ人、中国人と物々交換を行っていた。1790年代にブフタルマ地域がロシアに併合され、税金が課され始めたとき、そこには17前後の集落があった。
19世紀の初めまでに、ブフタルマ沿岸の住民の「自由」は終わった。1791年以来、一部住民が「異邦人」としてロシア帝国に組み込まれて、「ヤサク」(毛皮税)を支払う一方、徴兵と強制労働は免除された。
しかし、この状態はわずか5年間しか続かなかった。1796年からすべてのブフタルマ沿岸の住民が税金を払い始めた。これに対して、多くの人がさらに東と北、アルグート川とカトゥニ川の方面に移動した。

カトゥニ川。18世紀末に「石の民」が移動した地域。
Malupasic (CC BY-SA)つまり、理想郷ヴェロヴォージェは実在した。伝説は真実だと判明したわけだ。ブフタルマ沿岸に行くことは可能だったし、18世紀にここに辿り着けた者もいたのだから。ならば、なぜ人々は、ヴェロヴォージェを探し続けたのか?
18世紀末にツァーリの権力が「石の民」の地に到来したとき、最も信仰の固い者たちはさらに東へ移動し、再び山中に隠れた。どうやら、この「脱出」が伝説に新たな命を吹き込んだようだ。
ちなみに、誰かがついにブフタルマ沿岸に辿り着けたとしても、この場所は通常、「本当のヴェロヴォージェ」とは思われなかった。そこにはすでに税金と世俗の権力が存在していたので。だから、さらに探求し続ける必要があった。

「石の民」(アルタイの古儀式派)
Blomkvist, Grinkova, 1927こうした背景から、19世紀には、手書きの写本で流布した『旅人』のおかげもあり、ヴェロヴォージェ伝説はさらに広まった。
1807年、シベリアのトムスクで、農民デメンチー・ボブイリョフが警察署長のもとへ出頭し、こう告げた。自分は、重大な秘密を知っているが、それはモスクワでのみ明かすことができる、と。モスクワに連行されたボブイリョフが言うには、自分は、ヴェロヴォージェに行ったことがあり、その位置を教えることができる。そこに帝国臣民となるべき数十万人が住んでいる――。
ボブイリョフは、情報提供の見返りとして当局から金貨で150ルーブルを受け取り、ヴェロヴォージェへの遠征に加わることを約束したが、その金を持って失踪した。

「石の民」(アルタイの古儀式派)
Blomkvist, Grinkova, 1927これは数あるエピソードの一つにすぎない。19世紀を通じて、ペルミ、オレンブルク、ニジニ・ノヴゴロドの各県(現在は州)の農民集団が、ヴェロヴォージェを求めてシベリアに逃亡した。彼らは、トムスクの北方の森でこの理想郷を探すことが多かった。1840年代には、アルタイの「石の民」の一部が、理想郷を探しに中国へ赴いた。アジアの中央部の、現在のトゥヴァ共和国でも探索がなされた。
1870年代~1890年代に、山師のアントン・ピクリスキーは、アルカジー・ベロヴォツキー主教と名乗り、極東の古儀式派を騙し、こう主張した。自分は、ヴェロヴォージェで叙聖された、真の古き正教の司祭であると。
ヴェロヴォージェ伝説は今なお有名だ。しかし、現代の研究者たちは、ブフタルマ沿岸の「石の民」の末裔である沿海地方の古儀式派にインタビューしたとき、二度驚かされた。
まず研究者らは、その伝説がまだ生きていることに驚いた。しかし彼らは、次の事実にもっと驚愕する。つまり、「石の民」の子孫はヴェロヴォージェについて、「義にかなった敬虔な地として語ったが、明らかに懐疑的な態度だった」という。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。