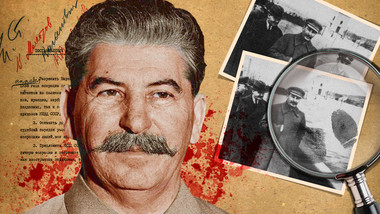日本的!閣僚すげ替え

ニヤズ・カリム
20世紀初めのロシアには「大臣の馬跳びゲーム」というフレーズがあった。専制君主である皇帝の意思による頻繁な大臣更迭のことである。
それがよくないとみなされていた理由は、第一に、大臣が新しいポストに馴染んで仕事の本質を会得することができないためであり、第二に、大臣の首が君主という一人の人間の意向ですげ替えられていたからである。
現在、ロシアでは、国民に人気がなくとも大臣が替わることはまれだが、日本では個々の閣僚については言うまでもなく、内閣がたびたび交替するのが特徴となった。2006年から首相が毎年交替している。
現職の野田佳彦首相は、就任後の一年間にすでに2度内閣を改造した。つまり、全閣僚の辞表を受理し一部を留任させ一部を交替させて新たに組閣を行った。ロシアの政治学者や政治に関心のある人はその意図や理由がのみ込めない。
ワシーリー・モロジャコフ

ワシーリー・モロジャコフ氏(44)は歴史学者・政治学者。モスクワ国立大学大学院博士課程修了。専門は日露関係史。2009年に『後藤新平と日露関係史』(藤原書店)で第21回アジア・太平洋賞大賞を受賞した。現在は拓殖大学日本文化研究所教授を務め、日本人論など論文多数。
両国の政治制度には多くの差異が見られる。日本の憲法は例外を認めながらも閣僚は国会議員の中から任命されることを基本としている。ロシアの法律では反対に、立法権と行政権を混同しないよう閣僚は国会議員になれない。
日本では、自ら担当する省庁の活動分野での一定の経験をそなえた政治家が大臣に任命されるが、その省庁を実質的に取り仕切っているのは役人である。
ロシアでは反対に、元の官僚を含むその分野のプロの人間が大臣に任命されるのが慣例となっている。全くの「文民」であるアナトーリー・セルジュコフ氏の国防相への登用が軍部や多くの政界や社会層において否定的に受けとめられたのもそのためである。
どちらの制度にもそれぞれ一長一短があると思われる。
政治家である日本の大臣は担当省庁において官僚の思惑に左右されないとはいえ、必要な知識と経験に乏しいため、プロフェッショナルな面ではやはり官僚に頼らざるをえない。
その道のプロであるロシアの大臣は官僚たちの手先となりうるが、省庁内で認められたリーダーとして実質的に部下を指揮することができる。
日本では省庁内の人事異動と大臣・副大臣の任命との直接的な関係は薄く、閣僚の辞任によって省庁の日常業務に支障がでることはない。ロシアの大臣の辞任はさまざまなレベルでの大きな人事異動をもたらすのが常だ。
日本の国家機関の機能にとって「大臣の馬跳びゲーム」は危険ではない。しかし、外務、財務、防衛といった国際交渉におけるパートナーの頻繁な交替は好ましくない印象を与え、決定を行うプロセスの安定性に対する疑念を呼び起こすおそれがある。
露日交渉はロシア側からは長年セルゲイ・ラブロフ外相が担当しているが、日本側のパートナーはたえず替わっている。
日本の閣僚はなぜ辞任するのか? それは主に野党からの批判によるものだが、ロシアではこうしたファクターは存在しない。日本の閣僚はなぜ批判されるのか? たいていは、閣僚がその道に精通していないことによる失言のためである。
ロシアの大臣は物言いに気をつけてはいるものの、失言によって大臣の椅子を失うケースはまず見られない。日本の閣僚の辞任原因をおおむね取るに足らないものとみなしている。
日本の閣僚は、自身の職責のみならず政治的責任も肝に銘じるよう努めている。社会が目を光らせているためであり、それは首尾よく機能する民主主義の証である。
一方で、プロフェッショナルな閣僚がもっと多ければ「大臣の馬跳びゲーム」もかなり稀な現象であったに違いない。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。