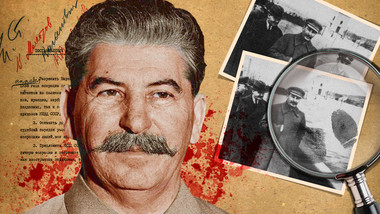響く正教会聖歌

=タス通信撮影
ロシア音楽のルーツの一つは正教会聖歌である。19世紀から20世紀にはチャイコフスキー、リムスキー・コルサコフ、ラフマニノフなどの大作曲家は正教会聖歌を作曲した。なかでもラフマニノフの『晩祷』は日本でもファンが多い。
ここにはロシア聖歌の二つの伝統が集大成されている。それはズナメニイと呼ばれる中世までのユニゾン(斉唱)による単旋律聖歌と、16世紀以後、ロシアが取り組んだ西欧化のもとで生まれた合唱聖歌である。
17世紀から18世紀は西洋音楽を模した合唱聖歌一辺倒であった。19世紀後半に、自国の文化や伝統を見直す動きからズナメニイが再評価され、それをモチーフにした新しい合唱聖歌が生まれた。ラフマニノフの『晩祷』はその最高傑作とされている。
ロシア聖歌の伝統に一か所で触れることができるのがモスクワ郊外の至聖三者聖セルギイ大修道院である。日本人も多く訪れるが、礼拝に参加する人は少ない。できれば泊まりがけで行って早朝の礼拝に出ることをお勧めする。正教会の聖歌は礼拝にあってこそ最高の輝きを見せるからである。朝一番の祈りは、最も古い至聖三者聖堂(トロイツキー・ソボール)で始まる。5時半、黒服の修道士がどこからともなく集まり、巡礼者や近隣の信徒であふれる。
ここでは中世以来の古聖歌ズナメニイが歌われている。歌うのは修道士と併設された神学校の学生。複雑な旋律の動きをイソンと呼ばれるバスの通奏低音が支える。骨太の男声聖歌には前へ前へと歩みを促す力強さがある。革命以後、忘れ去られていたズナメニイ聖歌はペレストロイカ以後、再評価された。
敷地内で一番大きな聖堂、生神女就寝大聖堂(ウスペンスキー・ソボール)では、朝8時頃から合唱聖歌で聖体礼儀が行われる。
日曜日や祭日には「祭日聖歌隊」と呼ばれる、よく訓練された聖歌隊がイコノスタシスの左右両脇に分かれ競うように歌い、きらびやかな祭服の聖職者が行き交う。フランスの作曲家ベルリオーズが「声のオーケストラ」と驚嘆したロシア合唱聖歌の系譜である。かつてビザンチン帝国にでかけたキエフ・ルーシの使節が「天にあるのか地にあるのかわからない」と評した美しい正教の礼拝が生きている。
礼拝中であっても聖堂の後ろから静かに入ってゆけば見学できる。女性の場合はスカートとスカーフ着用が望ましい。最近日本語の美しい小冊子も出版され、院内の書店で入手できる。
*ロシアNOW特別寄稿
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。