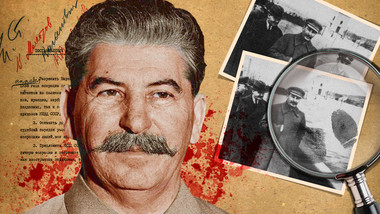「フクシマ」:4つの次元の危機

=AP撮影
2011年3月11日の地震は、日本で記録された最大の地震であり、それに続いた津波は、破壊の規模、犠牲者の数から言っても、超巨大なものであった。だが、それが日本の土台を揺るがすことはなかった。地震、台風、津波は、すべて日本の文化、経済、歴史の一部であり、日常生活の一部なのだ。
日本が新しい現実に直面したのは、10メートルの津波が太平洋に直近の岸にあった原子力発電所を襲ったあとのことだ。津波は通常の電力供給を停止させ、原子炉の非常冷却システムに電気を送る非常用ディーゼル発電機を破壊した。非常用ディーゼル発電機は、わずか海抜6メートルのところに設置されていたのだ。電源喪失の結果、3基の原子炉に炉心溶融がおきた。事故はIAEA(国際原子力機関)の評価尺度で最高のレベル7になった。大気、土壌、沿岸海水への放射性物質の放出量は、チェルノブイリの20%に達した。
「フクシマ」の事故は、必然的に原子力産業全体の危機になった。原発は総電力の30%を供給していたが、現在稼動している原子炉は52基のうちわずか2基であり、その他の原子炉はストレステスト実施のため停止中だ。稼働中の2基も4月までに停止する可能性が否定できず、原発がいつ事業を再開するかはわからない。現地市町村からの原子力産業に対する反対運動は絶大だ。
一方、輸入問題も厳しさを増している。日本政府はすでに米国の圧力により、対イラン制裁に加わり、全石油輸入量の10%を占めるイラン石油の輸入削減に実質的に同意した。さらに、イランとサウジアラビアの潜在的抗争が緊迫化し、イランに不安定化の兆候があるなど、全体として中東の政治情勢が動き出しており、この地域における米国の立場は複雑になってきている。これらすべての背景には、中国、インド、韓国のますます高まる石油需要がある。
危機克服の一案として、ロシアとの協力が検討されている。日本の野田佳彦首相は震災一周年の記者会見で、「日本とロシアは、とくにエネルギー分野で協力を拡大していく展望がある。(中略) 私たちはこれについてロシアの指導者らと話し合い、両国がこの作業を進めねばならないという同一見解に達した」と述べた。
日本はつねにシベリアの石油、ガスを期待して、サハリン大陸棚の開発に参加してきた。震災のあと、ロシアは日本の求めに応じ、日本への液化ガスの供給を大幅に増やした。極東ですでに2つ目のガス液化工場の建設をめぐる交渉が活発化している。12月には「東シベリア・太平洋」石油パイプラインが完成し、極東のコジミノ港に達する。両国関係を質的に飛躍させる客観的(地理的、資源的)基盤は存在する。
しかし、問題は対ロ関係の質的発展が、日本ではつねに領土問題の解決と結びついていたことだ。一方、米国はエネルギー産業における相互利益に基づいて近隣諸国との関係を築いていこうとするロシアのすべての試みに対して、極めて病的な態度をとっている。それは、すでにヨーロッパで示された、ロシアからのガスパイプライン建設の協議に対する態度と同様だ。
したがって、日本がロシアとのエネルギー協力を決定するためには、戦後つねに日本にとって唯一の安全保障国であり続けた米国の見解も考慮しなければならない。
フクシマの事故は、国家と社会の根幹に触れ、日本は経済、政治、安全保障、社会意識の各次元で試練に直面することとなった。こうした試練を日本がうまく処理していけるどうかは時間が示すことだが、恐らく、これまでと同様、全てを平穏無事に保っていくに違いない。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。