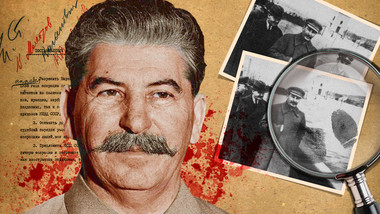ウラジオストクで露日シンポジウムが開催された

19回目のシンポジウムには、ロシア科学アカデミー極東分院・極東民族歴史考古民俗学研究所が参加した=写真提供:ihaefe.org
テーマが共通することで問題の検討がいっそう深まるよう、今回は、報告者がペアで選ばれた。
駒澤大学の杉山秀子教授は、「ジェンダー的観点から見た出生率低下に対するプーチン大統領の政策」という報告を行い、ロシア科学アカデミー極東分院・極東民族歴史考古民俗学研究所のアンゲリーナ・ヴァシチューク教授は、「ロシアの人口動態学的チャートにおける極東地域」という報告を行った。討論の参加者たちは、現在、ロシアにおける過疎のプロセスは鈍化したものの停止してはおらず、極東地域では人口動態学的に不安定な状況が保たれている、との結論に至った。ロシアの人口動態学的チャートにおいて、極東は、アウトサイダーであり続けており、これが、国家的安全保障を脅かしているという。
青山学院大学の羽場久美子教授は、「政権交代と領土問題、外国人嫌悪と戦争」という報告を行い、ロシアのアナトリー・サーフチェンコ氏は、「権力の合法性、軍事的、領土的、政治的次元」という報告を行ったが、羽場氏が、問題の解決における学者の役割と理性に期待しているのに対し、サーフチェンコ氏は、領土問題は国家にとってきわめて頭の痛い問題であるという点を重視している。地政学的な面で、近い将来、ロシアから何らかの譲歩を期待することが難しいのは、国内の合法的体制が、多くの点で、ソ連邦崩壊後の国の姿勢の現実的なもしくは現実的と思われる回帰の上に築かれているためである。
天理大学の五十嵐徳子教授の「日本と比較した出生率の低下と国民の老齢化の観点から見たロシアのジェンダー的状況」という報告とラリーサ・クルシャーノワ氏の「ロシアにおける老齢化の問題と年金改革」という報告は、国民の老齢化の問題に関するもので、両者とも、ロシア国民の年金保障の状況に懸念を表し、国家がそれに基づいてこの問題を解決しうる方策を分析した。
新潟大学の道上真由教授の「ロシアにおける住宅問題」という報告と、スヴェトラーナ・コヴァレーンコ氏の「家庭生活における住居、幸福か必要か」という報告は、ロシアにおける住宅建設の問題を扱っていた。
討論の参加者らは、すべてにおいてコンセンサスを見いだしたわけではないが、ロシア科学アカデミー極東分院と関西地域の歴史学者と経済学者による19回目の露日シンポジウムはひじょうに実り多いものであったとの見方では一致し、大阪市で開催される次の節目となる20回目の会合では、こうした討論が継続され、双方が二国間関係の問題の認識において一致点を見いだせるよう、希望を表明した。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。