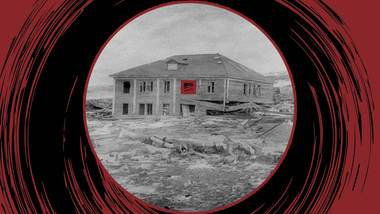厳しくも悲観するな

ダン・ポトーツキー
今年4月、プーチン大統領と安倍首相はモスクワでの首脳会談で、現在に至るまで露日間で平和条約が締結されていないのは異常な状況であると認め、「両国に受け入れ可能な形で最終的に問題を解決し」、平和条約を結ぶことで合意した。
8月19日にはモスクワで外務次官級交渉の第1ラウンドが行われる。報道によると、領土問題での双方の立場は根本的に異なっている。
もっと読む:
ロシア側は、クリル諸島で共同の経済活動を確立する可能性について話し合うことを提案したが、日本側は不同意を表明し、自らの提案を繰り返した。つまり、「歯舞、色丹、国後、択捉の4島は日本に帰属するとの原則的立場から、妥協可能なのは、4島の返還の条件と時期のみである」とした。
こうした両国の立場を比較すると、双方に受け入れ可能な合意に達するのは非現実的だと結論せざるを得ない。
交渉に当たってのポイント
だが、それほど失望するには当たらない。その理由は第一に、これだけ複雑で鋭い対立をはらんだ問題の交渉は長期にわたる緊張したものとなることを前提にすべきだからだ。
第二に、交渉は専ら非公開の形で行うべきだということだ。両国の世論をいたずらに刺激することを防ぐのがその理由。
第三に、両国関係をあらゆる分野で積極的かつ大規模に発展させていくための努力が極めて重要だ。
第四に、一部の政治家や政治学者は、どちらの国が国境画定と平和条約締結により関心があるか、従って「譲歩せざるを得ないか」といった議論を好むが、こういうものに引っ張られてはならない。
だから、交渉の見通しについて悲観する必要はない。日本の内政が安定し、「毎年首相が交替する」時期が終わったことも重要だ。プーチン大統領の任期は6年ある。一方、安倍氏は3年間は首相を務められる。
何によらず交渉というものはユニークで意外でさえある解決を生み出すことができるものだ。
日ソ共同宣言をたたき台に
交渉の参加者に助言を与えても、あまり報われないのが常だが、次のことを提案できる。平和条約締結問題の解決の選択肢として提示された事柄を見直してみてはどうかということだ。その中には、1956年の日ソ共同宣言の第9条「領土について」を検討することも含まれる。
この共同宣言は、二国関係の要をなす主要な法的文書だ。現時点では、誰も平和条約問題を解決する「魔法の形式」は持っていない。平和条約締結交渉の参加者たちには、忍耐と粘り強さをもって、良い成果を上げられるように願ってやまない。
アレクサンドル・パノフ、元在日本ロシア連邦大使
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。