ロマノフ朝のツァーリたちについての小咄:事実と虚構のはざまで生まれた真実
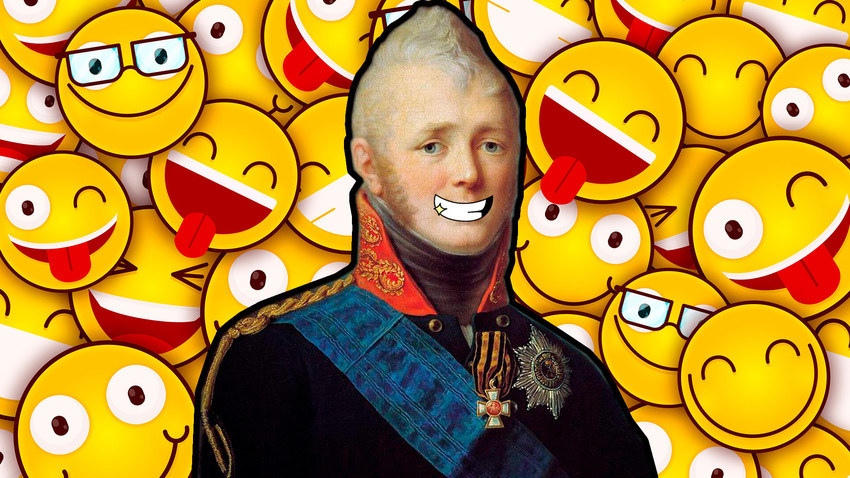
歴史上の逸話は、真実と虚構を区別することはいつも難しい。このジャンルは特殊な性格をもっていて、事実と憶測が混ざり合っている。つまり、実際に起きたことと、起こり得たこととがごたまぜになっている。
にもかかわらず、これらの逸話、小咄、ジョークは常に、人々が歴史的人物に抱いていたイメージを反映している。つまり、人々が自分たちの支配者についてどのように感じ、考えていたのかをよく示しているわけだ。
だから、ロマノフ家の小咄の世界をのぞいてみていただきたい!それは栄光に満ちてもいれば、哀れでもあり、狡猾でもあれば正直でもある。このように、同時代人の目には映っていたのだ。
ピョートル1世(在位1682~1725)

ピョートル大帝は、新首都サンクトペテルブルクを築き、宿敵スウェーデンを破り、ロシアを欧州列強の一国に変貌させた。彼は疲れを知らず、厳格で、賢明な帝王だと信じられていた。いくつかの逸話によれば、この才能あふれるツァーリは、臣民の暮らしをよりよく知るために、ありふれた平服で街を歩き回っていたという。そんな逸話の一つは次のようなものだ。
あるときピョートル大帝はお忍びで居酒屋に出かけた。そして、一人の兵士とビールを飲んだ。兵士は剣を質に入れていた。彼はピョートルをその辺の酒飲みと思い込んで、こう言った。「しょうがねえから、木の棒を鞘に入れて閲兵に出るよ。誰も気がつきゃしねえさ。その後で、質草を取り戻すとするさ」
翌日、軍事パレードがあった。ピョートルは皇帝としてパレードに臨んでいたが、例の兵士に気がつき、彼を立ち止まらせたうえで命じた。「お前の剣で私を撃て!」。兵士は恐怖で蒼白となり、ぶるぶる震えた。だが、皇帝は繰り返した。「撃て!さもなくば縛り首だぞ!」。やむなく兵士は「竹光」を握り、叫んだ。「天にまします父よ、奇跡を起こし、この武器を棒にお変えください!」。そして彼が、木の棒で皇帝を叩くと、もちろん棒はばらばらに割れ、皇帝は無傷だった。誰もがショックを受け、司祭は祈りを捧げた。「神が皇帝を救いたもうた!」
ピョートルはニヤリと笑い、兵士に囁いた。「お前はけしからんやつだが、頭は切れるな」。そして「汚れた鞘のため」、営倉に5日間入れた後で、航海学校に送った。
パーヴェル1世(在位1796~1801)

この皇帝は、ドイツ風の規律が大好きで、とても厳格だと思われていた。この残酷な逸話はそれを証明する。
騎兵大隊がロシアの農村に停止した。ところが村には、馬に食わせる飼料がないことが分かった。ただし、一人の商人の家にはあったが、非常な高値でしか売らないという。大隊長は、干し草を徴発せよと命じ、「その商人は縛り首ものだな!」と愚痴った。兵士たちはそれを文字通りの命令と受け取り、商人を絞首刑にしてしまった。大隊長はこの嘆かわしい事件の顛末を報告した。
まもなく、パーヴェル1世はこの件に関する命令を公表した。まず第一に、愚かしい命令を出したかどで、大隊長(大尉)を降等処分とする。しかし第二に、大隊長を少佐に昇進させる。なんとなれば、「愚劣極まる命令さえ直ちに実行されるような、優れた規律を徹底したからである」
アレクサンドル1世(在位1801~1825)

パーヴェル1世の息子、アレクサンドルは、1812年に祖国戦争でナポレオンを破った後、欧州の輝ける星となった。それに関連した話がある。
ナポレオンは1812年にロシアに対し戦争をしかける前に、駐ロシア大使として、側近アルマン・ド・コランクールを派遣し、次の手紙を送った。「フランスはかつてなく平和であり、軍備、兵力を増強していない」。コランクールは、ツァーリにそのことを納得させに赴いた。
その時までにアレクサンドルはすでに、ナポレオンが戦争の準備をしていることを知っていた。そこで彼はコランクールに答えた。「大使、それは私のもとにあるあらゆる情報と矛盾している。だが、貴下がそれを信じると言うなら、私も考えを改めることにしよう。私は貴下を信じているから」
恥じ入ったコランクールは何も言えず、立ち上がり、一礼して謁見室を去った。
ニコライ1世(在位1825~1855)

ニコライ1世も厳格をもって鳴り、いわゆる鉄の拳で帝国を支配していた。詩人アレクサンドル・プーシキンがこのツァーリについてこう言ったほどだ。「彼の心の中には多数の下士官と、小さなピョートル大帝が住んでいる」。にもかかわらず、ときどきニコライは本物のウィットを発揮することがあった。
あるとき何人かの小姓が玉座のある部屋で遊んでいた。誰も来ないだろうと思っていたら、突然、ニコライその人が現れ、玉座に座っていた少年の耳をひっつかんだ。縮み上がった少年は厳罰を覚悟したが、皇帝はただ笑って言った。「この椅子に座るのは、お前が思うより楽しいものではない」
***
兵士が、居酒屋で酔っ払って騒いでいた。彼のすぐそばにニコライ1世の肖像画がかかっていた。そこで、人々は彼を落ち着かせようとした。彼らは壁にかかっているツァーリの肖像画を指し、陛下がここにあらせられるのに、畏れ多いじゃないか、と言った。すると彼は、 「皇帝なんかどうでもいいや。唾してやる!」と言い放った。その後兵士は眠り込み、やがて拘留された。ところが、ニコライ1世は、事件を耳にすると、こう言っただけだった――「あの兵隊に言ってやれ。私もお前に唾をひっかけてやると。そして、居酒屋に私の肖像をかけるのはやめさせろ」
(ニコライ1世ではなく、アレクサンドル3世についての話になっているバージョンもある)
***
ロシアに蔓延する汚職に怒ったニコライ1世はかつて、皇太子にこう言った。「帝国で盗みを働いていないのは二人しかいないと思うことがあるよ。お前と私だけだ!」
アレクサンドル2世(在位1855~1881)

この皇帝は、農奴制を廃止したことで知られるが、こう言ったと伝えられる。「ロシアを支配するのは難しくないが、まったくの徒労だ」。彼のユーモアは概してとてもペシミスティックだった。
アレクサンドル2世は、ロシアの小さな町を訪れたとき、重要な勤行が執り行われている教会に行くことにした。建物はごった返しており、地元の警察署長は、皇帝の前の群衆かき分けながら進み、陛下のために道を開いた。「敬礼!敬礼!」と署長は叫びながら、道をふさぐ人々を片端からぶん殴った。署長の言葉を聞いた皇帝は、笑いながら、ロシアではいかに礼儀が教え込まれているか、ちょっと分かったよ、と言った。
アレクサンドル3世(在位1881~1894)

アレクサンドル3世はしばしば、ロシアの男の中の男と呼ばれた。堂々たる巨躯で、巨大な髭をたくわえ、怪力の持ち主だったから。だが実は、ロマノフ朝後期のツァーリの多くがそうであったように、彼の体内には、ロシア人の血はほとんど流れていなかった。
あるときアレクサンドル3世は、自分のルーツについて歴史家に非公式に尋ねた。
「パーヴェル1世の父親は誰かな?(パーヴェル1世の母、エカテリーナ2世は、夫ピョートル3世と不仲だった。そして、パーヴェルの父が彼女の愛人の一人であるという噂は、巷間で広く取りざたされていた)」
「陛下にお隠し申し上げることはできませぬ。…陛下の曽祖父はセルゲイ・サルティコフ伯爵であるとの風説が行われております」
「神に栄光あれ!それが真実であることを望む。もしそうであるなら、私の体内にロシア人の血が多少は流れていることになる」
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。