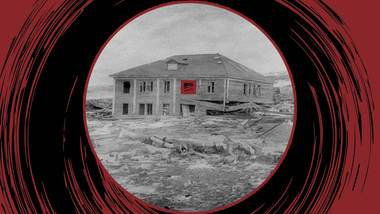帯広から画像診断

写真提供:沿海地方行政府の公式サイト
日本側は社会医療法人北斗(北海道帯広市)が中心的役割を担ってきた。利用者数を確保し、順調な滑り出しを見せている。
センターでは日本製の磁気共鳴画像化装置(MRI)、コンピューター断層撮影(CT)、超音波検査(エコー)などを備え「人間ドック」の検査に対応できる。
検査画像をインターネット経由で日本に送り、北斗病院にいる専門医の判断を仰ぐ。
現地の日本人スタッフは技師2人、事務員1人。既存の建物を改装した施設内は広々とし、清潔な印象を与えている。
利用者数は開業の6月上旬から10月中旬までの5カ月弱で延べ約1600人と目標を超えた。
内訳でいえばドックよりも一般診療の方がまだ多いが、施設の認知度と共にドック利用者も増えているという。
開業当初の6月のドック利用は14人だったが、ここ1、2カ月は30人前後と倍になった。
センターを運営する合弁会社のデニソワ・スベトラーナ社長は「極東ロシアにもドック施設はありますが、高度な検診機器の絶対数が少ないせいもあり、一つの検査が終わったら別の検査を受けるために違う医療機関に行かなければならない状況でした」と話す。
1カ所で高レベルな検診ができる上、診断に日本の専門医が関わる仕組みもあるのが、北斗のセンターの強みだ。「狙い通り、人気が出始めています」とスベトラーナ社長は太鼓判を押す。
今後は機械のさらなる拡充や検査メニューの充実を図るという。また、企業や団体と契約して職員の健康診断に使ってもらうなど、営業的な作戦も練っているところだ。
運営会社に出資するのは、ロシア側が現地の保養所「ストロイチェリ」と建設機械商社「アキラ」の2社。日本側は北斗とロシア専門商社ピー・ジェイ・エルの2社だ。2012年初頭に合弁を立ち上げ、1年以上かけて開業にこぎつけた。
世界保健機関(WHO)によると、ロシア国民の平均寿命は69歳(男性63歳、女性75歳)=2011年。以前より長くなっているとはいえ、健康悪化の初期段階で手を打つのが遅かったために起こる病気や、それによる死亡はまだまだ多い。
日露の医療関係者同士が手をたずさえ、ロシアの予防医療を発展させることは2国間関係を前進させる大きな要因になるだろう。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。