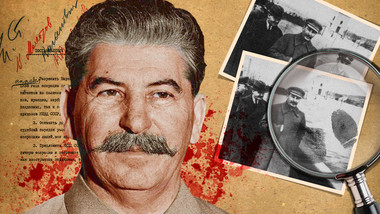ファベルジェだけじゃない

カルル・ファベルジェの作品=www.art1.ru、Vostock-Photo、Fotodom
19世紀半ばまで、宝石職人という仕事は、ごく普通の職人と見なされていた。しかしその後彼らが国際展示会に参加するようになると、彼らの名は一躍商業的ブランドとなったのである。
ストックホルム・シンドローム
スウェーデンの宝石職人ボリン一族が、ファベルジェに先立つこと数十年、19世紀初めに来露した。複雑なのは、彼らが6人もの皇帝に仕えたことである。そうそう容易い仕事ではなかったに違いない。例えば、皇帝の娘に持参金となる宝飾品も用意しなければならなかっただろう。婚礼のための宝飾品一セットで、ペテルブルクの屋敷一軒分くらいはした。その一セットには婚礼の冠、いくつかの皇族の冠、頸飾、ブレスレットなども含まれていた。その他に、指環やイヤリングも必要だったに違いない。婚礼前夜、皇女の新しい宝飾品はすべて検分のため陳列された。古い習慣では、花嫁の価値は、その持参金の額によって決められたのだった。
ボリン一族の宝石工房は第一次世界大戦直前まで続けられ、当時、会社のオーナーでドイツに在ったウィルヘルム・ボリンは戦争の開始に直面した。ボリンはスウェーデン経由でロシアに入ろうとしたが、ストックホルムに滞留することとなり、そこで店を開き、すぐにスウェーデン王室御用達となった。こうして彼は別の君主に仕えることになった次第。
ロシアン・スタイル
商人パーヴェル・サジコフの宝石工房は1793年創立と知られている。1851年、彼の息子イグナーチーは農民の風俗をモチーフとしてつくった作品をロンドンでの展覧会に出品した。その中には熊と熊使い、牛乳を搾る女性、クリコヴォの戦いを記念したシャンデリアなど、国民的ないし民芸的作品があった。このシャンデリアで彼は銀メダルを受け、名士としてペテルブルクに凱旋したのだった。
Vostock-Photo、ロシア通信撮影
あのロンドンで認められたのなら、天の声である! 宮廷の人々は先を争って彼に注文をした。「単なる職人」に、ではなく、他でもない「ロンドンで受賞した宝石職人」に。
しばしばロシア語よりもフランス語を能くした彼らロシア貴族だが、彼らはこのようにして自分たちのロシア性を強調することができた。ロシアのスタイルが、このような一定の流行を利用したものであったことは、特に驚くべきことではない。西欧の人々にとってもこれらは「à la russe(ロシア風)」として好まれた。また同じく宝石職人イワン・フレーブニコフは1873年、ウィーンの展覧会でサモワールとティーセットを出品し、それを見た観衆に深い印象を与えた。サモワールは雄鳥の足を象ったもので、取っ手の部分は雄鶏の頭の形につくられていた。また大きなカップは高価な石やエナメルでデコレーションされていた。その美しさを認め、また賞賛しない者はなかったという。フレーブニコフは展覧会から帰ると、定期市の雄鶏のモチーフには満足し、新たな着想でまた仕事に取りかかった。
彼は作品の主題にイワン雷帝や、正教の聖人であるラドネジの聖セルギイの生涯、またレールモントフの詩を選ぶなど、歴史や文学を題材とした。しかしフレーブニコフの作品で何より興味深いのは「七宝(しっぽう)」である。国立歴史博物館にはフレーブニコフによる1870年代のワイン用道具が保存されているが、雄鶏の形をしたデキャンタとヒナの形をしたグラスは、シャンルヴェ(金属のエッチングをエナメルで埋める技法、象嵌七宝)の技法で装飾されている。この技法は、金や銀の皿へのデコレーションにも使われている。
出世譚
七宝はパーヴェル・オフチンニコフの作品にも顕著である。職人たちに特に名誉をもたらしたのは、クロワゾネ(地の金属の上に金属線で輪郭を描き、エナメルで埋める技法。有線七宝)やペイントエナメル(焼き付けたエナメルの上にさらにエナメル画を描き、焼く技法)、プリカジュール(金属箔の上にクロワゾネを施し、焼いた後に箔を取り除いて七宝の部分だけを残すことでステンドグラスのように仕上げる技法。省胎七宝)の技術だった。クロワゾネの技法はキエフ・ルーシの時代にすでに使われており、元はビザンツからもたらされたものであったが、タタールの襲来により失われていた。その復元に成功したのが、まさにオフチンニコフであった。
Press Photo、タス通信撮影
彼の運命は数奇なものだった。彼は農奴の家庭に生まれたが、少年の頃にはすでに絵画の才能を見せ、貴金属職人の道へ向かった。8年間の労働で貯蓄をつくり、賦金を払って農奴の身分から解放されると、結婚して自らの工房を開いた。
オフチンニコフが24歳のとき、彼の工房の一年の取引高は50万ルーブルに達した。今日の金額に換算すれば、映画『タイタニック』が撮影できるほどの金額である。このとき彼の工房では600人、あるいはもっと多くの人間が働いていた。35歳になると、オフチンニコフは帝室御用達の職人となり、名誉市民の称号といくつかの勲章を受章した。
1917年の革命の後、宝石職人たちは国外へ出て行った。飢饉、混乱、そして困窮する労働者のために行われた革命後の貴金属の徴発の中、仕事を続けることなど到底不可能であった。次第にソ連の貴金属工業は復活していったが、それはすでに全く別の流儀、そして全く別の美学をもつものであった。ツァーリの宝石職人たちがつくった高雅なスタイルは、今や博物館と一部のコレクションに残るのみである。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。