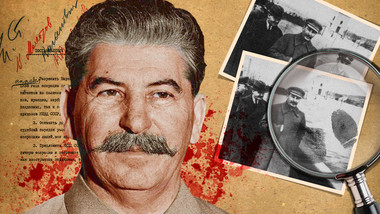トルストイがインターネットを見たら

ウラジーミル・トルストイ氏=ロシアNOW撮影
ウラジーミル・トルストイ氏
ウラジーミル・トルストイ氏は、モスクワ国立大学卒のプロのジャーナリスト。すでに20年間、トゥーラ州にあるトルストイ生家・博物館「ヤースナヤ・ポ リャーナ」の館長を務めている。2012年にロシア連邦大統領文化顧問に就任。レフ・トルストイの専門家で、アカデミー賞にノミネートされたマイケル・ホフマン監督の映画「終着駅 トルストイ最後の旅」(2009)のアドバイザーを務めた。
-ロシアNOWはトルストイについての記事をよく掲載しますが、読者はトルストイをとても愛し、ロシア語でしか本を書いていないことを時に嘆いています。トルストイはフランス語に堪能だったという話は知られていますが、他にどのような外国語を知っていたのでしょうか。
高祖父は、レベルの違いこそあるものの、13ヶ国語を自由に操っていました。フランス語とドイツ語が得意でしたし、英語もよく知っていました。そのほかには珍しい言語、より詳細にはタタール語や複数のスラヴ語を知っていましたし、古代ギリシャ語を学んで、その本も読んでいました。これらはすべて独学で習 得したもので、独自の外国語学習法というものがありました。
「ヤースナヤ・ポリャーナ」の図書館には37~38ヶ国語の本がありますが、そのうちの多くに高祖父の読んだ跡や書き込みが残っているので、ただ置いておいたわけではなく、実際に読んで活用していたことがわかります。
-その外国語学習法について、少し教えていただけませんか。
文学作品を読みながら語いを増やし、翻訳をしていました。これは独自の方法なので、今再現するのは難しいです。ただ、それで語学学習はうまくいっていました。
-トルストイは西欧とその作家について、どのように考えていたのでしょうか。「ヨーロッパの文明とは深淵への道」と言っていたというのは本当ですか。
高祖父は作家と文学に対して深い尊敬の念を抱いていましたし、若いころはルソーの思想に夢中になり、ヴォルテールやモンテーニュの作品をよく知って いました。文芸作品ではディケンズが好きで、子どもにはジュール・ヴェルヌを読んで聞かせていました。ホメロスの『イーリアス』や『オデッセイ』を原語で読もうとし、文章の中に浸るにつれ、大きな快感を得ていたようです。最初は何となく読み始めたのですが、原語と文脈を理解し、感じ取るにつれ、夢中になっていきました。
-トルストイはとても情熱的な人物でした。現代のグローバル化、インターネット、さまざまなできごとなどについて、何を言うと思いますか。
『復活』の冒頭
「何十万もの人間が、ちっぽけな一つところに寄り集まって、自分たちのひしめきあっている土地を醜くそこねようとどんなに努め、その土地に何一つ育たぬように石を敷きつめ、芽をふく草を片っぱしから摘みとり、石炭や石油でくすぶらせ、木々を切り倒し、動物や鳥を残らず追い払ってみたところで、春は都会の 中でさえやはり春だった」
想像するのは難しいですが、長編小説『復活』の最初に書かれている予言的な数行を読む限り、進歩のための進歩を、どこにも導かぬ道と考え、否定的にとらえていました。したがって、現代の多くのことが、高祖父を失望させたのではないでしょうか。
ただ、ここで申しあげておかなければならないのは、高祖父は頑固一徹な保守主義者ではなく、常に新しいものに関心を持っていたということです。初めて映画が現れた時、映画がもっと早くできていれば、すっかり忘れてしまった自分の母のおもかげを残せておけただろうに、と考えました。母が亡くなったのは、高祖父が1歳半の時です。生きた人間とその会話の様子をフィルムに残し、その記録を呼びだすことができるとすぐに悟りました。
インターネットには強い関心を示したでしょう。いらだたせたり、怒らせたりするものもあったでしょうが、これほどの情報と可能性の集中は、きっとおもしろく感じたでしょう。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。