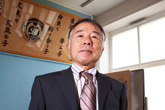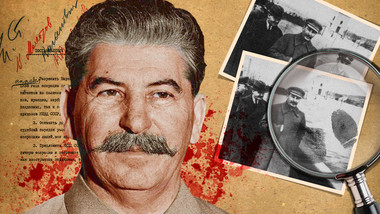学生の祭日「聖タチアーナの日」に因み

とくに怠け者の学生は、「タナボタ」に期待する、つまり、何の努力もせずにいい点を取ろうとする=タス通信撮影
1.試験の前には頭を洗わない
でないと、「知識がみんな洗い流されてしまう」。可哀そうなのは女子学生で、彼女たちは、帽子をかぶったり頭をスカーフで覆ったりと、あの手この手を考える。試験の前に髪を切らず、男子なら髭を剃らないのも、効果てきめん。試験期間中「着たきり雀」の学生もいる。その代わり、試験の終わりには、頭を洗わず、髭を剃らず、髪を梳かさず、よれよれの服を着た学生たちは、自分の見事な知識に胸を張ることができる。
2.犬の鼻をなでる
モスクワの地下鉄駅「革命広場」のそばにある国境警備兵の銅像のライフル銃の遊底と牧羊犬の鼻に触れれば試験に受かるという伝説もある。たしかに、この銅像を見ると、遊底と鼻面の辺りが、何世代もの「巡礼」の学生たちに触れられて、なんとなく黄色っぽく光って見える。
3.開いた教科書を枕の下に
試験前の「一夜漬け」には、開いた教科書を枕の下に忍ばせるとよい。知識が形而上学的に頭のなかへ沁み込んでいくという。冬場なら、ヨールカ(新年のツリー)に玩具の飾りではなく要点の抜き書き帖を吊るすという手もある。
4.タナボタよ、つかまれ!
とくに怠け者の学生は、「タナボタ」に期待する、つまり、何の努力もせずにいい点を取ろうとする。しかも、文字通りにそれを手に入れようとする。試験前日の真夜中に窓を開け、成績簿を手に持って「タナボタよ、つかまれ!」と三度叫ぶ。ただ、寮の場合は少々難しく、隣の窓からライバルたちに「タナボタよ、来たるなかれ」とやり返される。
5.タナボタを逃がさない
ザチョートカ(成績簿のこと)の「冒険」は、まだ続く。「タナボタ」をつかまえたら、それをぱたんと閉じて(「タナボタ」が逃げていかないように)、念のため紐で縛っておく。そうすれば、次にザチョートカを開くのは試験官だけで、そうしないと、「タナボタ」がどこかへ行ってしまう。ただ、試験前に成績簿を開かせてそれを机の隅に置くよう指示する教官もおり、そうなると、すべては水の泡。
6.最初の体育の試験を受けない
学生は、試験を受ける順番もよく考えたほうがいい。体育から始めるのは、何としても避けたい。「試験期間中ずっと駆け回ることになる」、つまり、追試に追い回されるというわけ。
7.粥に顔を突っ込む
「粥に鼻面」という珍妙な名前のおまじないもある。試験前の朝食には、かならずコケモモジャムを入れたオートミールをいただく。コケモモではなくたとえばキイチゴのジャムを入れると「2(落第点)」や追試を食らうという恐ろしい言い伝えがある。いただくまえにその粥に鼻面をつけ、粥粒を顔にくっつけたまま残りを平らげなくてはならない。それが、名前の由来。
8.左手で試験用紙を引く
試験の用紙は、左足で立ったまま左手で引かなくてはならない。大事なのは、そのおまじないを教官に気づかれないこと。さもないと、知識を身につけていないのに試験に通りたいと考えている虫のいい輩とみなされかねない。
9.「つき」を分ける
試験に通った学生は、順番を待つすべての学生と握手をしなくてはならない。自分の「つき」を分けてあげるために。
10.来年に備える
すべての試験に通ったら、心おきなく羽を伸ばせる。受かった科目のノートや抜き書き帖を燃やして焚火をおこし、次の試験シーズンもうまくいきますようにとそれを飛び越える。ただ、ノートブックやアイパッドを愛用する学生は、そんなことをするはずもないが…。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。