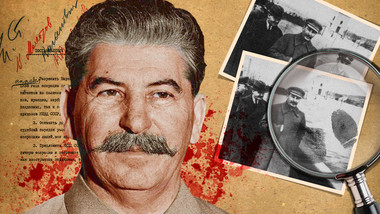「愛する人に気持ちを伝える手段として食がある」

「天のしずく 辰巳芳子 ”いのちのスープ”」映画の画像。写真提供:国際交流基金
NHKの担当プロデューサー、矢内真由美さんが訪露
10作品以上もの著書や長年続いているスープ教室、NHKの長寿番組「今日の料理」でもおなじみの辰巳芳子さんは、日本では非常に有名だが、ロシアではまだまだその名前は知られていない。そんな辰巳芳子の一年間を描いた「天のしずく」は、これまでスペインやポーランド、ハンガリーで上映され、ロシアまでたどり着いた。
今回は、ドキュメンタリー映画を紹介するとともに、日本食そのものの概念をロシア人に伝えようと、NHKエデュケーショナルの「今日の料理」のプロデューサーとディレクターを務め、「天のしずく」のプロデューサーでもある矢内真由美さんがモスクワを訪れた。
矢内さんが映画を紹介し、玄米スープを実演
上映開始の5時間前、矢内さんは上映を主催する国際交流基金モスクワ暫定事務所内のキッチンにいた。電気コンロの上には大きなステンレス鍋。コトコトと心地いい音を出しながら湯気を上げている鍋のお湯の中には、日本の伝統的な食材・煎り玄米と昆布と梅干。「一番日本的であり、誰でもが簡単に作れる玄米スープを、モスクワの方々に紹介したかった」と、出来上がったスープを味見する矢内さん。
「世界一寿命が長い日本人は、古くから自然を神様として尊い、自然の恵みを大切にし、自然に感謝してきた。日本人が食と向き合ってきたことは、こう言うことなのです。それを理解していただきたい」と、矢内さんは言う。世界各地で起きている日本食ブームは、ロシアでも花を咲かせているが、どうしても「寿司・刺身・天ぷら・うどん」などと、一方に偏ってしまい、和食全体の概念が今一伝わっていないのは確かだ。「日本食は、手はかけないが、素材の味を上手に引き出し、体を整える食。これって、世界を救う食べ方だと思うのです」
そう。実は、今回の上映は日本食を紹介するだけでなく、世界各地で見られる現代病「孤食」という深刻な問題を取り上げる重要なミッションにもなっているのだ。共働きが多いロシアの家庭でも、料理を作らなくなっている人は年々増えている。「自分で食事を作ることの大切さ、重要さを決して忘れてはいけない。愛する人を守り、愛する人に気持ちを伝える手段として、食がある」と矢内さんは上映前に、会場いっぱいに集まったお客さんに話しかけた。
「天のしずく 辰巳芳子 いのちのスープ」映画の画像。写真提供:国際交流基金
温かい料理に温かいコメント続々
「ファーストフードは、現代のファーストライフが作ったもの。生活のスピードが高い故に、自分の気持ちさえも確かめる時間が失われたことに、改めて気づかされた。人々は、生活のリズムを落ち着かせて、スローライフ・スローフードを大切にするべきだ」と、上映終了後、目に涙を浮かべた若い女性(匿名希望)が感想を述べた。矢内さんが作った玄米スープについても、「安心する、心地よい味」や「子供のころよく食べた、大麦のおかゆに味が似ている」と、温かいコメントが数々。
今年73歳になるマリーナさんは、「日本人は、実に哲学的な民族。自然を愛し、自然を観察し、自然とともに生きている。本当に素晴らしい」と、感想を語った。27歳のタチアナさんは、映画に出てくる子供の「大豆100粒運動」について、「子供たちに、小さい頃から自然を守る大切さ、高齢者を尊重する大切さ、労働の大切さをちゃんと身に着けさせていることに関心した。ロシアも教育の在り方を見直すべき」と、重要なメッセージを映画から読み取った。
辰巳さんのメッセージは届いた
「スープの湯気の向こうに見える、実存的な使命」という、辰巳芳子さんの言葉が、映画の最後に出てくる。「食を通して世界平和があるから、みんなで一つのものを食べる時間を大事にしてほしい」と矢内さんが言うように、人々は、単なるエネルギー回復のために毎日食事をするのではなく、一回一回の食事を身体のみならず、心の食事にもつなげる必要があるのだ。今回の上映がきっかけとなって、より多くのロシアの食卓が、毎晩家族が集う場になればいい。
気温がどんどん下がり、雪が積もるモスクワも、少し暖かくなった気がする。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。