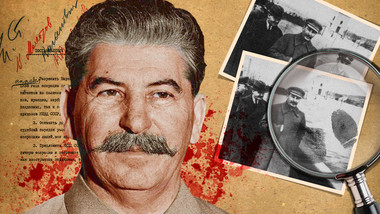太平洋のリトル・ウッドストック

世界的な音楽の危機を背景に、ロシア人ミュージシャンには、ローカルなアジア市場へ進出するまたとないチャンスがあるとみている =グレブ・フョードロフ撮影
この余白を埋めようとしたのが、ロシアのロック・バンド「ムミー・トローリ」のリーダー、イリヤ・ラグテンコだ。夏の終りに、彼は、日本、中国、韓国、台湾、さらには、アメリカの西海岸からバンドを招き、ウラジオストクで国際音楽祭「V-ROX(ウラジオストク・ロックス)」を催した。ウラジオストクを太平洋地域の音楽のメッカに変え、祭典後には、ロシアのバンドが極東諸国でスターに、そして、極東諸国のバンドがロシアでスターになる、という野心的な試みだ。夢が叶うかどうかはわからないが、ラグテンコは、1969年のニューヨーク郊外でのウッドストック・フェスティバルを想わせる太平洋のリトル・ウッドストックの開催に漕ぎつけた。いわば、太平洋のウラジウッドストック…。
ロシアン・フォーク・チャイニーズ・ロック
「アジアの音楽はよく知っていますか?」。極東国立大学の学生、ヤーナさんは、その問いにこう答えた。
「ほとんど何も…。市場へ行くと中国の歌を耳にしますね。この町には昔から中国系の居留民がたくさんいますから。でも、選曲はいかにも市場といった感じ。日本の音楽はアニメ漫画で知っています。韓国人では『江南スタイル』を歌っているサイとか…」。
大方の市民ばかりでなく、地元のミュージシャンさえ、そんな具合だが、アジアの隣人たちのほうは、ロシアの音楽事情にはるかによく通じている。
中国のアンダーグラウンドの人気グループ「P.K.14」のリーダー、ヤン・ハイソンは、ウラジーミル・ヴィソーツキーや、ヴィクトル・ツォイが率いたグループ「キノー」の名をさらりと口にする。中国では、多くのミュージシャンたちがロシアン・ロックの影響を受けてきたという。
日本の電子音楽アーチストDaisuke Tanabeも、1980年代のロシアン・ロックに一目置いており、本国でもごく一握りの音楽マニアしか知らないロシアのアヴァンギャルドな電子音楽グループの名をいくつも挙げる。
もはや欧州ではなく太平洋
ウラジオストク一の音楽通といえば、ラグテンコ自身だ。ロシア国内で押しも押されもせぬ大スターである彼は、自分のグループとともに世界を巡り、これまでに、上海、香港、東京などで公演を行っている。
この地域の音楽チャートにもよく通じており、世界的な音楽の危機を背景に、ロシア人ミュージシャンには、ローカルなアジア市場へ進出するまたとないチャンスがあるとみている。欧米は無理でも中国なら十分可能性がある。たとえクラブのスター程度のレベルであっても。必要なのは、意欲と努力。とにかく場数を踏み、ギャラの安さなど気にせず、軽快なフットワークを心がけること。
ところで、音楽に関しては、太平洋諸国に共通点はあるのだろうか? Daisukeは、太平洋サウンドは「優しくデリケート」であるという。ラグチェンコは、それを「煙草のプレゼンが行われる気だるいラウンジ」にたとえる。こうした沿海地方らしい呑気なところは、サンフランシスコのグループにも、日本のアーチストにも、当の「ムミー・トローリ」にも共通している。たしかに、韓国勢はもっとハードで、中国勢はもっと前衛的だが、いずれにせよ、面白い音楽を演奏してくれる。
エゴラッピン(Ego-Wrappin`)は、日本のロカビリー、中国の惘聞(Wang Wen)は、ハードなミニマリズムのギターサウンドを交えた前衛的アートロック、韓国のユニット「クナムグァヨライディングステラ(Goonamguayeoridingstella)」は、1970年代のメロディアスなロック、そして、サンクトペテルブルグのグループ「ストラーンヌィエ・イーグルィ(不思議なプレー)」は、パンク風のロシアン・スカを、堪能させてくれた。電子音楽のグループも多数来訪し、地元のクラブで大好評を博していた。
アリス・クーパーの隠れたファンたち
ウラジオストクは、音楽の伝統が豊かな都市といえる。アンダーグラウンドの伝統もしかり。1970年代には、ウラジオストクっ子たちが、ソ連で一番最初に最新の音楽情報を得ていた。外国航路の船員たちが、レコードをたくさん持ち込んでくれたおかげである。今年初め、オケアンスキー大通りとアドミラル・フォーキン通りの角に、1980年代初めの商船の船乗りの記念碑が建立されたが、その像は、なんと、当時流行っていたジーンズファッションに身を包み、西側のレコードを何枚も小脇に抱えている。
ウラジオストクでは、かつて、国内きってのブルースの名手、アレクサンドル・ジョーミンも公演を行った。この町には、ヒッピーや西側のロックのコレクターたちのコミューンが長いこと存在していた。現代芸術ギャラリー「アルト・エタージ」を主宰するアレクサンドル・ゴロドニーイさんは、こう懐かしむ。「私たちはよくミーンヌイ街の公園にたむろしては、そこから追い出されて警察にしょっ引かれたものでした」。
彼の「ジーンズ・ブック」には、ウラジオストクを公演に訪れたアリス・クーパーも目を丸くした。ゴロドニーイさんは、何枚もの西側のレコードのジャケットを手で描き写し、その文字を書き写し、スターたちに関するたくさんの記事をせっせと集めていたのだ。クーパーは、仲間のミュージシャンにこう豪語した。「なあ、みんな、お前らがまだ生まれていないころに、ウラジオストクにはもうおれのファンがいたんだぜ!」。
それは、西側のロックへの30年越しの愛であり、そこへ、このたびアジア勢が乗り込んできたのである。
みんなの太陽
中央広場でのメインコンサートの目玉は、なんといっても地元のアイドル「ムミー・トローリ」。非公式な市の歌ともいえる「ウラジオストク-2000」の演奏がはじまると、盛り上がりは最高潮に達し、ラグテンコの声もかき消されるほど。その力強いグラムロックは、会場のすべての人を虜にした。ロシア人も、アメリカ人も、アジア人も…。
オルタナティヴなハードなギター音楽を披露した「P.K.14」のステージも、強烈な印象を残した。4曲目あたりで、どしゃ降りの雨が降りはじめ、音響機材は水びたし。聴衆は、アスファルトのうえで裸足で踊り、頭にトカゲの刈り込みの入った日焼けした大男である地元ウラジオストクの人気パンクグループ「トゥマーンヌイ・ストーン(霧の嘆き)」のリーダーは、葉巻をくわえたまま踊っていた。ずぶぬれのTシャツ、足もとで迸る水…。
主催者は、コンサートの中止を呼びかけたが、ヤン・ハイソンは、「太陽が出るまで、おれは歌う」と宣言。まさに、ギタリストが最後のアコードを奏ではじめると、雲間から太陽がのぞき、サンフランシスコの金門橋にそっくりの金角湾をまたぐ橋のうえにカリフォルニアさながらの虹がかかった。すべてこれを、広場のもう一方の端に立つ極東におけるソヴェート権力をめざす闘士たちの雨にぬれた記念像が、驚きの目で見ていたが、ラシャ製の戦闘帽をかぶりライフル銃を背負った巨大な石造りの赤軍の兵士が、こんな光景を目にするのは、まさに初めてのことであった。
ヤン・ハイソンが何を歌っているかは、十人ほどの中国人ジャーナリストのほか、誰にもわからなかったが、太陽は、みんなのために姿を見せてくれた。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。