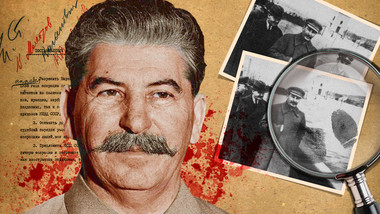モスクワで銅銭一揆が始まる

エルンスト・リスネル画「銅銭一揆」(1938) 画像提供:wikipedia.org
1648年の塩一揆
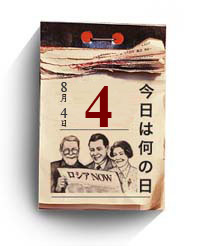 1648年の“塩一揆”は、アレクセイ・ミハイロヴィチ帝(ピョートル大帝の父)の寵臣で実権を握っていた大貴族ボリス・モロゾフが、財政難を打開するために、緊縮財政をすすめる一方で、塩を専売制にし、その結果、塩の値段が暴騰したのがきっかけだった。
1648年の“塩一揆”は、アレクセイ・ミハイロヴィチ帝(ピョートル大帝の父)の寵臣で実権を握っていた大貴族ボリス・モロゾフが、財政難を打開するために、緊縮財政をすすめる一方で、塩を専売制にし、その結果、塩の値段が暴騰したのがきっかけだった。
19歳の若きツァーリは、激昂して押し寄せた民衆を前になすところを知らず、泣き出してしまう。民衆が同情して静まったからよかったものの、まさに危機一発だった。
塩一揆の再現となった銅銭一揆
1662年の銅銭一揆の背景も似たり寄ったりで、長引いていた対ポーランド戦争の戦費を調達するために、銅銭を乱発したのが原因だ。
しかも、俸給は銅銭で与え、税金は銀貨で徴収することにしたから、銅銭の価値は際限なく急落し、ついには銀貨で6ルーブルに対し、銅銭170ルーブルまで暴落した。
なぜ銅銭ばかり乱発したかというと、当時のロシアには、金銀の鉱山がなく、金貨、銀貨を輸入して、ロシアの貨幣に鋳直していたという事情もある。
怪文書が導火線に
1662年8月4日に、ルビャンカで怪文書が見つかった。大貴族、大商人など、インフレの“張本人”の名を連ねて糾弾する内容で、その顔ぶれは、前回の塩一揆で槍玉に挙がった面々とだいたい同じだった。しかも、彼らはポーランドに内通しているとされた。これは事実無根だったが、民衆のくすぶっていた不満が爆発するには十分だった。
激昂した人々は、14年前と同様、大商人の邸宅を打ち壊し、このとき離宮コローメンスコにいたツァーリのもとへも数千人がやって来る。
14年前と打って変わったツァーリの対応
外務官僚グリゴリー・コトシーヒンによると、アレクセイ帝の対応は次のようなものだった。
「ツァーリは人々に向って、皆モスクワに引き返すようにと物静かに言い、聖餐式が終わり次第、自らがモスクワに赴き、この件を取り調べ、勅令を出すと説得した。だが人々は、ツァーリの着衣のボタンをつかんで、一体どうしてそれが信じられるのかと言った。ツァーリは神かけて約束し、自らの言葉の証に手を差し出すと、彼らの一人が両手でツァーリの手を握りしめ、皆はモスクワに帰った。人々に差し向ける軍勢もないではなかったが、ツァーリは、この無礼を理由に手出しをすることは一切まかりならぬと厳命した」。
為政者の“成長”
ところが、モスクワからさらに、数千の群集が押し寄せてきた。彼らは、零細な商人や農民からなり、前の人々よりも戦闘的な気分で、ツァーリに請願するという形ではなく、裏切り者を引き渡すよう、あからさまに要求した。
このときまでに、コローメンスコエには、モスクワから大貴族によって派遣されてきた軍隊が到着していた。
群集が解散命令に従わないのを見たツァーリは、ここで伝家の宝刀を抜く。棍棒やナイフしか持たない群集に対する制裁は、まさに容赦ないものだった。モスクワ川に追い落とされて千人近くが殺され、150人が縛り首になり、数千人が捕縛された。
捕縛された者も、拷問にかけられたり、焼き殺されたり、罰として、手足を切り落とされたり、顔に「叛徒」と焼印を押されたりしたが、怪文書の出所はついに分からずじまいだった。
その一方で、翌1663年から、銅銭の鋳造所は閉鎖され、銀貨の発行が再開された。成長したロシアのツァーリの姿、というべきだろうか?・・・
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。