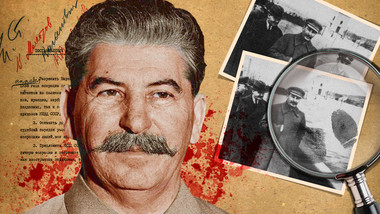外交官アレクセイ・ベストゥージェフ=リューミン生まれる

写真提供:wikipedia.org
十分な能力をもち、最高の地位にもつきながら、何らかの理由で、目立った成果は残さずに終わる。世の中には、残念ながら、こういうことがあるものだが、ベストゥージェフ=リューミンもそうだったかもしれない。おまけにそれで歴史まで大きく変わってしまうことがあるのだ・・・。
彼は、ピョートル1世(大帝)の随員として外遊、留学し、若くしてロシア公使となる。女帝エリザヴェータ・ペトローヴナ(大帝の娘)の治世(1741~1762)には、初め副宰相、1744年からは宰相(外相に相当)として、外交を担当する。
相次ぐ戦乱と目まぐるしく変わる合従連衡
この時代ロシアは、相次ぐ大戦争と、欧州列強の合従連衡の渦のなかに巻き込まれる。オーストリアの女帝マリア・テレジアの即位に端を発したオーストリア継承戦争(1740~1748)では、フランス、プロイセンなどが、オーストリア、イギリス、ロシアなどと戦う。
この戦いは、結局、フリードリヒ2世(大王)のプロイセンが、シュレージェンを獲得して一人勝ちに終わった観があり、他の列強は目立った利益を得ることはできなかった。
フランスとオーストリアは、15世紀以来の宿敵で、継承戦争でも、“仕掛け人”と被害者であったが、プロイセンの台頭を目の当たりにして、一転して同盟を締結する。いわゆる外交革命だ。
そうなるとイギリスは、新大陸、インドなどで一貫してフランスと対立してきたので、今度はプロイセンと同盟を結ぶ。こういう目まぐるしさであった。
反プロイセン網を構築
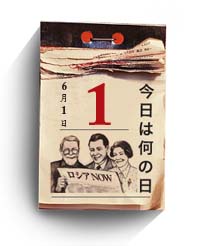 さて、ロシアだが、露墺は、対トルコなどで利害が一致しており、イギリスとは貿易で切っても切れない関係だったので、基本的な方向性は明らかなはずだった。
さて、ロシアだが、露墺は、対トルコなどで利害が一致しており、イギリスとは貿易で切っても切れない関係だったので、基本的な方向性は明らかなはずだった。
ところが、実際には、宮廷内には、親仏派、親墺派、親英派、親プロイセン派などが入り乱れており、国内での権力闘争のために、それぞれがしばしば勝手に外国と結ぶというありさまで、一貫した外交政策がとられにくかった。
ベストゥージェフは、継承戦争の前から、基本的に、親英反仏であり、プロイセンに脅威を感じていた。彼は列強と計って、反プロイセン網を着々と構築していく。
その結果、プロイセンはほぼ完全に孤立するにいたった。しかも、その唯一の同盟者イギリスも、貿易のお得意様ロシアに遠慮していたので、かりにロシアがプロイセンと戦ったとしても、積極的な支援を行う気はなかった。この時点で、四面楚歌のプロイセンの命運は、ほぼ風前のともし火だった。
命取りのミス
ところが、イギリスとプロイセンの同盟に驚いたベストゥージェフは、こともあろうに、英国との二国間同盟を主張してしまう。
これが、政敵ミハイル・ヴォロンツォフにうまく利用されたため、ベストゥージェフんの権勢は落ち目となり、まもなく開戦した七年戦争(1756~1763)でも、重要な決定が彼抜きに行われることが多くなった。
とはいえ、戦争では、ロシア軍は破竹の進撃をみせ、57年8月には、東プロイセンを占領した。司令官は、ベストゥージェフの親しいステパン・アプラクシン元帥だった。
ダメ押しのミス
ところが・・・ここで女帝エリザヴェータが病に倒れてしまう。跡継ぎは、大のプロイセンびいきで、個人的にベストゥージェフを毛嫌いしていた皇太子ピョートルであった(その妻が後の女帝エカテリーナ2世)。
焦ったベストゥージェフは、独断でアプラクシン元帥に、進撃をやめてロシアに戻れと手紙を書く。
ところが・・・女帝が回復してしまったからたまらない。怒った彼女は、ベストゥージェフを解任する。これで彼のキャリアは事実上終わった。
もっとも、戦争のほうは、いずれにせよロシアは勝つ運命になかった。62年に今度は本当に女帝エリザヴェータが死に、ピョートル3世が即位して、戦線から離脱するからである――一切領土を要求することもなく。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。