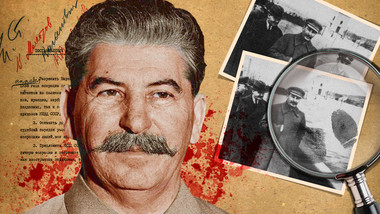SF作家ボリス・ストルガツキー生まれる

ボリス・ストルガツキー=タス通信撮影
1933年の今日、4月15日に、SF作家ボリス・ストルガツキー(~2012)が生まれた。日本文学者であった兄アルカージー(1925~1991)と共作で、SF小説の枠を超える哲学的、社会的な作品を多数執筆し、日本でもファンが多い。代表作の一つ「ストーカー」は、アンドレイ・タルコフスキーが映画化している。
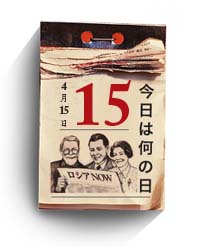 ボリスはレニングラード(現サンクトペテルブルク)生まれで、レニングラード包囲戦の際には母と同市に残った。兄アルカージーと父は、ラドガ湖のいわゆる「生命の道」を通って脱出するが、父はヴォログダで亡くなってしまう。
ボリスはレニングラード(現サンクトペテルブルク)生まれで、レニングラード包囲戦の際には母と同市に残った。兄アルカージーと父は、ラドガ湖のいわゆる「生命の道」を通って脱出するが、父はヴォログダで亡くなってしまう。
日本文学者と天文学者
アルカージーは1943年に軍に召集されるが、それまでに母と弟をレニングラードから疎開させていた。歩兵学校を卒業すると、軍の外国語研究所に転属させられる。専門は英語と日本語の通訳で、49年に卒業。以後、55年まで軍に通訳として勤務し、東京軍事裁判の準備にも携わった。デビュー作は、第五福竜丸事件を題材にした「ビキニの涙」。安部公房の「第四間氷期」のロシア語訳も手がけるなど、日本関連の著作もある。
一方、ボリスはレニングラード大学で天文学を学び、卒業後は天文学者として働く。57年から兄と共作で、SF小説を発表し始める。ストルガツキー兄弟の合作は、アルカージーが1991年に亡くなるまで続けられた。
SFを通してあぶりだされる人間の歪み
「神様はつらい」(1964)、「有人島」(1972)などの作品では、異星人の社会との接触というSF的筋書きを通して、逆に、接触する側の人間性、社会性、さらには根底的な世界観の歪みがあぶりだされる。
そのため、「そろそろ登れ蝸牛(かたつむり)」、「トロイカ物語」(いずれも1968)、「醜い白鳥」などは発禁処分となったが、ぺレストロイカ期の87年以降解禁され、部数でソ連史上空前のヒットとなった。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。
ロシア・ビヨンドのFacebookのページで
おもしろいストーリーとビデオをもっと見よう。