世界の終末の10億年前に
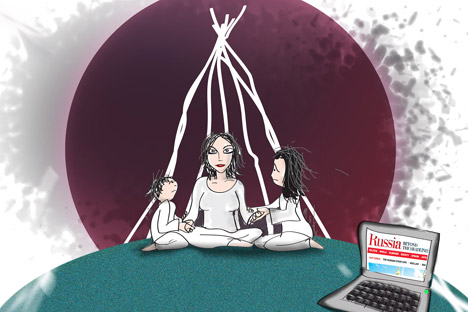
ニヤズ・カリム
階段状のピラミッド遺跡をぜいぜい言いながらよじ登り、単調な風景を眺めると、頂上にひときわ目立つアメリカの「ニュー・エイジャー(新時代の人)」のグループがいることに気づいた。軽いノリのこのアメリカ人たちは、気軽に声をかけてきたかと思うと、紀元前3114年8月11日を始点とする13バクトゥン(約5125年)が終わりに近づいていて、世界はクリスマスを祝うことなく滅びるんだと説明しだした。
終末論を明るく肯定
メキシコ人ガイドは、明るくこの話を肯定した。
「人間は洪水の後、魚になり、ハリケーンの後、猿になり、大火の後、鶏や七面鳥になってきたが、今は世界から血の争いが消えようとしているんだ」。
「じゃあ私たちは今度は何になるんだい?」。
「何にもならないよ」とガイドは手を振った。
メキシコ人ですらサッカーほど興味を示さないマヤ暦だから、私はこれをすぐに信じることはなかった。それに世界的大惨事なんて、「不幸を共にする人があれば苦しみは和らぐもの」ということわざの通り、大した恐怖感も感じなかった。
「キリスト再臨の祭、この車は運転手不在になります」
でもアメリカでは多くの人が世界の終末を予期していて、特に信仰の厚い南部では、車のバンパーに「携挙(けいきょ)の際、この車は運転手不在で取り残されます」なんて注意書きをしている人もいる。携挙とはキリスト教の終末論に記される言葉で、イエス・キリストが再臨する時に、キリスト教徒が空に上昇してイエス・キリストと会い、不死の体を得るということだ。
私が暮らすニューヨークでは、ユダヤ教ラビのシュネルソンが亡くなった時に、終末の話が出ていた。シュネルソンの回顧録のロシア語翻訳文を編集する仕事で、ハシド派に採用された経験があるため、私はラビとはわずかながらも関係があると言える。文章を読んで行く中で、ラビがレニングラード造船大学で学び、国家政治局に収監され、パリでサルトルと話をしたことなどを知った。ブルックリンでは多くの人がラビを救世主であると考え、永眠したことを信じなかった。
モルドヴィア共和国の収容所にいた経験のある、ラジオ・フリー・ヨーロッパ・ロシア局局長だったユーリー・ゲンドレル氏は、予期したことが起こらなかったからと言って信者をなじることほどの侮辱はあり得ないと言った。
映画「メランコリア」の黙示録
世界が予期した時に終わらなかったからといって、それが永遠に起こらないというわけではない。地球が太陽に飲み込まれるという科学的な説だって存在する。
数十億年も終末を待てない人は、ラース・フォン・トリアー監督の「メランコリア」という黙示録をテーマにした映画で、終末の時の様子を見ることもできる。
この映画では、地球に惑星が接近する。予言能力がある主人公のジャスティンはこれが終末だと知っている。天啓は徐々にジャスティンに降りてくるが、運命からは逃れられないとさとり、普通の生活を送ろうと結婚を考える。
すべてが無意味に
しかしながら仕事に愛、能力にキャリア、お祭りにセックス、ケーキにコニャックなど、何をしても無意味で楽しめない。人は瞬間ではなく、将来あってこそ人生を生きるが、その将来がないのだ。ジャスティンは庭で花が咲き乱れることも、婚約者が夫になることも、結婚で家族ができることも、仕事がキャリアにかわることも起こらないと知っている。
預言者は自分から知ろうとするのではなく、まるで印刷物や呪いのように、一度きりの永遠の知識を受け取る。終末の一ヶ月前、一週間前、一日前、一分前にどうやって生活すればいいのか。
ジャスティンの姉のクレアは、誰でもうらやむような生活を送っている。クレアは喜びを賛美しながら終末を覚悟し、ワイン、ロウソク、ベートーベンの交響曲第9番を用意し始める。
一方でジャスティンは他の預言者がそうであるように、何が起こるか、言い換えればもう何も起こらないことを知っているため、気分が悪くなる。いかなる終末も、罰せられた罪深き人や救われた信仰の厚い人、崩壊した教会や新しいエルサレム、苦しみの時間や厳かな永久を包括しているため、恩寵(おんちょう)で満たされる。「羊と山羊を区別する(善人と悪人を区別する)」、すなわち怖い裁きは厳しいが公正だ。
宇宙の日常的現象としての終末
でもトリアー監督にとって、このような裁きはそれほど怖いものではないし、宇宙人はまったく動じない。善悪やベートーベンのある地球人は恐竜より優れているわけではないのだ。地球人の生活が自滅することは、宇宙にとってちっぽけなことなのだ。
偶然に生じ、偶然に消えて行く、そして誰も見つけられないような、跡形も残さない例外的な唯一の変動ならば、くり返されることはない、ということにジャスティンは、予言に押しひしがれながら気づく。
こんな夢も希望もない予言をどうしたらいいのだろうか。
見出された解決
トリアー監督はドストエフスキーのように、罪なき子供の涙を思い出しながら、解決策を見いだす。ジャスティンには甥がいて、救うことはできないが、気を紛らわせることならできる。これが地球の歴史の最後の瞬間だ。ジャスティンは野原でシェルターを作り、これで接近するメランコリア惑星から身を守れると男の子を安心させる。惑星はすでに空の半分を覆っている。シェルターとは木の枝を集めた簡易なものにすぎない。おかしくて、こわくて、わかりやすい。ニュートンもベートーベンも助けてくれない、永遠の命もない、希望もない状態なのに、このみすぼらしいシェルターは自分の役目をしっかりと果たす。男の子を落ち着かせるという役目を。嘘でも瞬間的でもいい、これは芸術であり、そして大義なのだ。
アレクサンドル・ゲニス
評論家、ジャーナリスト。ラジオ・リバティーで毎週放送されるラジオ番組「アメリカンアワー」の司会者。ロシアの独立系新聞「ノーヴァヤ・ガゼータ」のコラムニスト
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。





