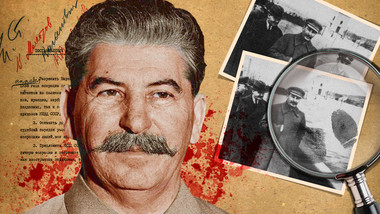イスラエルの手詰まり

アレクセイ・ヨルスチ
過去30年の安定
この地域で一連の戦争が起こった後、1970年代の末から、公式、非公式な関係のシステムが徐々に構築されていった。イスラエルはアメリカの支援を受けて、エジプト・イスラエル平和条約に調印し、その少し後にイスラエル・ヨルダン平和条約も締結して、周辺のアラブ諸国からの完全包囲状態を打ち破った。またアメリカは、ペルシア湾沿岸の君主国をはじめとして、最も裕福で影響力のあるアラブ諸国との関係を深めていった。
これらのアメリカの同盟国や協力国は、イスラエルの敵国であり続けたが、イスラエルの存続を保障するバランスを乱すような行動は取らなかった。
パレスチナ問題は争いの種に変わりはなかったが、この問題を地政学的に活発に利用してきたソ連が崩壊してしまうと、パレスチナを庇護するアラブ諸国は、現状維持を望むようになった。
1990年代の和平プロセスは、安定化に向うという錯覚を生みだした。アラブの大国はこのプロセスに口先だけの支持しか示さなくて済んだのだからなおさらだ。
イスラエルの仇敵であるシリアとさえ、ゴラン高原占領の問題という“時限爆弾”はあったものの、暗黙の不可侵条約が存在していたほどだ。
崩壊の21世紀開幕
21世紀を迎えると、すべてが崩壊し始めた。イスラエルの有権者の気分が変わり、左翼的協調主義者に票を投じなくなっただけではない。パレスチナも二つに分裂した。従前通りのパレスチナの特権階層が牛耳るヨルダン川西岸と、ハマスが支配するガザ地区に。
アメリカが中東の変革を促そうと試みたことで、イラクが事実上のイラン領となり、全体的に不安定化して、スンニ派とシーア派の対立が激化した。
大衆のエネルギーが「アラブの春」となって爆発すると、このカオスは「何でもあり」で、そのなかには種々雑多な考え方や気分が混在していたが、西側諸国、アメリカ、イスラエルへの好感度が増ことだけは決してなかった。
イスラエルの危うい足元
イスラエルが自国の展望に自信をもっていたのは、さっき述べた政治的・外交的均衡を保つシステムのほかに、問題はいつでも力で解決してきた国のあり方からも来ている。それは、軍事的優位性、コストを考えずにとことん行くところまで行く構え、そして、国際支援の保障の3点にもとづく。国際支援が保障されてきたのは、アメリカが反イスラエル的措置を常に抑え込んだからだ。だが現在、この3点は変わってきている。
イスラエルは2006年にヒズボラの活動を阻止するためにレバノン南部に侵攻したものの、うまくいかなかったし、2009年にガザ地区で展開されたキャスト・レッド(鋳造された鉛)作戦も成功とは言えなかった。つまり、軍事的方法で危機を効果的に解決できるという、自信が揺らぐことになった。
また、イスラエルはEUを含むほぼすべての国際社会から激しい非難を浴びていて、それを無視できない。アメリカでさえ暴力を停止させるために、イスラエルにプレッシャーをかけなければならず、せいぜい時間の猶予を与えるぐらいしかできなくなっている。
パレスチナ問題で中東全域が反イスラエルに?
パレスチナ問題は、中東の不透明な再編プロセスにおいて、交渉の切り札になりつつある。新しいエジプト政権は、カイロをアラブ社会の政治的首都にしようとしているため、キャンプ・デービッド合意を徹底的に見直し、パレスチナ問題でも積極的に行動し、シリア問題で地域的解決を押し進める可能性が高い(つまり、エジプト、 サウジアラビア、トルコ、イランの中東主要4カ国協議による解決だ)。
エジプト以外にカタールも、これらの問題で特別な役割を果たそうとしている。カタールの首長がガザを数週間前に訪れて、こう喧伝した。ハマスは、以前はシリアとイラン寄りだったが、今や新たな“スポンサー”が現れた。それは、アラブ世界の変革を伝播すると同時に、シーア派の影響に抗する指導者でもある、と。
概してカタールは、ムスリム同胞団の運動の「中枢」になることを歓迎している。ムスリム同胞団はすでにエジプトを支配し、他国でも活動を活発化している。
ヨルダンでも不満が高まっており、情勢が緊迫しているが、ここにもペルシア湾の支援がなくもないようで、いずれかの国が、ヨルダンをも、イデオロギー上の変革に引きずり込み、その後で、パレスチナ問題の解決にも引っぱり込もうとしているようだ。トルコは完全な反イスラエルである。
チェスの「ツークツワンク」の局面
中東におけるアメリカの立場は揺らいでいる。アメリカはこれまでスンニ派政権に頼っていたが、それらの政権も徐々にイスラム色が濃くなってきているし、影響力を増してきているシーア派とは、イラン問題によって対立している。アメリカにとって、イスラエルを無条件で支援しなければならないことは、重荷とまでは言わないまでも、中東で新システムを構築する妨げになりつつある。
イスラエルは軍事作戦を続けると完全に孤立してしまうが、かといって、明確な成果なしに軍を撤退させれば、イスラエルはもうかつての強国とは違うとアラブ人が悟り、もっと圧迫できると思わせてしまう。まさにツークツワンク(チェスの一手で、自ら状況を悪化させざるを得ない状況)だ。
フョードル・ルキヤノフ、「世界政治の中のロシア」誌編集長
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。