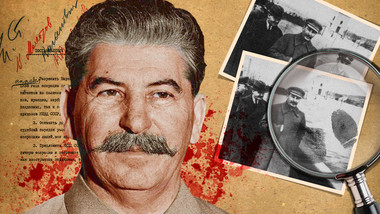日露海底送電線計画の復活

Lori/Legion Media撮影
また、日本の発電所にガスを供給するための、ガスパイプラインの建設も検討されている。ロシアと中国は現在、中国への電力供給の価格について交渉を行っているため、日本へのエネルギー供給の可能性は、中国への圧力となり得る。ロシアの専門家は、エネルギーが不足する日本は、自国のエネルギー生産を急激に増強している中国よりも、有望な提携先だと考えている。
スーパーリング計画の誕生
1999年から2000年代に、サハリン島から日本に大規模な電力輸出(最大4ギガワット)を行うことを目的として、海底ケーブルを敷設するプロジェクトの実現可能性が調査された。その調査では、サハリンに出力4ギガワットの複合サイクル発電所を建設し、600キロボルトの全長600キロ(海底ケーブルを含む)直流送電線を敷設し、さらにサハリンに4ギガワット、北海道に1ギガワット、本州に3ギガワットのあわせて3カ所の変電所を建設することが想定された。しかしながら、2000年代にプロジェクトは進まなかった。
エネルギー協力に関する日本の提案は、アレクサンドル・ノバク・エネルギー相が8月に日本側と会談した時に行われ、その後、一連のエネルギー・プロジェクトが記された書簡が、エネルギー省に届けられた。
「日露間電力ブリッジ構築プロジェクトから着手すべき」
日本側は特に、「サハリン1」または「サハリン3」のガス供給プロジェクトのため、ロシア・サハリン州と日本をつなぐガスパイプラインの建設の可能性を模索するよう、ロシア側に提案した。また、極東の既存または建設増強予定の発電容量から、余剰分を輸出するため、ロシアから日本に海底ケーブルを敷設するプロジェクトや、コヴィクタ・ガス田とチャヤンダ・ガス田を中心とした、東シベリアの開発・ガス採掘共同プロジェクトの実現も提案している。
ロシア政府は10月初め、エネルギー省に日本側の提案を検討するよう命じた。11月6日にエネルギー省はその結果を政府に報告し、特に「アジアのスーパーリング」プロジェクトを、分割して手際良く実現すべきであると伝えている。その中で、中国への電力供給プロジェクトはすでに実現段階にあるため、「アジアのスーパーリング」は、より検討の進んでいる日露間電力ブリッジ構築プロジェクトから着手するべきであるとしている。
スーパーリングと中国:価格をめぐる各国の綱引き
専門家は、ロシアが日本向けの電力輸出を進めようとすれば、中国がロシアの電力の価格交渉でより妥協してくるだろうと見ている。現在ロシアは中国に対し、毎年300~500億キロワットの電力輸出を可能にする、5~8ギガワットの超高圧直流送電線を建設するプロジェクトを提案しているが、中国が協定価格でこの電力量を受給することを保証しない限り、実現は不可能だ。
アナリストは、いずれにしても中国とは合意にいたらないだろうと考えている。
「『アジアのスーパーリング』の経済性について話すなら、中国と合意できる可能性はゼロだ。中国にとって電力価格は絶対的で、高いエネルギーなど必要としていない。一方でロシアは、『スーパーリング』よりも安く済む、シベリアや極東からのより簡単な電力供給プロジェクトにおいても、中国に安い価格を提案することはできなかった」と、エネルギー発展基金のセルゲイ・ピキン理事長は説明する。
また、ピキン理事長によれば、日本は以前からエネルギー不足の状態だったが、津波と一連の原発停止後、さらに事態が悪化しているため、日本との提携は必ずうまくいくという。日本では原発から電力供給減少分を、ガス火力発電で補っているが、液化天然ガスを発電所用に購入するよりは、サハリンからケーブルで電力を受給する方が安く済む。
ピキン理事長は、ガスプロム社が日本へのガスパイプライン建設プロジェクトにそれほど夢中になっていない理由のひとつがこれで、ガスを液化し、環太平洋諸国にタンカーで輸出した方が利益が大きいと考えている。
*イズベスチヤ紙の記事抄訳
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。