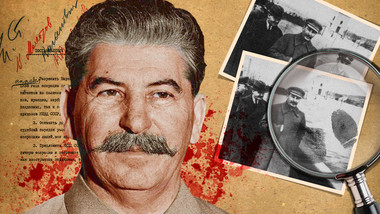死を考える日本

ナタリア・ミハイレンコ

ナタリア・ミハイレンコ
ロシアの音楽家ボリス・グレベンシチコフは、匿名の友人の言葉を引いたとして、日本の文化は死を巡って築かれたと語った。
日本は領土を始め何もかも乏しい。それゆえ一方では、自動車のコンパクトさや経済性、住居の広さへの渇望があり、他方では、限界についての不断の記憶や終末についての執拗な想念がある。しかも、客観的事実に基づいて破滅の思想を確認する冷静で示威的ですらある能力である。
これが自死的な国民性に極めて好い影響を及ぼしたとは言わないが、国の発展に良い作用をもたらしたことは紛れもない。
死について多くを考える国の方が現実の振舞いも優れている。
ロシアの実業家アレクサンドル・マムートは、ロマン・アブラモビッチにごく実用的な助言を求めたところ、相手はようやく2人が同じエレべーターに乗ってどこへも逃げ隠れできなくなるまで明確な返答を避け続けた。
アブラモビッチはこう言った。「きみは一切がどのように終わるかを憶えているのかい?」。「この取引でかい?」。「いや、すべてにおいて」。まさにそこから始めよというわけだ。
正直なところ、私は人生でこれ以上の助言を与えたことも受けたこともない。
日本は常にこの原則に従っている。日本の自然は厳しく、有用鉱物はごく限られている。海に囲まれ、長い鎖国も国民性の開放を促さず、慇懃さはもはや気密性とも言えるまでになっている。
この国民的な美徳は芥川龍之介の『手巾』でも描かれている。芥川が文学作品においても日常生活においてもそれほどまでに内向きでなければ自殺で果てることはなかったかどうかは分からない。
ロシアではそれは非難の対象であるが、日本の価値体系において自殺は神聖さの属性である。日本人はそれを最高のヒロイズムとみなし、間違った世界秩序の受容を拒んで自ら命を絶つ。ロシア人はどんな世界秩序にも順応し、どんな苦難にも耐え、そうした適応性を優れた資質とみなしている。私は日本人の感性により共感を覚える。
日本人は驚くほど健康的である。軍務は日本人の事実上不変の常態であり、日本人は夜でも歩哨に立つ自分の姿を夢に見る。
これまでに著された書物の中でおそらく最も有益で刺激的な一冊は、山本常朝の『葉隠』であろう。
私は、侍の倫理そのものが慈悲を促すとは信じず、自分にそれらの原則が守れるとも思っていないが、それらを愛でる心を妨げるものは何もない。
日本の料理もリスクの思想の上に築かれている。フグと死は味が似ているらしいが、死ぬことはあってもそれを試すことはできない。
日本の文化は繊細さ、苦しみ、優しさにあふれている。こうした資質を備えている人には、現実に直面した際に高貴ではかないものを汚さないために自らを亡くすことしか残されていないのである。
この無上の美がとりわけ顕著に描かれている日本映画の傑作が三つある。溝口健二、大島渚、そして、今村昌平の作品だ。
私は日本で英語字幕の『楢山節考』をテレビで観たことがある。耐え難いまでに悲しく、この上なく残酷でこの世のものとは思えないほど美しいこの作品に魅了された感涙の時を決して忘れない。
溝口の『雨月物語』にも優しさと厳しさが並存している。
日本文学では芥川の短篇『鼻』を挙げたい。自身の心の病を呪われたものとしてではなく個性あるいは特異性とみなすことを読者に教えてくれた。
死が正しく悟られなくては正しい生き方もありえないことを万人に知らしめてくれた日本に栄光あれ。
ヤポーニア誌抄訳
 ドミトリー・ブイコフ 詩人兼作家・反体制派指導者 |
1991年、モスクワ国立大学ジャーナリズム学部卒業。中学校で国語(ロシア語)と文学を教える。様々な新聞雑誌の評論員、社会政治評論部副部長などを務める。
映画、文学、政治の問題に関する記事を執筆し、雑誌『イスクーストボ・キノー(映画芸術)』、『セアーンス(上映)』、『アガニョーク(灯)』ほか、新聞『エクラーン・イ・スツェーナ(スクリーンと舞台)』、『リチェラトゥールナヤ・ガゼータ(文学新聞)』などに掲載される。
一連の詩集、長篇小説『正書法』(2003年)、『最も近い戦争のクロニクル』(2003年)、『正当化』(2005年)、『プーチンはいかに米国大統領となったか:新ロシア御伽噺』(2005年)、『避難業務従事者』(2005年)、『生に代えて』(2006年)ほかの著者。
『ナショナル・ベストセラー』賞受賞(2006年『パステルナーク』)。2010年、テレビ番組『油彩画』のMC。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。