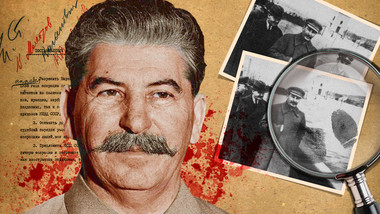平和条項の強化こそ:日本の安全保障の鍵に

ナタリア・ミハイレンコ
このところ、国の平和的地位を規定する法令における平和条項からの日本の漸次的離脱の傾向が見られる。
日本が国際紛争解決の手段としての戦争を放棄している憲法第九条の直接的放棄というよりも、その延長線上にある法令、原則、合意の解釈のことである。
指摘すべき点は、国の軍事的潜在力の強化を目指す日本の路線が西側の大国によって支持されていることである。米国からは、憲法の条項から導き出される「集団的自衛権」行使禁止の撤廃で圧力がかけられている。
米国はそうした禁止が中国の軍事的台頭を背景に米国が望みをかけるようになったアジア太平洋地域における集団安全保障体制推進の面での日本の消極的姿勢の要因となることを懸念している。
「中国包囲」という共通戦略の枠内で、米国は共通の脅威に対抗する協力を軌道に乗せるような参加国同士による複数のネットワーク(米国 – 日本 – 韓国、米国 – 豪州 – 日本 – インド、米国 – フィリピン – 日本)を自国の庇護のもとで構築しようとしている。
米国が不満を抱くもう一つの側面は日本の国内法が不完全な点である。
現行規則によれば、いかなる作戦であれ自衛隊が参加するためには毎年延長される特別の法律を採択する必要がある。
米国は国際的作戦への自衛隊の参加を保障する法的手続きは他の同盟国と比べて複雑であり、部隊の海外派遣を合法化する基本的な法律を採択する必要性を日本側に提起し続けている。
一方、日本では多くの人が日本は米国との軍事同盟を通して自国の安全を保障することができるのか、と自問している。
たとえば、中国との領土紛争(尖閣諸島をめぐる)の枠内での日本への攻撃あるいは北朝鮮サイドからの軍事的挑発といった場合に核兵器の使用にアメリカが踏み切らないのではないかという懸念が広がり始めている。ブッシュおよびオバマ政権において示されてきた米国政府の代表らの口頭確約にもかかわらず、その答えは一義的なものとは言えない。
日本の軍事的潜在力の再生に関する問題や憲法で規定された「平和的地位」の放棄の見通しをめぐり議論が続いている。
日本は、米国とのグローバルなパートナー関係を継続する路線と、米国の国益とは必ずしも一致しない自国の国益を優先的に保障する路線との微妙なバランスを必要とする政策を堅持すべきとの考え方が支配的だ。
ロシアは、全体として日米同盟に理解を示しており、それを北東アジアにおける戦略的状況安定化のファクターとみなしている。
憲法第九条によって規定された日本の特別な平和主義的地位をロシアは高く評価しており、その保持と強化の政策にこそ日本自らの安全保障の鍵があるとみなしている。
ロシアは北東アジア非核地帯化構想を全面的に支持している。国際的安全保障の分野には露日協力の大きな潜在力があり、それを活かすならば、日本はポスト・フクシマの経済復興のために必要な資金を軍備に注ぎ込まずに済むのではなかろうか。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。