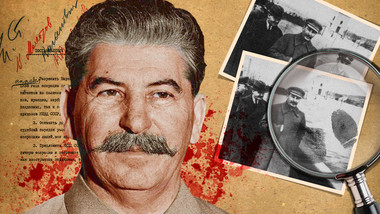独創的な決定と行動を:日露関係の未来へ向けて
 ドミトリー・ストレリツォフ ドミトリー・ストレリツォフモスクワ国際関係大学教授 |
日本の政権が目ぼしい成果を挙げられない場合、ロシアは打ってつけの「サンドバッグ」だ。対露関係は、日本の主たる国益には関係ない。いざという時にロシアを避雷針として利用できるように、「非友好国」としてのイメージを意識的に維持する方針がとられてきた。
ロシアの重要性増す
今のところ、日本にとってロシアは、有望なエネルギー供給国であるにすぎないが、脱原発政策のなかで、その重要性は増している。
ロシアは、既に日本のLNG(液化天然ガス)市場の約8%を占めており、さらに拡大を望んでいる。販売市場の多角化という戦略目的に適うからだ。
しかし、日本も、ロシアへの一方的依存を懸念しており、供給国の選択肢を最大限増やそうと努めている。ちなみに、欧州にとってロシアは、その自然的、地理的条件のために主要なエネルギー供給国となるべく「運命づけられており」、事情がまったく異なる。
中国ファクター
日露の経済関係は、例えば日本と中国のように相互補完的ではない。仮にロシアが急に輸出を停止しても、日本は容易にその代役を見つけられる。中国の経済的・軍事的台頭といった要因には、日本は米国との同盟の強化という昔ながらの方法で対処しようとしている。
日本では、ロシアは、むしろ中国の同盟国とみなされている。だから、中国ファクターを礎に日露の戦略的関係を構築することもあまり現実的ではない。
一方、ロシアにとっては、東アジアのすべてのパートナーとバランスのとれた関係を築くことが重要であり、指導部によって打ち出された、重層的な協力関係による安全保障の構想はこれを目指している。
パートナー関係の可能性
日本には、プーチン氏の大統領就任とともに対日路線が一変するという幻想はないようだ。日本は、新旧の大統領が共通の外交ブレーンを擁していることをわきまえている。とはいえ、ロシアとの政治対話に弾みをつける新たな可能性はある。
日本外交は、深刻な構造的危機に直面している。アジアの主要なパートナーとの関係強化の努力を怠り、アメリカとの同盟にすがるばかりでは、安全で安定した国際的環境の保障は覚束ないし、経済に安定した成長パワーを外から取り込むこともできない。ロシアは、日本にとって、そうした環境を形作る上でのパートナーとなりえよう。
そのためには、双方の国益に照らしたパートナーの重要性を首脳レべルで速やかに確認し合うべきだ。活性化の分野としては、北朝鮮の核開発問題を含む、極東の安全保障、軍事的分野における信頼醸成措置、大災害などの非常事態に対応するシステムの構築などが考えられる。
指導者間の個人的交流を深めることも重要な一歩となろう。その有効性は、1997~98年の「ボリス・リュウ(エリツィン・橋本)の蜜月」時代に実証されている。もう一つは、対話の「セカンドトラック」、まず第一に専門家による定期的な話し合いの場を設けることである。
日露関係の現状は、そこに眠る深いポテンシャルの活用を阻んでいる。そこでは、独創的な決定と行動こそが成果を挙げうる。いずれにせよ、両国の首脳が国内の政局を少し度外視して相手を評価し直すことは意味があろう。それには政治的叡智が求められる。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。