ヴェネチア・ビエンナーレの歴史あるロシア館を改修した日露の建築設計事務所KASAにお話を聞く

ヴェネチアにあるロシア館は1914年に、後にレーニン廟の設計で有名となったアレクセイ・シューセフの設計により建てられた。ヴェネチアの建築要素を取り入れながらロシア様式で建てられたパビリオンは、国外で常にロシア芸術が紹介される最初の展示場となった。

シューセフの設計は、展示空間とジャルディーニ公園の自然を融合させるというものであったが、100年のときとともに、時代要求に応じた数々の変更が加えられ、オリジナルの「多孔性」が失われていた。パビリオンと周辺環境を関係性を再構築するという課題に挑んだのが、公募によって選ばれた日露建築家ユニットKASA/Kovaleva and Sato Architectsである。パビリオンのコミッショナーはV-A-C基金のTeresa Iarocci Mavica会長、キュレーターにはIppolito Pestellini Laparelli。

改修工事を終え、長年にわたって塞がれたままになっていたほとんどの窓やテラスに向かうドアが再び開け放たれた。またパビリオンの内部には自然光をに満ちた展示室が再び現れ、外壁はオリジナルのグリーンが再現されている。8月30日、ロシア館は第17回ビエンナーレの国際建築展の「特別表彰」を受賞した。

KASAはロシアのアレクサンドラ・コヴァレヴァと日本の佐藤敬による建築家ユニット。2人は石上純也建築設計事務所に勤務していたときに知り合い、2019年に事務所を立ち上げた。おふたりに、コロナ禍により余儀なくされたリモートでの作業について、またヴェネチアで隣り合う日本館とロシア館や、2025年に開催予定の大阪万博のビジョンについて尋ねた。

日露建築家ユニットKASAのアレクサンドラ・コヴァレヴァと佐藤敬
―現在、KASAではどのようなプロジェクトを行っていますか?
私たちは家具やオブジェクトのような小さなスケールからインテリアや建築、街や環境などの大きなスケールまで人間の生活に関わる広い領域で活動しています。プロジェクトの立地も日本やロシアだけでなく、世界中のあらゆる場所に広がっています。先日竣工したヴェネチアビエンナーレロシア館の改修はイタリアですし、ロシアでは自然公園のカフェの離れ、ダーチャの新築、日本ではアトリエの改修や都市計画、来年2022年の瀬戸内国際芸術祭のアートインスタレーションのプロジェクトが現在進行中です。

―今回、ヴェネチアビエンナーレのロシア館の改修にあたり、KASAの応募案が選ばれた理由はなんだと思いますか?
提案を考えるにあたり、私たちは建築の形を考える前にまず、この建築が持つべき精神性のようなものを考え始めました。それこそがこの建築が100年後も存在するために再考すべき事だと感じたのです。ロシア人にとってこの建築がどのような存在になるべきか、そのような問いを投げかけました。

およそ100年前、A.シューセフがロシア館を設計した際には、建築様式に国のアイデンティティを求めました。しかし、今の時代にそれを見出す事が難しいと感じた私たちは、ロシアの持つユニークな生活様式に着目しました。それが「ダーチャ」(菜園付きのセカンドハウス) です。街と村を移ろいながら暮らすロシア人にとってのヴェネチアのロシア館。

ロシア館の改修プロジェクト
KASAそれは皆のためのダーチャのような場所なのではないかと思ったのです。街から村を想う事とロシアからヴェネチアへ想う事、2つが重なり合った時、愛着ある場所へと生まれ変わるような気がしました。キュレーターが掲げたキーワード「Identity / アイデンティティ」「Openness / 開放生」「Vulnerability / もろさ」「Constituency / 構成員」「Collaboration / 協働」にダーチャのもつ精神性が呼応するような設計姿勢を物語として示しました。
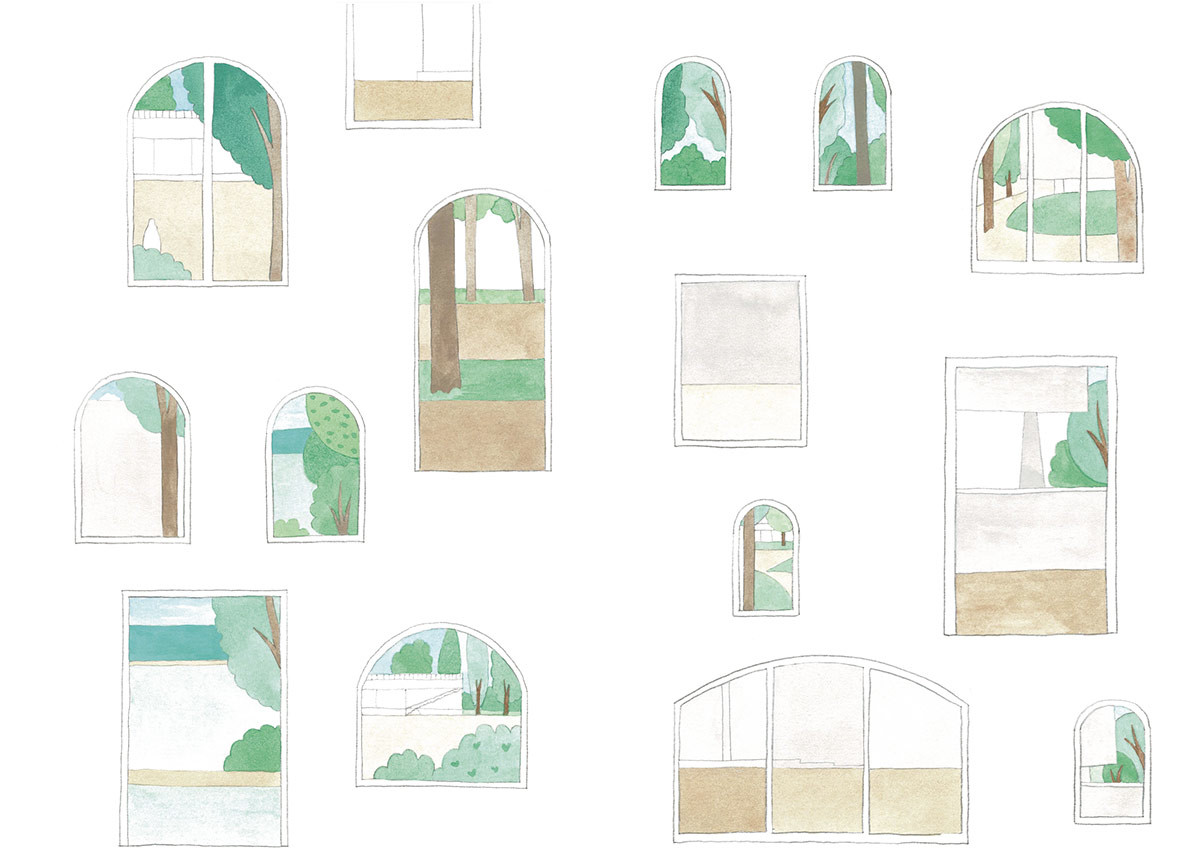
―新型コロナ禍の中での作業は大変でしたか?
このプロジェクトが始まった2020年の初頭に世界的パンデミックが起こり、私たちは現地へ一度も訪れる事なく設計に取り組まなくてはいけなくなりました。プロジェクトは全てリモートで行われたのです。

私たちはその時には東京にいたため、アトリエで大きな模型をつくったり、パヴィリオンと同じような空間を街の中に探し出したり、できる限りイメージを私たちの身体に近づけるよう試みました。それは想像の旅だったとも言えるでしょう。実際に訪問できないという制限はあっても、想像力は無限です。

私たちはロシア館を舞台とした架空の世界をアニメーションとして描き、設計のプロセスと並行しながらオンライン上で発表していく事にしました。これはキュレーターが企画した、他のオンラインコンテンツと共存し、ロシア館のウェブサイトで閲覧できます。

今回のプロジェクトは、国際的なチームでの協働の結晶として実現され、私たちだけでは決してなし得ないことでした。ミラノのキュレーターチーム2050.plusとヴェネチアのローカル建築家map studio、そして日露ユニットとしての私たちKASA。親密なコミュニケーションと信頼の大切さを改めて実感しました。どんな状況でもチーム全員が諦める事なく、改修プロジェクトが続行され、竣工された事はとても幸運だったと思います。また、コミッショナーのTeresa Iarocci Mavica氏やキュレーターのIppolito Pestellini Laparelli氏の強い信念があったからこそ存続できたのだと思います。このプロジェクトに関わった人々みんなに感謝の意を表します。

―どのようにして、改修されたロシア館と隣にある日本館を結びつけることができたのか教えてください。
偶然にもロシア館と日本館は隣同士でした。日露の架け橋として何かできないかと思い、私たちから日本館のキュレーター門脇耕三氏に連絡を取った事を端に協働プロジェクトが始まりました。両国のチームメンバーを交えながら議論を重ね、2つの事が実現されました。
1つ目は、交換展示です。ロシア館の改修をまとめた私たちの絵本「Traces」を日本館に、日本館の展示コンテンツである民家の古写真をロシア館に、それぞれ展示しました。これは互いの展示物を互いのパヴィリオンを背景に鑑賞するという今までにない体験です。ロシア館の塞がれていた窓やドアが再開された事で、周辺との新たな関係性が生まれ、日本館との交換展示はそれをよく体現する出来事のように思えます。

2つ目は、共通展示です。両国のパヴィリオンの境界には擁壁があるのですが、ここに”This is not a「wall」”というフレーズを、ロシア館側には日本語で”これは「壁」ではない”、日本館側にはロシア語で”Это не «Стена»”、と記しました。各々の言語は壁を超え互いを表裏一体の存在となり、壁に新たな力を与えたようでした。私たちが今年の8月末に初めて現地に訪れこの展示をみた時、歴史的に隔てる事に関与してきた壁が、互いを繋げるものとして貢献している姿に建築への希望を見出しました。
―今後、露日のプロジェクトに参加される計画はありますか?
在日ロシア人または在露日本人のための居場所づくりをしていきたいと思っています。まずは改修中の私たちのアトリエで在日ロシア人の議論の場を仲間と共につくり、そこを拠点に少しずつ輪を広げていくつもりです。ロシアの本や作家のためのギャラリーのような場所も設ける予定です。

2025年には大阪万博があります。これに関して具体的な仕事がある訳ではないですが、私たちは大きなビジョンを持っています。今までの万博のパビリオンの多くは短期的な役割を終え行き場を失い解体されてしまいます。未来を考えるはずの万博なのに、会期後は泡のごとく消え失せてしまう少し悲しい現実があるのです。私たちはこのあり方に対して問いを持ち、大阪万博のロシア館にて万博の違う未来を描きたいと思っています。展示のための即物的展示から脱却し、万博をつくる事自体が未来の生活と直結するようなあたらしい姿です。
日本でのロシア人の居場所。日本でロシアについて知れる場所。日本からロシアを見つめ直し世界に発信するような場所。万博をきっかけにそのような場所をつくれたら、何と素敵な事でしょうか。街のリビングであり学校でありギャラリーでもあるような、みんなの場所をつくりたいと願っています。

ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。