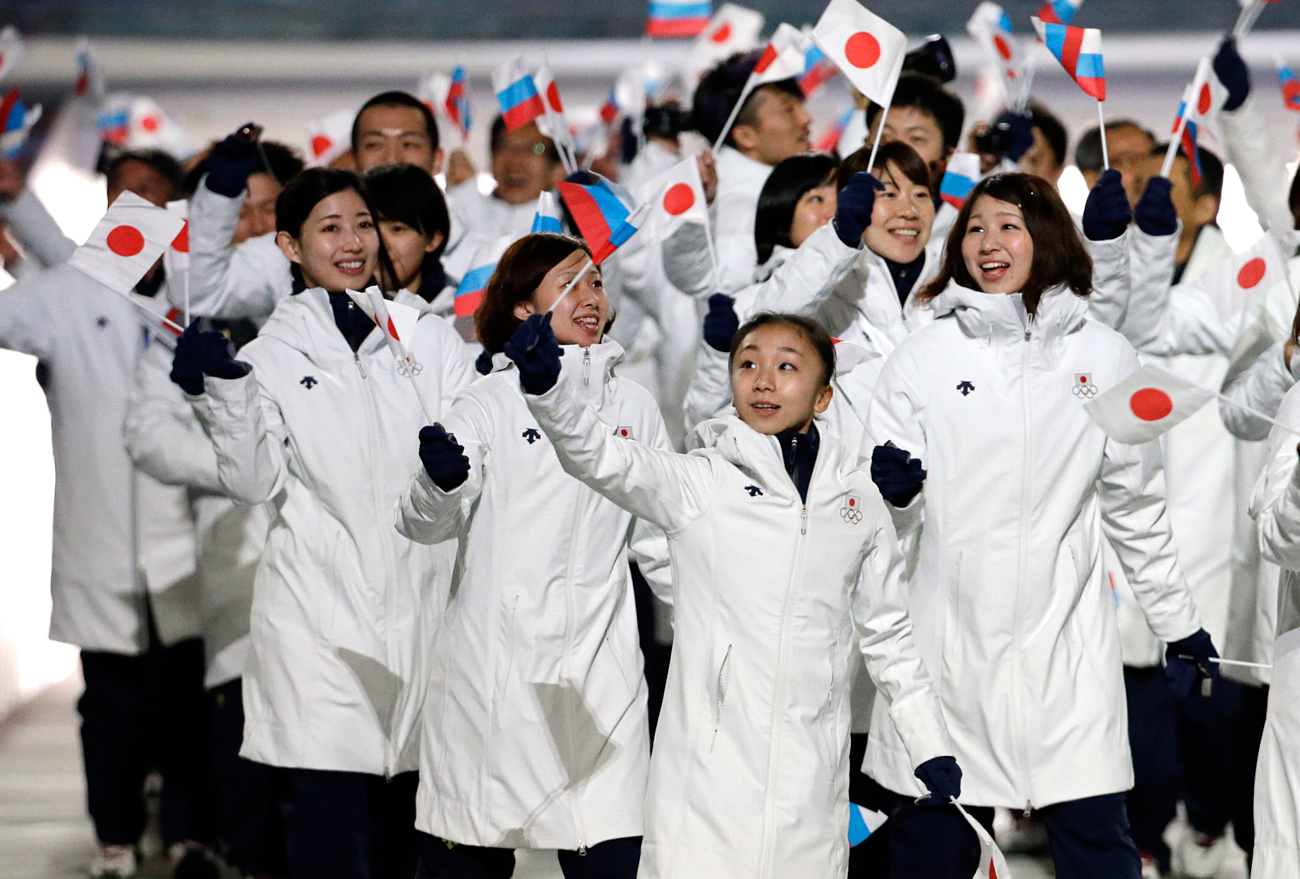新潟、隣国への扉

新潟県、津南町の風景=
AFP/East News日本を訪れるロシア人、そしてそれ以外の外国人観光客の大多数の人にとって、日本にやってきてまず目につくのは太平洋沿岸部特有の狭さであろう。世界でも最大級のメガポリス(東京、大阪、名古屋)は、都市や工場が小さな建物を圧迫する、そんな人間の蟻塚をつなぐ鎖を形成している。
日本で人の住まない地域といえば、日本最北の島である北海道にしか残っていないという考えが根付いている。しかし「日本のシベリア」はそこだけではない。実はどこにでもある。その場所を見つけるためには、太平洋沿岸から少し離れてみさえすればよい。すると目の前にはたちまち高山草原、滝の飛沫があがる川、世紀を超えて立ちつづける松の木の間に眠る火山湖が開ける。本州の北部と中央部、四国南部、九州南部などがそうした場所である。
日本の国土は実はそれほど小さくはない。面積はイギリスの1.5倍ほどだ。一方で日本の国土の6/5は山腹の開発に適していない。日本人が好んで口にする「農民は山と海に追いやられている」という言葉にも表されているように、狭さが目につくのは国の人口の半分が、たった2パーセントの国土に集中しているからだ。
山陰―山の陰に
シベリアに向かっている側の日本の地方には「山陰」という比喩的な名前が付けられている。「山の陰」である。しかし現在この名称は詩的な隠喩というより、経済的、社会的に「陰に置かれてしまっている」というこの地方のイメージと解釈されている。
ロシアに近い側である日本海沿岸部は、今や狭さではなく、過疎が特徴的となっている。そしてロシアと隣り合っていることが、地元の住民たちに地域繁栄の希望を与えている。その代表的な例が、日本の裏玄関という立ち位置から抜け出ることを願う新潟港だ。一方、裏日本(山の陰に位置するこの地方のもうひとつの呼称である)の気候もまたロシアとの近さを思い起こさせる。太平洋沿岸地域の冬の気候は乾燥していて、よく晴れている。しかし新潟県ではシベリアからの風によって深い雪がもたらされるため、村の子どもたちは何週間も学校に行けなくなることもあるほどだ。
しかし今、裏日本の住民たちは、ほかでもないシベリアの広大さと天然資源の豊かさに、地域の将来の展望を見ている。新潟港には松の丸太の匂いが染みついている。この丸太は日本海の反対側にあるナホトカから運ばれて来るものだ。まさにこのナホトカでは、東シベリア・太平洋石油パイプラインの敷設作業が完了しようとしている。このパイプラインは、日出る国、日本のエネルギー供給を支える活力ある幹線パイプラインとなった。新潟では戦後まもない頃からロシア語は耳慣れた言語となっていた。1960年代に日本で働いていた頃、わたしは地元の人々に瓶詰めのキャビアを売ろうと懸命になっているロシア人をよく見かけた。それを売ったお金で、当時、日本のおみやげとしてもっとも好まれていた小さなトランジスターラジオを買おうというのである。今、ロシア人がじっくり選ぶのはまず中古のトヨタやホンダだろう。
白鳥の湖の管理人
もうひとつ、わたしたちの地理的な近さを思わせる感情的な結びつきがある。1960年代にマリインスキー劇場の東京公演が行われたとき、日本中がバレエ「白鳥の湖」の話に湧いた。そして数千人の人々が新潟近郊に同じ名称の記念公園を創るというアイデアに飛びついた。越冬のため東アジアの暖かい国々へと飛び立つシベリアのハクチョウは、瓢湖で羽を休めるのだが、ある日、年老いたコメ農家の吉川重三郎さんが病気にかかって群れからはぐれたハクチョウと、その忠実な恋人である雌のハクチョウを手元に置き、世話をした。吉川さんは冬の間ずっと餌入れをいっぱいに満たし、凍った湖の氷を割ってやった。絵のように美しい誇り高き鳥はやがて吉川さんに懐くようになり、彼の手から餌を食べるようになった。
 新潟県の瓢湖=Getty Images
新潟県の瓢湖=Getty Images
吉川さんは農作業よりもハクチョウの世話に精を出した。そんなある日、冷たい水の中で1日中働いた吉川さんは帰ってきて横になると、それからもう二度と起き上がることはなかった。しかし死さえも瓢湖で始まった善い行いを阻むことはできなかった。「シベリアのハクチョウを保護した人物」についての噂は、バレエでよく知られる白鳥の物語に劣らぬほど強く日本人の心を揺さぶった。彼が住んでいた家には、日本のあちらこちらから、羽の生えた訪問客のために数千という贈り物が届いた。新潟近郊の「白鳥の湖」は国指定文化財と認定され、日本人、外国人の観光客に愛される場所となった。
新潟のハバロフスク通り
ちょうど1960年代半ばのその頃、新潟は強い地震に見舞われた。テレビのニュースで災害について知ったわたしはすぐに自動車の運転席に乗り込むと、東京で働くすべての外国人ジャーナリストの中でただ一人、その日のうちに被災地に着いた。
当時市長を務めていた渡辺氏とともにわたしたちは街中を視察した。見るからにとても古い日本風の家屋が倒壊していないことにわたしはとても驚いた。一方で、市の誇りであった戦後の5階建て住宅は土からむき出しになった基礎部分とともに横倒しになっていた。
また一枚岩のような鉄筋コンクリートでできた高層ビルはといえば、その多くはあの有名なピサの斜塔の如く傾いていた。7度以上傾いた建物の中で、人々はめまいと吐き気を感じたという。
被災地に到着した数時間後、わたしはモスクワからの電話に呼び出された。そこで現地からのルポルタージュのためには自分自身の印象を語るだけで十分であった。
「プラウダ」紙に掲載された新潟地震に関するわたしのルポはハバロフスク市民らの同情を誘い、義捐金の募集が行われた。こうして集まった義捐金を使い、家を失った日本人のための建材を積んだ木材運搬船3隻が準備された。新潟には、これらの丸太と板を使って、一列に並んだ住宅が作られたのだが、その区画は現在、ハバロフスク通りと名付けられている。
この後、新潟市民はハバロフスクの人々に対し、より緊密な友好関係を築こうと提案した。そしてこれによってわたしは再び復興を遂げた新潟を訪れるきっかけを得ることとなった。接近したこの2つの都市の深い友好関係の最初の時期について、露日の交流史に書き留めるためであった。実際、このように個人的にこの出来事に関われたことをわたしは誇りに思う。それに渡辺元市長はわたしのために、日本でもっとも色が白いことで有名な(新潟にはシベリアの吹雪がもたらすもっとも柔らかい雪が降るためというのがその理由らしい)地元の芸者たちと会う機会を設けてくれた。
より強まったロシアとの絆は、新潟がもはや日本の裏玄関ではなくなったことを証明するものとなった。新潟は隣国への扉となったのである。
*フセヴォロド・オフチンニコフ―「ロシースカヤ・ガゼータ(ロシア新聞)」評論員。ソヴィエトおよびロシアの社会評論家で東洋学者。40年以上にわたり「プラウダ」紙の記者および評論員を務めた。日本と日本人の特徴について描いたソ連時代の人気の作品『桜の枝』の作者として知られる。この本は邦訳がある。『桜の枝―ソ連の鏡に映った日本人』、早川徹訳、サイマル出版会、1983。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。