『ビジネスパーソンのための世界情勢を読み解く10の視点 ベルリンの壁からメキシコの壁へ』
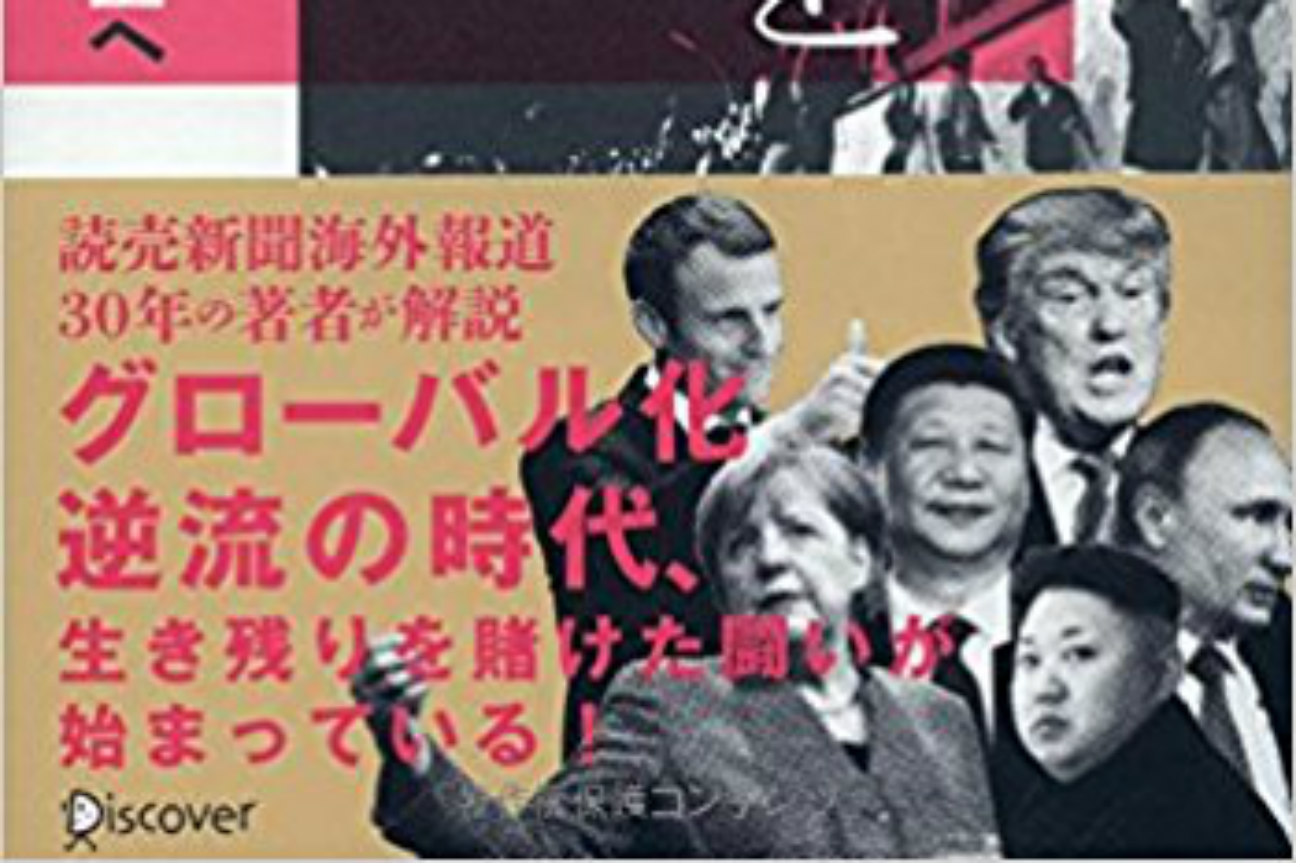
刊行:2017年8月
森 千春 著
ディスカヴァー・トゥエンティワン 刊
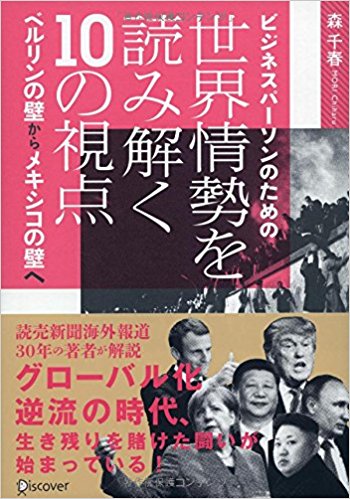 本書の帯に、「グローバル化逆流の時代、生き残りを賭けた戦いが始まっている!」とある。このこと自体は、かなり一般的な認識になってきているかもしれない。何世紀も膨張をつづけてきた「成長モデル」が、限界に達し、行き詰まろうとしている。分業、市場がいまや地球大になり、利子もゼロを超えてマイナス圏に下がりつつあるからだ。しかし、各国、各民族が具体的にどんな状況に陥り、いかにサバイバルしようとするか、という肝心の点になると、これは難しい。本書は、その点で極めて有効な道標になると信じる。
本書の帯に、「グローバル化逆流の時代、生き残りを賭けた戦いが始まっている!」とある。このこと自体は、かなり一般的な認識になってきているかもしれない。何世紀も膨張をつづけてきた「成長モデル」が、限界に達し、行き詰まろうとしている。分業、市場がいまや地球大になり、利子もゼロを超えてマイナス圏に下がりつつあるからだ。しかし、各国、各民族が具体的にどんな状況に陥り、いかにサバイバルしようとするか、という肝心の点になると、これは難しい。本書は、その点で極めて有効な道標になると信じる。
著者の森千春氏は、読売新聞のベルリン特派員、ソウル特派員、欧州総局長などを歴任し、現在は論説委員を務めている。本書のタイトルにもあるように、ベルリンの壁崩壊からメキシコの壁にいたるまで――つまりソ連崩壊、冷戦終結によるグローバル化の加速、ピーク、終焉(?)まで――、現場での取材、考察を積み重ねてきた。
最近、森氏は、本業のかたわら、大学で国際関係を講じている。しかし学生たちが、今日の世界の地殻変動に戸惑っているのを見て、それを読み解く「次世代のための注意書」のようなものを著したいと思ったという。この注意書きでは、だから当然、ソ連、ロシアの話が大きな比重を占めている。
地殻変動の根源は成長モデルの終焉
地殻変動の根源は、おそらく、成長モデル、資本主義の終焉である。例えば、日本では、いち早く水野和夫氏が、ロシアでは、エコノミストのミハイル・ハージン、モスクワ国際関係大学教授のワレンチン・カタソーノフなどが、こうした説を唱えてきた。
ちなみに、ミハイル・ハージンによれば、終焉するのは、資本主義だけでなく、社会主義もである。中国のそれはもちろん、ソ連型社会主義も、経済的に見れば、国家全体が一つの会社のようなものだから、やはり成長モデルの問題を免れないという。
成長から縮小、破綻、戦いへ。欧米が主催する “仮面舞踏会”は終わろうとしている。仮面とは、自由(貿易)、民主主義、人権、国際法など、グローバル化の枠組みそのものだ。欧米とそれに調子を合わせてきた各国は、仮面を脱ぎ始める。その素面はどんなものか?そして、彼らはどう行動するのか?
国家の個性とは
森氏は、まさにそれを見極めるために、各国の「個性」を深く捉えようとする。だから、国家が本書の主役となる。
国家は、歴史、伝統、集団的世界感覚、行動パターン、他国との関係のあり方などの、生きた膨大なコンプレックスの総体である。その総体が一つのイメージを結ぶまで、森氏はじっと待つのだ。国際関係も、そこから自ずと浮かび上がってくる。そのイメージのリアルさと深さが、氏の最大の武器である。その意味で、氏の眼差しは、人間を見つめる心理学者あるいは文学者を思わせるところがある。
しかし本書は、高度な内容を扱いながら、とても読みやすい。各センテンスが短く、考えを一つ一つ確かめるように文章が進んでいき、曖昧なところがまったくない。図版が多く、レイアウトがよく工夫されているのも、読者としてはとても助かる。
ロシアの行方は
個々の国家の個性については、本書の陰影に富んだ、含蓄のある文章を直に読んでいただくにこしたことはない。箇条書き風にまとめてもあまり意味がないのだが、森氏のロシア観のみ、かんたんにまとめておこう。そこには、森氏から照会を受けた筆者(佐藤)の見解も反映されているが、次のようなものだ。
ロシア人というのは、個人のモラル、生活から、国家の政治、外交まで律してくれる、唯一絶対のイデーをどうしても求めたがる(そういうイデーは、だから、国家権力と不可分になる)。帝政時代のロシア正教も、ソ連時代の社会主義も、まさにそうしたものとして心理的に機能していた。こういう唯一の教えを奉じ、他にも広めねばならぬ、というメシアニズムがここから、論理必然的に出てくる。ところが、連邦崩壊後は、そんなイデーがないから、ロシア人は心理的にとても不安定で、行き場のない情念が渦巻いていた。
しかも、彼らには――彼らの意識の中ではだが――欧米に対する積年の恨みが、ソ連崩壊後とくに強まってきていた。対ナポレオン戦争、クリミア戦争、対ナチス・ドイツ戦争、そして、冷戦終結による東欧喪失、NATO拡大。西方からのたび重なる圧迫と軽視への鬱積した怒り。これらの情念が一気に、クリミア編入を機に噴出している、と…。
帝国主義的な多極世界
さて、各国が織りなす未来の国際関係であるが、森氏は、一つのカギとして、国際法というものの本質的な弱さを指摘する。国際法を破っても、国連安保理決議が採択されるケース以外は、強制力が働かないからだ。みんなが国際法を守ったほうが、守らせたほうが得だという、グローバル化の時代は終わった。
それで、一部大国が「国益を追求する中で、国際法を利用したり、無視したりしている」(179頁)ということになる。森氏によれば、ロシアのクリミア編入、中国の南シナ海、東シナ海への進出は、その現れである(クリミア編入について欧米は、ロシアが、ウクライナの領土保全を保証した「ブダペスト覚書」に違反したと非難し、一方ロシアは、クリミアの「民意」、国連憲章の民族自決の原則を盾に、コソボのケースを例に挙げ、反論する)。
米国のトランプも、「不動産ビジネス 思わせる取り引きを対中外交に持ち込」む(186頁)。これは、今年4月の米中首脳会談後にトランプが、中国が北朝鮮問題で協力するのと引き換えに、同国を為替操作国と指定することは差し控えると、ツイートしたことを指している。
「帝国」の間の超法規的取引で物事が決まっていくのでは、という危惧を、森氏は強く抱いているようだ。日本も、知らぬ間に取引材料にされ、ツイッターで勝手に発信されていた、などということになりかねないと。
記事、コンテンツの筆者の意見は、RBTH(日本語版はロシアNOW)編集部の意見と一致しない場合がある。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。