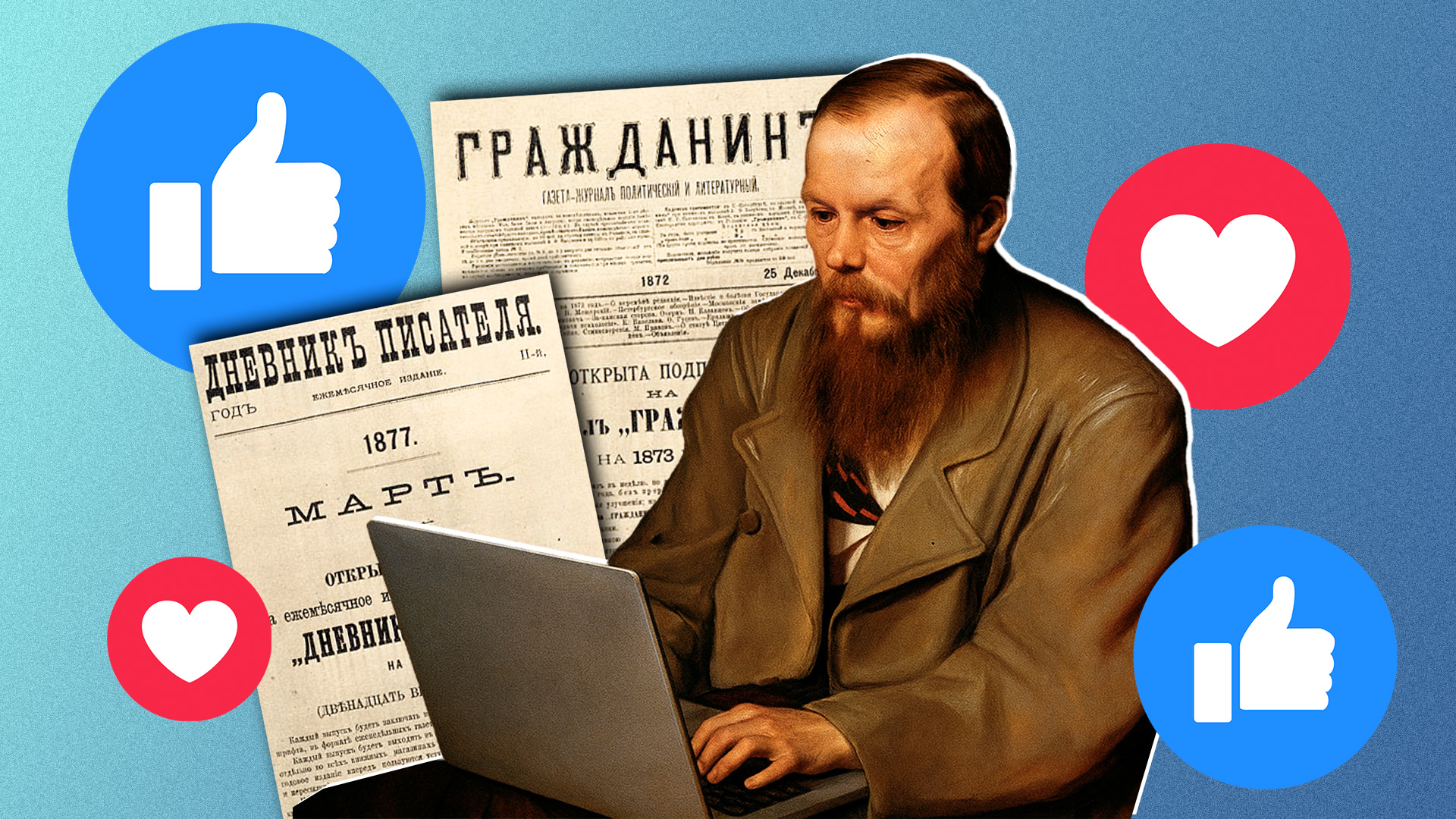ドストエフスキーの『悪霊』のショートサマリー
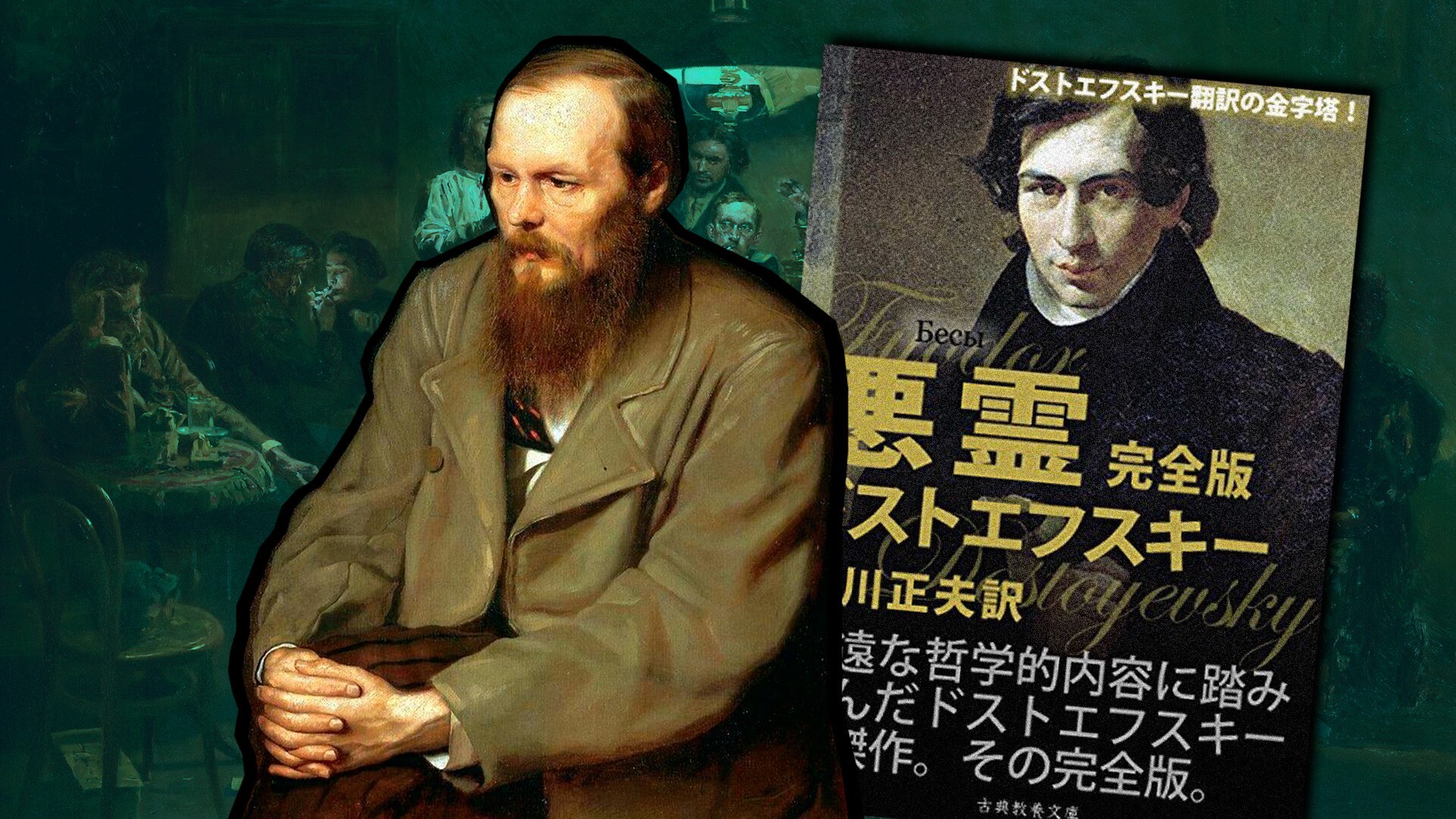
ネタバレ注意!
読者は、ある地方都市に導かれる。勢力家の婦人、ワルワーラ・スタヴローギナが、自分の邸宅に客を招いている。皆が、彼女の息子、ニコライ・スタヴローギンの到着を待っている。彼は、バイロン的なタイプの大変な美男子で、経歴も人柄も、不可解で謎めいたゴシップや噂に包まれている。
その彼は、友人のピョートル・ヴェルホヴェンスキーという、やたらとせかせかした男といっしょにやって来た。ピョートルは、秘密の革命組織のリーダーでイデオローグであり、社会主義とニヒリズムの傾向がある若者を組織に集めている。
突然、スタヴローギンは、組織のメンバーであるイワン・シャートフに、客全員の前で平手打ちされた。シャートフは元学生で、かつては革命思想に共感していたが、現在は、神はロシアとともにあり、信仰こそが唯一の真のロシアの道であると熱烈に信じている。
すぐに、スタヴローギンが平手打ちされた理由について多くの噂が広まるが、誰も本当のところは知らない。しかし、(後で分かって来るが)どうやら、スタヴローギンがシャートフの妹を誘惑したらしい。そのため、スタヴローギンはシャートフとそれ以上争おうとしなかったと推測された。

ヴェルホヴェンスキーは、誰かを血祭りにあげて、革命組織を血の犠牲と共通の秘密で団結させようと企てる。そして彼は、シャートフをそうした政治的犠牲にできると考えた。そこでヴェルホヴェンスキーは、シャートフが組織について警察に通報しようとしていると仲間に主張する。それによって、仲間たちをシャートフ殺害に同意させようとする。
ヴェルホヴェンスキーは、シャートフを射殺し、仲間たちはその死体を池に沈める。その後、ヴェルホヴェンスキーはロシアからまんまと逃亡する。他のメンバーは摘発され逮捕される。そしてスタヴローギンは縊死した。
こうした事件と並行して、この地方は、不穏な時期に入っていく。火災、疾病、暴力、暴動…。まさに悪霊たちが跳梁し社会に浸透し蔓延するかのようだった。
小説の背景と意味
ドストエフスキーの小説の多くは、何らかの形で実際の犯罪や殺人事件に基づいている(『カラマーゾフの兄弟』と『罪と罰』を含む)。『悪霊』も例外ではない。この作品のきっかけは、1869 年に遡る。革命家セルゲイ・ネチャーエフのグループによる学生殺害に、作者は衝撃を受けた。ロシアでの革命的テロルの高まりと、人間性とモラルの崩壊とを懸念しつつ、ドストエフスキーはその最も政治的な小説を書いた。
ドストエフスキーは君主主義者であり、ロシア正教会の信者でスラヴ主義者だった。そして、新しいリベラルでニヒリスティックな政治的見解をすべて斥け、それらはロシアにとって結局、有害であると考えていた。
こうした革命運動を彼は、若者と学生を毒する邪悪な力として捉えた。ヴェルホヴェンスキーの父親(若者たちにリベラルな考えを教えた人物)が登場する示唆的な場面がある。家出した彼は、道すがらある女性と出会う。彼女は彼に、『聖書』を読んでやる。キリストがある人から悪霊を追い出したエピソードだ。そして彼は、悪霊にとりつかれた人をロシアになぞらえる。ドストエフスキーは、信仰だけがロシアを救うことができると示唆し、『ルカによる福音書』の引用を小説のエピグラフとしている。