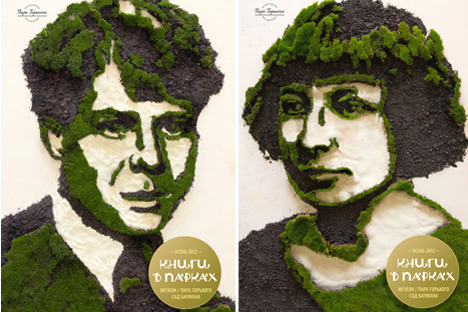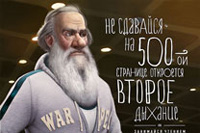マーケティングに見るトルストイとプーシキン

プーシキンはシャツやサングラス、高級不動産、果ては建築資材まで「宣伝」しており、詩人の名は、ネスカフェやコカコーラ、マースといった巨大企業まで利用している。=Press Photo
アレクサンドル・プーシキンは最も有名なロシアの詩人。彼の作品はロシアでも国外でも読まれ、世界中の舞台で演じられ、また映画化もされている。プーシキンはロシア文化のシンボルであり、その人気においてマトリョーシカや熊、バラライカにも引けを取らない。この天才の「名」によって商売しようとする試みは、ずいぶん昔から多く行われてきた。『プーシキン』ブランドでの最初の大規模なキャンペーンは、すでに1899年、詩人の生誕100年と時を同じくしてすでに行われていた。この年には、プーシキンの人気を背景に記念の品が発売されることになった。アレクサンドル・セルゲーエヴィチに敬意を表してその名を付けられたウォッカ、紙巻き煙草、チョコレートは、まるでほかほかのピロシキのように争って買われた。
一方ソ連では民間企業の活動が禁止されたために、生誕200年記念の「利益」は、すでに政府が握っていた。ソビエト・ロシアの商店の棚にはチョコレート『プーシキンの民話』や、特製のボトルに入ったウォッカや徽章、記念コインが置かれていた。
今日では、プーシキンはシャツやサングラス、高級不動産、果ては建築資材まで「宣伝」しており、詩人の名は、ネスカフェやコカコーラ、マースといった巨大企業まで利用している。ロシアじゅうで、商品のパッケージやカフェの看板に描かれた彼の肖像が見られる。「プーシキンの相貌と彼の作品の使用は、いわばハズレのない、手堅い方法なのです。私たちが外国の市場を指向するなら、このようなアプローチは製品に他とは違った魅力を付与し、またミステリアスなロシアの本質、その伝統と独自性をデモンストレーションすることになるでしょう」と、BrandHouse Groupのアレクセイ・グヴィントフキン氏(CEO)は語った。

ウォッカ「プーシキン」
消臭剤に見る文学
古典文学を使用した、近年の最も大胆なマーケティング手法の中に、2011年カンヌ広告祭銅賞を獲得した広告代理店『ヴォスホート』社の『クニーギ=オスヴェジーチェリ(消臭剤本)』がある。書店チェーン『ストー・トゥイーシャチ・クニーグ(十万冊の本)』の依頼により、『ヴォスホート』社は古典文学作品からの抜粋をプリントした消臭剤を企画した。多くの人がトイレで読書をすることに広告代理店は目を付けたのだ。それなら、なぜ文学作品そのものをそのまま消臭剤にプリントしないのか、というわけだ。この「消臭剤本」はショッピングセンター、娯楽施設、ビジネスセンター、レストランやバーに普及した。一風変わったこの手法で、『ストー・トゥイーシャチ・クニーグ』への来店者数は23%増加した。
ビール広告の中のレールモントフ
ロシア最大のビールメーカー『バルティカ』は2011年、ミハイル・レールモントフの詩を使ったテレビ広告を始めた。広告代理店Leo Burnett Moscowが企画したキャンペーンは、10年を超す『バルティカ』で初のイメージ広告となり、同社のビールのラインナップすべてに捧げられたものであった。プロジェクトメンバーであるセルゲイ・デニーソフ氏によれば、Leo Burnett Moscowは『バルティカ』ブランドの再構築を行ったという。当時の調査によると、この巨大なビール業者は、消費者の目から見て流行遅れの、ぱっとしない商標イメージへと変わってしまっており、他の商品との間に、製品ラインナップの統一されたコンセプトもなかった。「我々は、この状況を変えようと決意しました。レールモントフの詩を、コマーシャル映像にあてるテクストとして使用しました。」とデニーソフ氏は明かす。プーシキンについで有名なこのロシア詩人の詩作の断片は、それを聴く人に対してロシアの根源とその文化的遺産を思い起こさせるものであっただろう。レールモントフのおかげか否か、バルティカの2011年の売り上げは13.2%上昇した。
トルストイとグーグル
IT企業も遅れをとってはいない。グーグルは自社のコマーシャル動画「もしもインターネットが千年も前に存在していたら、我々の世界はどんなふうに見えただろう?」の中で、「レフ・トルストイとツイッター」をテーマとしたファンタジーを繰り広げた。長編小説とその詳細を極めた描写で有名なこの作家は、コマーシャルの中でツイッターを使って作品を発表しようと試みている。この巧妙な広告手法は人々の注意を惹き、30万のユーザーが動画を視聴した。
「第一級の作家たち、それはすなわち文化的コードなのです。広告においてその作家たちの様式を利用し、作品を引用するということは、それはある限られた特定の視聴者、つまり中等教育を受け、ある程度の収入をもつ人々を対象にしていると言うことを意味します」と、文芸出版社「エクスモ」の古典文学部門部長エカテリーナ・アレクセーエワ氏は説明する。氏の言によれば、この広告には、大作家への信用が広告商品への信頼として作用しているという。トルストイは悪いものは勧めない、というわけだ。
ソーシャルネットワーキングの中の作家たち
2010年、「アフェクト」社は、ブックフェスティバル「BookMarket」の大規模な広告活動を行った。その中でトルストイ、プーシキン、ゴーゴリ、ドストエフスキーと言った作家の名でFacebookのアカウントがつくられた。それぞれの立場からこれらの作家たちが、ロシアや海外の現実の出来事に対してコメントし、またユーザーからの質問に答えたり、互いに交流したりするものであった。わずか10日の間に1000人を越えるユーザーがこれらヴァーチャルな作家たちと「友達」になり、作家たちのページへのアクセス数は10000以上を数えた。ところがその顛末は、Facebookの管理者により、これらの作家たちは「偽アカウント」であり、利用規約違反であると見なされ、ページが削除されるというものだった。しかし広告代理店もフェスティバルの組織者も、特段損失を蒙ることはなかった。

トルストイがツイッターでつぶやいた?「私を意気消沈させ侮辱するのは、この140字という字数制限だ」
「著作権は死後70年間有効であり、その後はパブリックドメインとなりその利用は誰の合意も求められることはありません」と法律事務所「ユコフ&パートナーズ」のアリーナ・トポールニナ氏は語る。偉大な作家たちの子孫は、いかなる恩恵も受けられないわけである。その上、彼らはその文学遺産がどのような枠組みにおいて利用されるかということに対しても、何も関わることができないのである。ビールの広告にレールモントフの詩が出現するという事態において、いかんともしがたいのと同じように。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。