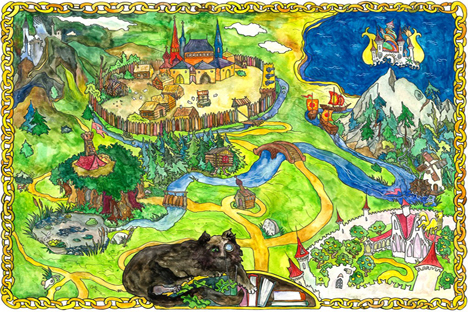児童文学作家マルシャーク死す

写真提供:wikipedia.org
生涯の恩人スターソフとの出会い
マルシャークは、1887年に、ロシア南西部の都市ヴォロネジで、石けん工場の技術者を父に生まれた。少年時代から抜群の文学的才能を発揮し、詩作を始める。
まだ彼がギムナジウムに通っていた頃、そうした習作のノートが文芸批評家ウラジーミル・スターソフの目に触れる。以後、スターソフは、物心両面でマルシャークを助けることになる。この出会いがなければ、彼の才能は埋もれてしまったかもしれない。
スターソフはやがて、少年がサンクトペテルブルクの名門ギムナジウムに転校するよう取り計らった。当時、スターソフは同市の公共図書館で働いていたので、マルシャークもここで本漬けの毎日となる。ところが、マルシャークは1904年に結核を発症してしまう・・・。
同年、スターソフは、少年を作家マクシム・ゴーリキーに引き合わせる。ゴーリキーは彼の才能を惜しみ、彼を家族といっしょに黒海沿岸のヤルタに住まわせ、療養させる。
施設「子供の街」を創設し児童劇を書く
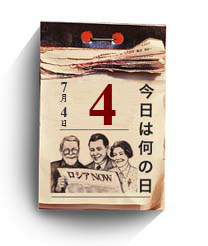 マルシャークは、1907年から雑誌に詩を発表し始め、1912~1914年にはロンドン大学に留学して、イングランド各地を徒歩で旅行しながら、民謡を聴いて回る。この間、ウィリアム・ブレイク、ウィリアム・ワーズワースなどの翻訳も手がけ、ロシアで出版する。
マルシャークは、1907年から雑誌に詩を発表し始め、1912~1914年にはロンドン大学に留学して、イングランド各地を徒歩で旅行しながら、民謡を聴いて回る。この間、ウィリアム・ブレイク、ウィリアム・ワーズワースなどの翻訳も手がけ、ロシアで出版する。
翻訳は、マルシャークの主な業績のひとつであり、とくにシェイクスピアのソネットは名訳の誉れが高い。
第一次世界大戦中は、戦災孤児の救援活動を行い、ロシア革命後の1920年には、施設「子供の街」を創設し、その劇場のために児童劇を書くようになる。
マルシャークは、ゴーリキー、作家コルネイ・チュコフスキーとともに、新しいソビエト児童文学を創り出していく。日本でも、「森は生きている」(現代は十二月)をはじめ、「郵便」、「サーカス」、「静かな話」、「猫の家」などはよく知られている。
「森は生きている」は、俳優座・二期会合唱団(音楽は林光、語りは岸輝子)による2枚組みのレコードが1950年代に出ていた。翻訳は湯浅芳子。このレコードを聴きながら育った方は少なくないだろう。
ソ連児童文学とは何であったのか
現在、マルシャーク、チュコフスキーの児童文学を読むと、筆者はどうも矛盾した印象を受ける。
マルシャークは、その経歴からも分かるように、抜群の音感の持ち主で、チュコフスキーもまた「2歳から5歳まで」という子供の言語感覚を分析した優れた本を書いている。実際、ロシア語で彼らの作品を聴くと、その多彩で疾走するような音響効果はめざましく、響きが、あたかも吸い取り紙にくっつくように、耳に残ってしまう(筆者のような音痴がそう感じるくらいだから、実際大したものだ)。
その一方で、内容は・・・。無駄を削ぎ落とした緻密な構成は見事だが、教訓臭を発しつつ、むりやりハッピーエンドにまとめられてしまうと、どうも違和感が残る。ロシア民話のあの豊穣な象徴の森はどこへ行ったのか。
心理学者C.G.ユングなどがくり返し色々な形で述べているように、人間というものは、自国のそして世界の象徴体系(元型)に自分なりに根を下ろすことで、伝統を継承するとともに、新たな創造性を獲得する。ところが、その象徴的な世界把握が、意識的に根こそぎにされている印象なのだ。おそらく、ソ連児童文学の創始者たちは、新たなイデオロギーを注入するために、高度に意識的にそれをやったのである・・・。
これは、筆者が彼らの作品に触れるたびに、頭に浮かぶ勝手な想像である。だが、もしこれが事実だとすると、その結果はどういうことになっているのだろうか?
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。