セルゲイ・ウィッテ生まれる
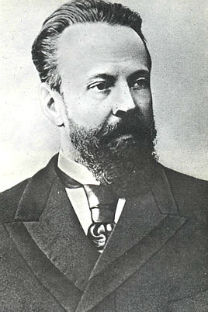
セルゲイ・ウィッテ、1905年
彼は、1892年に大蔵大臣に就任して、工業化を指導した。成果はめざましく、例えば、銑鉄の生産量は90年代の10年間で3倍増となったが、ロシアのアキレス腱である経済のひずみは解決できず、これが1905年革命につながっていく。
セルゲイ・ウィッテ(1849~1915)の父は、バルト出身のオランダ人技術者で、母はロシアの名門貴族出身だった。オデッサの新ロシア大学物理・数学部を卒業し、民間鉄道会社に入って頭角を現し、92年2月に交通大臣に就任する。
工業化か没落か
92年末に彼が蔵相になった頃のロシアは、穀物と石油などの一次産品を輸出し、工業製品を輸入するという、植民地的もしくは後進国的な経済構造だった。
ウィッテは、欧州列強が産業革命、工業化、植民地獲得にしのぎを削る状況にあって、急激な経済発展を実現し、国の没落を防ごうとする。
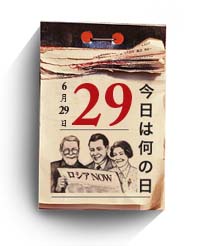 ユーラシア回廊が弱さを強さに変える
ユーラシア回廊が弱さを強さに変える
ウィッテの考えでは、ロシアの特徴は、ヨーロッパでもあればアジアでもある点にある。ロシアは、西欧に対しては、遅れていて弱いが、アジアに対しては優勢である。
西から東に鉄道を敷き(シベリア鉄道)、それをテコに工業化を進める一方、アジアに市場(植民地)を獲得して、工業製品を鉄道で輸送してアジアで売れば、自らの弱さをカバーできるではないか!
しかし、ロシアには鉱石、石油などの資源と安い労働力はあるが、資本と技術はない。そこで、高関税で産業を保護した。ただし、穀物輸出とドイツからの機械の輸入にはさしつかえないよう、関税協定を結んだ。
外国が投資しやすいように、金本位制を導入してルーブルを安定させ、政治的にフランスに接近して、1894年には露仏同盟を締結し、主にフランスとベルギーから外資を導入した。
重税、低賃金、ヤケ酒で国庫を潤す
こうして空前のテンポで、鉄道の敷設が始まり、それに引っぱられて冶金工業が発達していく。90年代前半には、鉄鋼の完成品の半分以上がレールだったほどだ。
これは確かに大成果だったが、貧困層は、工業化の果実を享受できなかった。
農民の土地は地主のそれよりも数倍高く課税されていたし、都市の労働者も劣悪な条件での労働を強いられていた。
例えば、文豪レフ・トルストイが評論『現代の奴隷制』に目撃談として書いているように、36時間ぶっ通しで働く鉄道労務者もいた。
酒びたりとなる者も多かったが、その酒はウィッテが国家専売にしたので、国庫を大いに潤し、主要な財源の一つとなっていた。どこか核燃料サイクル風である・・・。
矛盾の帰結は日露戦争と第一次革命
このように農民、貧困層は、急激な工業化のしわ寄せをもろにかぶった。それだけでなく、国内の資本の大半がフランス、ベルギー、イギリスをはじめとする外国の投資だったのも問題だった。ロシアの経済政策が、これら諸外国の利益や戦略に影響されるからだ。
ウィッテも、こうした問題は十分自覚していたが、解決できなかった。
やがて、欧州を恐慌が見舞う20世紀初頭に、矛盾が一気に噴き出すことになる。国内の不満を外にそらすための戦争、すなわち、日露戦争と、第一次革命が起き、その両方でウィッテは後始末をさせられることになるだろう。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。