ロシア初の石造教会が建立され成聖式を執り行う

19世紀の聖堂
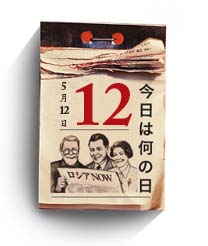 本家に倣って
本家に倣って
現存するのは土台の遺構だけで、往時の姿はよくわからないが、発掘調査の結果、3つの身廊と6つのドームをもつ、ビザンツ様式の1つ「内接十字型」だったことが判明している。
ビザンティンの教会建築は、初期には、ローマ建築から受け継いだバシリカが一般的だったが、9世紀以降の中期ビザンティンでは、この「内接十字型」が標準となった。
「什一聖堂」の内部は、豪華なモザイク、壁画、彫刻などで飾られていたと推測されている。以上のことから、“本家”の様式にのっとり立派な教会を建てようとしたことがわかる。
逃げ込んだ住民の重みで崩壊
創建当初から「什一聖堂」には、コンスタンティノーポリ総主教庁のキエフ府主教座が置かれていたが、1037年に、現存する聖ソフィア大聖堂(1990年に世界遺産に登録)が建てられて、府主教座はこちらに移った。
什一聖堂には公の霊廟が置かれ、1011年にウラジーミル公の妻のアンナ(ビザンティンの皇女)が、1015年にはウラジーミル公が葬られている。また、ウラジーミルの祖母でキリスト教に改宗したオリガもここに改葬された。
その後、ロシアの中心がウラジーミルに移ると、什一聖堂の運命は暗転する。1169年には、ウラジーミル・スーズダリ公のアンドレイ・ボゴリュブスキー(モスクワの建設者ユーリー・ドルゴルーキーの息子)がキエフを占領し、什一聖堂の宝物を強奪する。
1240年に、モンゴル帝国のバトゥがキエフを占領すると、什一聖堂も破壊されてしまう。ここに大量の住民が最後の砦として逃げ込み、彼らの重みで聖堂が崩れ落ちたと伝えられる。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。