サロフに核開発センター建設

AFP/East News撮影
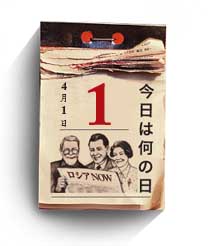 サロフの二つの顔
サロフの二つの顔
当初、開発全般を指導したのは、大粛清の組織者の一人であった副首相ラブレンチー・ベリヤで、物理学者クルチャトフ、ハリトンらが研究、開発に当たった。サロフが選ばれたのは、森の奥深くにあり、秘密を守りやすいのにくわえ、鉄道が通っていて輸送に便利だったのが決め手の一つになった。
サロフの歴史は12~13世紀にさかのぼり、古くから修道院があった。正教会で尊崇されている聖人「サロフのセラフィム」は、ここの森林で修行した。彼には熊もなついていたという言い伝えがある。
サロフ修道院は、ソ連時代に閉鎖され、建物は強制収容所に使われていたが、独ソ戦中は、ロケット弾「カチューシャ」の製造工場となった。
ソ連の核開発を支える
サロフの核開発センターは、1949年には、カザフ共和国(当時)のセミパラチンスクで、最初の原爆実験に成功し、1961年には、史上最大の水爆(通称ツァーリ・ボンバ、つまり爆弾の王様)の製造、実験に成功している。威力は広島型原爆の3300倍あった。
連邦崩壊後、アルザマス16は旧名のサロフに戻ったが、核開発をはじめ物理学研究は依然行われており、許可を得なければ、この街に入ることはできない。
あのアルザマスは北へ80キロ
ところで、文学好きの方は、文豪レフ・トルストイが、旅先のアルザマスで突然、死の恐怖にとりつかれて世界観が変わったという「アルザマスの一夜」をご記憶かもしれない。これは、彼が名作『戦争と平和』の完成を目前にしていた1869年9月2日のことだ。こっちのアルザマスは、サロフ(元アルザマス16)の北80キロのところにある。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。