奉天会戦が始まる

写真提供:wikipedia.org
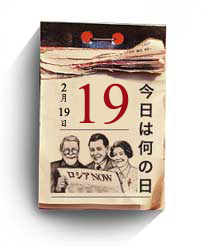 日露戦争で日本軍は勝利をつづけ、1905年1月1日には旅順要塞を陥落させたものの、戦費の調達、補給、兵力動員は限界に達していた。
日露戦争で日本軍は勝利をつづけ、1905年1月1日には旅順要塞を陥落させたものの、戦費の調達、補給、兵力動員は限界に達していた。
一方ロシアは、陸軍の全兵力(200万)の半分しか動員しておらず、とっておきのバルチック艦隊は極東に向けて回航中で、シベリア鉄道全線開通も控えていた。だが、弱みもあり、1905年1月の血の日曜日事件で、国内情勢は、第一次革命に向けて、一気に流動化していた。
凄惨な消耗戦の予期せぬ結末
こうした状況にあって、日本軍(満州軍)は、奉天で増援を待っているロシア軍に、一か八かの大会戦を挑むことに決める。
兵力は日本軍が24万人(大山巌と児玉源太郎が指揮)、ロシア軍は36万人(アレクセイ・クロパトキン大将指揮)。
日本軍は3月1日から、奉天への攻撃を開始したが、ロシア軍は強固な防衛線を築き、よく反撃した。会戦は、全戦線での凄まじい消耗戦となり、日本軍の損害は次第に拡大して、もはや予備軍もほとんどないという苦境に陥った。
ここで、会戦は予想外の結末をみる。
露軍はまだ余力があったのに、3月9日、ロシア軍総司令官のクロパトキンは、乃木希典の第三軍によって退路を絶たれることを警戒して、転進を命令した。
日本軍は3月10日、無人となった奉天に入り、退却する露軍を追撃した。
どっちが勝ったのか?
この会戦では、両軍とも甚大な損害を被り、それぞれ約7万人にのぼる死傷者を出している(露軍はさらに3万近くの将兵が捕虜となった)。
日本軍が奉天を占領したことで、会戦は日本が勝利した形だが、ロシア軍にとっては、奉天の放棄は、伝統的な「戦略的撤退」にすぎなかった。
祖国戦争(ナポレオンのロシア遠征)でもそうだが、広大な国土に相手を引っぱりこんで、相手の補給を苦しくし、これに適宜焦土作戦を組み合わせるというのが、ロシアの“お家芸”である。
ところが、祖国戦争と違っていたのは、クロパトキンが罷免されてしまったことで、ロシアはこれで敗北を自ら認めることになってしまった。
却下された和平提案
日本の満州軍首脳の大山巌と児玉源太郎は、これ以上の戦争継続は困難と考えた。児玉は急遽帰国して、この勝利を花道に、講和の道を探るよう進言する。
アメリカ合衆国大統領のセオドア・ルーズベルトが、仲介役となって、ロシア宮廷に講和を打診したが、「バルチック艦隊が日本に鉄槌を下すだろう」として、和平提案を却下。この時点では、戦争の帰趨はまだわからなかった。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。