1905年革命でニコライ二世が10月詔書
 ニコライ二世 |
ロシア帝国は、1890年代に蔵相セルゲイ・ウィッテの指導のもとで、フランス、ベルギーなどの外資導入により、シベリア鉄道建設、鉄鋼、石炭、石油など重工業が発展し、いわゆる第二次産業革命が起きたが、自律的に発展したのは、綿工業などの軽工業にすぎず、それが低賃金の出稼ぎ労働者によって支えられる、という脆い構造だった。
出稼ぎ労働者は、ほとんど農村出身で、地主の土地が共同体(ミール)の農民の雇役で耕作されており、自作農は育っていなかった。
こうした構造のゆがみが、90年代の好況から一転、20世紀に入って恐慌におそわれたとき、顕在化することになる。
「血の日曜日事件」
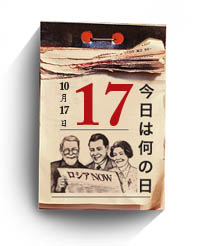
直接の引き金になったのは、「血の日曜日事件」だ。1905年1月9日、首都ペテルブルクの農民出身の司祭ガポンが、女性、子供をふくむ数万の市民とともに冬宮にむかって行進し、請願書をツァーリに提出しようとしたところ、軍隊に発砲され、死傷者多数を出した。死者は1000人以上と推定されている。
請願書は、生活の窮状を訴え、市民的自由と日露戦争の中止などを求める内容だった。当時、デモは禁止されていたが、イコンなどを掲げての平和的な行進に無慈悲に発砲したというので、ツァーリの権威は失墜した。
自由主義的なブルジョワ層を離反
これにくわえて、日露戦争でのあいつぐ敗北、とくに旅順要塞の陥落と日本海海戦での完敗で、政府の権威は地に落ち、6月14日には、黒海艦隊で戦艦ポチョムキンの反乱が起きた。これはセルゲイ・エイゼンシュテインの名画「戦艦ポチョムキン」で有名だ(故淀川長治氏は、「これは“映画の魂”だ」という名言を吐いた。ご覧になっていない方はぜひどうぞ!)。
ペテルブルク、モスクワではゼネストが発生し、労働者、学生、農民だけでなく、地主、資本家なども、政府に要求を突きつけるようになった。国民全体が政府を見限ったかたちだ。
事態の進展は、政府とツァーリを震撼させ、日本との講和に踏み切らせた。ロシア全権はウィッテで、樺太の南半分の割譲のみで、講和することができた。
ウィッテがポーツマスから戻るや、ツァーリは彼を首相に任命した。ウィッテは、まずは自由主義的なブルジョワ層を離反させようともくろみ、10月詔書を起草する。これはみごとに図に当たり、徐々に革命は収束していく。革命勢力内部でも対立が生じるようになる。
咽喉もとすぎれば
結局、政府は革命の押さえ込みに成功し、ツァーリは、今や用なしとなった、うるさ型のウィッテを罷免する。悪夢よさらば…。
ついで首相に任じられたのはピョートル・ストルイピンで、彼のもとで経済はふたたび活況を呈するが、彼の自作農創出の試みは失敗に終わる。
ストルイピンが暗殺されたあとは、もはや戦略眼をそなえた政治家は現れず、政策は行き当たりばったりの冒険主義的傾向を強め、ロシアは第一次世界大戦に巻き込まれていく…。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。