クリミア戦争勃発

セヴァストポリの戦い
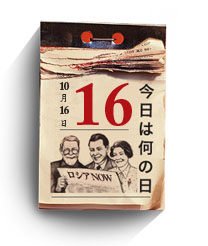 ウィーン体制の破綻
ウィーン体制の破綻
ナポレオン戦争後、戦勝国は、フランス革命前の領土を復活させ、自由主義とナショナリズムは押さえ込み、たがいに妥協できるところはできるだけ妥協して、戦争はやらずに、共通の利益を守っていこうとした。このいわゆるウィーン体制は、いってみれば、旧勢力の利益を真空パックすることをもくろんだわけだ。
帝政ロシアの大歴史家ワシーリー・クリュチェフスキーいわく、「ウィーン会議によって、ヨーロッパに作り上げられた政治秩序というのは、いわば破壊されてしまった古いもののうち、わずかに残る破片を、むりに人工的につなぎ合わしたものにすぎず、その遺物が現在では通用しないところを、いかにも不手際に、“正統性”なる粘土を塗りたくって隠していた」(「ロシア史講話」)。
改革の足かせに
アレクサンドル一世が、ウィーン体制のいわば番人を務めたことは、国内の改革の足かせにもなった。なにしろ、現状維持と正統性と勢力均衡が大原則なのだから。
彼のあとを継いだニコライ一世にいたっては、「鉄道は、社会を流動化させて危険」だというので、なるべく鉄道も建設させなかったという真空パックぶりだったが、これは当然裏目にでることになる。
はたせるかな、西欧での産業革命の進行、市民社会の成熟、1830年と48年の革命のうねり、トルコの弱体化と被支配層、被支配民族の騒乱、蜂起、ナショナリズムの高まりは、真空パック体制を不可能にした。
かくしてヨーロッパ列強は、トルコの利権をめぐって数十年ぶりに正面から激突することになった。
ロシア対トルコ+欧州列強
具体的には、ロシアが、数次にわたる露土戦争で、ダーダネルス、ボスポラス両海峡の自由通行権、全トルコ領における通商権などをつぎつぎに獲得すると、英仏は、ロシアとの対抗上、トルコを支援するようになったのが対立の構図だ。
戦争の直接のきっかけは、フランス皇帝ナポレオン三世が、トルコに対し、聖地エルサレムでのカトリック教徒の特権を認めさせたことだ。正教徒の保護者をもって任ずるロシアのニコライ一世は、正教との権利回復をスルタンに要求したが、拒絶された。そこでニコライがトルコ領に軍を送ると、英仏を後ろ盾にもつトルコもすかさず、ロシアに宣戦布告したという次第。
戦争の経過
緒戦では、ナヒモフ提督の露艦隊がシノペ湾の海戦でトルコ艦隊を撃破するなど、露軍有利に運んだが、英仏が艦隊を黒海に派遣するや、戦局は逆転した。
クリミア戦争は、西はドナウ川流域、バルト海から東はカムチャツカ半島まできわめて広い地域で戦われたが、主戦場は黒海、とくにクリミア半島のセヴァストーポリ要塞の攻防が天王山となった。
露軍は勇敢に戦ったが、ナポレオン戦争当時とは異なり、産業革命の成果が軍備にも反映されるようになった時代で、ロシアの帆船は、英仏の汽船の敵ではなかった。55年8月に要塞は陥落し、戦争は事実上終わった。
戦後、ロシアでは、軍制改革のみならず、農奴制の廃止、自治体(ゼムストヴォ)の創設など、国家の根幹にかかわる大改革がはじまる。
戦争と平和主義
この大戦争は、逆説的だが、二人の偉大な平和主義者を育てている。近代的看護学の生みの親で、みずからも現地で献身的に看護にあたったフローレンス・ナイチンゲールと、作家レフ・トルストイだ。砲兵大尉だったトルストイは、自ら志願して、セヴァストーポリ要塞のなかでも最も危険な第四堡塁におもむいた。彼はここでの極限状況をもとにルポルタージュ的な短編『セヴァストーポリ物語』を書いている。
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。