文豪レフ・トルストイの誕生日

レフ・トルストイと孫
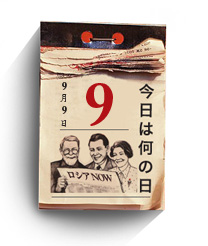 トルストイは稀有の天才で、体力にも財力にもめぐまれていたが、同時にいろんな「業」も背負っていた。
トルストイは稀有の天才で、体力にも財力にもめぐまれていたが、同時にいろんな「業」も背負っていた。
社会のお荷物
ロシアの地主貴族は、国家にとっては、人頭税という国税徴収の番人だった。番人を務めるために国家勤務から解放され、農民が逃亡しないように目を光らせ管理してきたのだが、トルストイが生まれた1828年ごろは、ちょうど歴史の変わり目にあたっていた。
地主貴族の非効率な経営は、もう社会のお荷物で、それはトルストイ家の家計にも現れている。父ニコライが死んだ1837年の総収入の6割(!)ほどが、借金と利子の返済に消えている。
これはつまり、貴族という階層そのものが社会のお荷物にほかならず、早晩滅びる運命にあったのに、贅沢三昧な生活にうつつをぬかしていたということだ。
もちろん、なかには目覚めた貴族もいた。トルストイもそのひとりだった。
“寄生虫”がいだく啓蒙思想とは
トルストイ自身の思想傾向はというと、当人が言うとおり、早くも10代からルソーに傾倒し、音楽事典もふくめ全巻読破していた。大学時代の日記からも、彼の啓蒙主義的傾向はあきらかである。
日記を読むと若きトルストイの知力と教養に驚くのだが、問題は、「社会のお荷物」がいだく啓蒙主義とは、自分自身への刃にほかならなかった、ということだ。
好きな女性のタイプは
もうひとつトルストイの生涯をややこしくしたのは、好きな女性のタイプだ。トルストイ研究の権威、故リディア・オプリスカヤさんは、「トルストイ的美女」と言ったが、そのイメージははっきりしている。
目の覚めるような美貌、こわい波うつ黒髪、野性的なまでの生命力、グラマラスな肢体、傲岸なまでの誇り高さ。
こういうタイプが最初に現れるのは、コサック娘のマリアーナ(『コサック』)においてだ。ナターシャ・ロストワ(『戦争と平和』のエピローグ)やアンナ・カレーニナのような貴族のヒロインも、カチューシャ・マースロワ(『復活』)も、みな同じタイプだ。
概して、トルストイは、上流社会のひよわな貴婦人にあまり魅力を感じず、チェチェン、ダゲスタンなどコーカサスの山岳民、コサック、ジプシー、農民などの女性に惹きつけられた─―彼らの桁はずれの生命力に、自然のふところに抱かれた労働生活に。
理想をかけての実験
だが、地主貴族のトルストイが、こういう女性と真に対等の関係になり、生活をともにするのは至難だ。彼は主人であり、彼女らは奴隷か敵なのだから。利害は真っ向から対立、世界観は水と油。
自分に対立、敵対する世界の女が、ファム・ファタール!にもかかわらずトルストイは、結婚、家庭生活へのあこがれが人一倍つよかった。彼の理想的世界像は、幸福な家庭をベースとして世界全体が愛と調和でむすびつくといった、あくまで家庭を基礎とした一元的、包括的なものだった。
女性の愛にもとづいた世界の調和へのあこがれは、さまざまな変遷をへながらも、処女作『幼年時代』から『アンナ・カレーニナ』まで貫流する中心テーマとなる。
ナターシャ・ロストワやアンナ・カレーニナといった女性像は、「トルストイ的美女」が貴族社会におさまるかどうか、という、彼の理想をかけての文学的実験だった。
しかし、実験は結局失敗する。トルストイはアンナを自殺させ、葬ってしまう―。
トルストイの生涯と作品は、こういう複雑に入り組んだ「業」を、彼がいかに始末したかをみせてくれる。おもしろくないはずがない。これを機にぜひご一読を!
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。