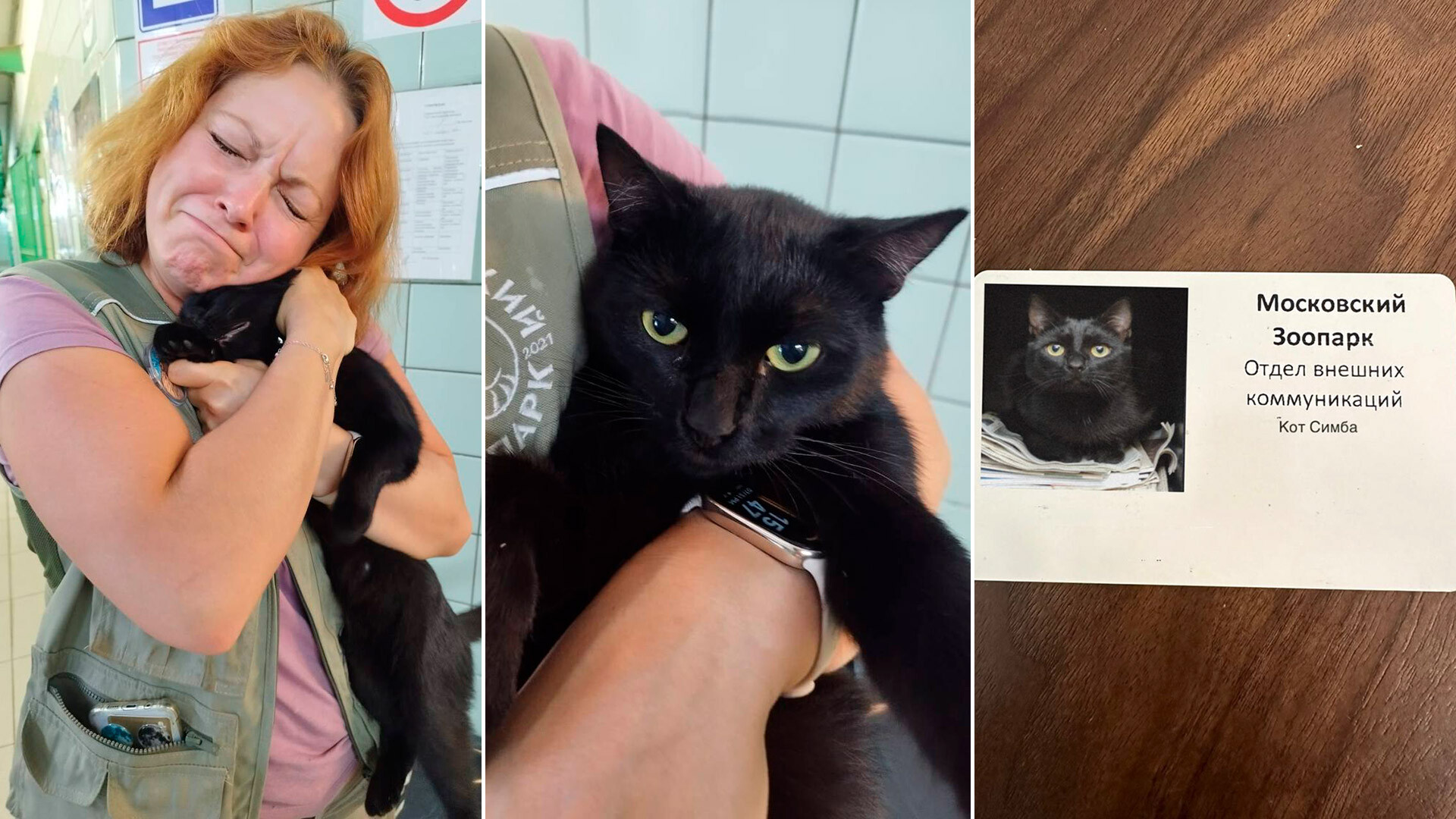ソ連版「ハチ公」物語

1974年。モスクワのヴヌコヴォ空港。ノリリスク(ソ連の極北)に向かう飛行機イリューシン18への搭乗が行われている。タラップのそばで乗客の一人が乗務員と何やら長いこと、激しく言い争っている。この間、彼のそばではリードをつけたジャーマンシェパードが走り回っている。
どうやら対話は、乗客の期待していた方向には向かっていない。そしてついに落胆した乗客は乗務員から離れ、自分の愛犬に向かって何やら話しかけ、首輪を外す。シェパードは散歩に行くのを許されたと思い、嬉しそうに滑走路を走り出す。
シェパードは飼い主が飛行機に乗り込み、タラップが片付けられ、ドアが閉まり、航空機が離陸しようとしていることにまったく気づかない。そしてついにそれに気づき、驚いた犬はスピードを上げる航空機の後ろを追いかけ、見えなくなるまで目で追い続ける。これが、数百万人のソ連市民の心を揺さぶった映画の始まりである。
捨てられた友

後に明らかになるのは、飼い主には動物の検疫証明書がなかったため、友人である犬を手放したということである。そしてそれから2年間、ヴヌコヴォ空港は犬のための避難所となった。
航空機の停車場あたりに住むようになったシェパードは、毎日、滑走路に駆け寄った。イリューシン18の形を覚えていたシェパードは、その型の航空機が近づくたびに、そこに大好きな飼い主が乗っていて、自分の元に戻ってくるのではないかと期待した。
しばらくすると、パイロットや空港の職員たちが、走りまわる犬に気がつくようになる。最初は捕まえようとするが、うまくいかない。注意深いシェパードは誰の邪魔もせず、そしてある職員が規則を違反し、シェパードの面倒を見るようになる。
シェパードは誰にも近づこうとしなかったが、職員たちは餌をやった。また名前はなにかを知ろうと、さまざまな名前で呼んだ。シェパードは、アルマという名前に反応したため、パルマという名になった。

パルマは毎日、辛抱強く、雪が降ろうと雨が降ろうと、イリューシン18を追いかけた。作業員の一人が、犬の飼い主がタラップのそばで乗務員と言い争っていたのを覚えていたが、詳細を明らかにすることはできなかった。
そしてついに、パイロットの一人、ヴャチェスラフ・ワレンテイが、この驚くべき犬のことを「コムソモールスカヤ・プラウダ」紙の編集部に話したのである。「ワレンテイがいなければ、誰かがパルマのことを知ることはなかっただろう」と、ジャーナリストで写真家のユーリー・ロストは述べている。
 ヴャチェスラフ・ワレンテイ
ヴャチェスラフ・ワレンテイ
ロストは、パルマに会うため、ヴヌコヴォに向かった。「これからは、わたしたちみんなで食べ物をあげるからね」と空港の職員が言ったという。「でも、パルマは人の手からは何も食べず、技術のヴォロジン以外の人を近づけることもなかったんです。どうも彼とは友情が芽生えていたようなのですが、それでも、飛行機を見落としてはいけないと彼のそばに行くのすら嫌がることもありました」。
新しい家
まもなくして、「コムソモールスカヤ・プラウダ」に「2年待っている」というタイトルの記事が掲載された。パルマのことを書いたもので、犬を空港に置いて行った飼い主に呼びかける内容をもつものであった。「イリューシン18に搭乗して飛び去り、もう犬のことなど忘れてしまった人がこの記事を読んだなら、急いでお金を用意し、休暇を取り、飛行機でモスクワにきてほしい」。
パルマの物語はソ連全土に広がった。新聞社の編集局には、忠実な犬を引き取りたいという人から数千という手紙が届くようになった。
そして飼い主も見つかった。仕事のために極北に行ったのである。書簡の中で、彼は「問題が次々と出てきて、忘れてしまった」と言い訳した。しかし、モスクワに戻ろうと思うという言葉は書かれていなかった。そして本当の名前も書かれていなかったため、犬はパルマと呼ばれ続けた。
パルマのために新しい飼い主を探しはじめ、教育大学の助教授で、有名なウクライナの詩人イワン・コトリャレフスキーの玄孫であるヴェラ・コトリャレフスカヤに白羽の矢が立った。彼女はこの怖がりのシェパードを本格的に可愛がることにしたのである。
 ヴェラ・コトリャレフスカヤとパルマ
ヴェラ・コトリャレフスカヤとパルマ
ヴェラは1ヶ月の休暇をとり、ヴヌコヴォに移り住んだ。毎日、犬に会いにきて、そしてついに信頼を勝ち取ることになる。
そしてついに、コトリャレフスカヤはパルマに睡眠薬を与えるのに成功し、その翌日、パルマはウクライナの首都にある見知らぬ家で目を覚ますのである。
パルマは騒ぎ立てることもなければ、パニックを起こすこともなかった。「強い神経を持ち、人にも家にも慣れた、とても落ち着いた犬でした。家で眠る娘に近づいて、頬をなめ、やさしく耳を噛みました」とコトリャレフスカヤは日記に綴っている。
しかし、それでもパルマは隙があれば逃げようとしたため、バルコニーや窓は常に閉めておかなければならなかったという。
半年ほどしてようやく、パルマは新しい家と新しい飼い主にすっかり慣れ、愛情を捧げ、忠誠を誓うようになった。