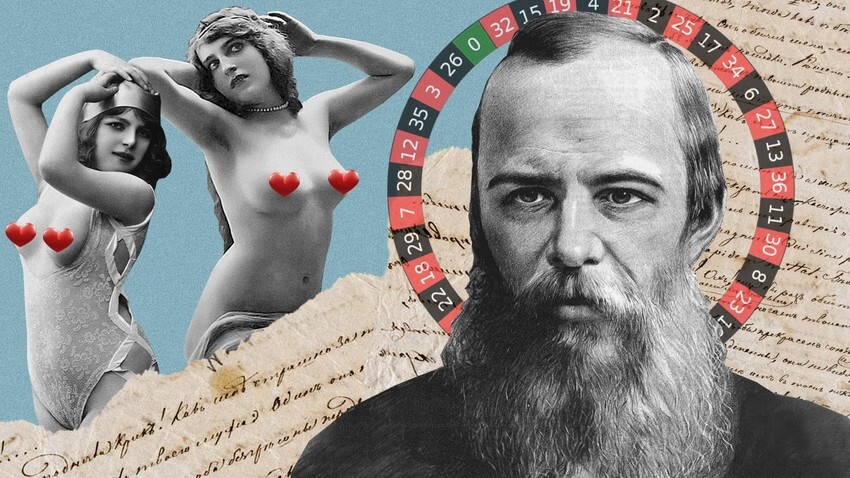知っておくべき(そして舞台で観るべき)アントン・チェーホフの4つの戯曲

1. かもめ(1896年)

時代は帝政ロシア。アマチュアの戯曲家コンスタンチン・トレープレフは、地方にある叔父の領地で、ある劇の上演の準備をしている。トレープレフはこの芝居で、隣人の娘であるニーナ(トレープレフが恋心を抱いている)を主役に据える。ニーナは女優になることを夢見ているが、両親に反対されている。ニーナは言う。わたしはかもめが湖に飛んでくるように舞台に向かうのだと。そしてある日、トレープレフはかもめを撃ち、ニーナの前に横たえる。
アマチュア芝居の初演には、友人や隣人が集まり、ニーナの演技は、彼女をほめそやす人々からは賞賛される。しかし、戯曲について人々はデカダンス的だとして批判し、トレープレフは落胆する。結果的にニーナは彼女に優しい言葉を言ってくれる男性に恋をし、一方のトレープレフは自分の戯曲が失敗に終わったことを確信し、そこを去る。そして彼の人生は悲劇的な最期を迎える。
チェーホフの「かもめ」は、彼の別の戯曲でもさらに発展を続けるテーマである、19世紀のロシアの貴族階級の衰退を描いたものである。ロシアの貴族たちは働くことができず、贅沢な暮らしをし、お金に困っている。芸術に精通し、演技をしたり、本を書いたり、作曲したりしてみるが、実際、自分には才能がないということを認めることができない。彼らは人生と芸術を混同し、人間関係を無視して、名声を得ようとしている。
「かもめ」は1898年、モスクワ芸術座で、コンスタンチン・スタニスラフスキーとウラジーミル・ネミロヴィチ=ダンチェンコによって上演され、大成功を収めた。作品はその2年前にサンクトペテルブルクのアレクサンドリンスキー劇場で上演され、酷評されたことから、チェーホフはモスクワの初演には顔を出さなかった。
2. ワーニャ伯父さん(1897年)

自分自身の生活スタイルを維持するだけのお金を持たないセレブリャコフ教授は、亡き妻の領地に住まなければならなくなった。教授は、新しい若い後妻、そして先妻との間の娘ソーニャと暮らしているが、娘のソーニャは義母がお金目当てで父親と結婚したのではないかと疑っている。イワンは、セレブリャコフの最初の妻の兄でソーニャの伯父(ワーニャ伯父さん)である。彼は長年、この領地を経営してきた。運命の皮肉によって、セレブリャコフはイワンをその博識ゆえ、尊敬していたが、今や落ちぶれた教授を羨むこともなくなり、セレブリャコフは教授の若い妻に恋をする。イワンの苦々しい怒りに、教授は、領地を売りはらって、お金を得ることを提案する。イワンはセレブリャコフを撃ち殺そうとするが、弾は外れてしまう。教授と若い妻は去っていくが、ワーニャ伯父とソフィヤは領地に残る。姪のソーニャはイワンを落ち着かせ、この世のすべての苦しみは、死後の世界で報われるのだと諭す。「もう少しよ、伯父さん。もう少しで一息つけるのよ」と。
チェーホフはこの戯曲を「田舎暮らしの風景」と位置付けた。彼がここでも描いているのは、帝政後期に貴族の多くがたどることになった貧しい暮らしについて、また彼らがいかに一般の労働者を蔑み、尊大な態度であったかを描き出した。チェーホフは利己主義がいかに魂を歪めるかということ、そしてかつて高い教育を受けた貴族たちの低下した道徳イメージについて書いた。セレブリャコフ教授は、他人の気持ちを考えず、自分自身の快楽のことしか考えていない。ドラマの中心となっているのは、ワーニャ伯父はいつも皆のことを気遣い(しかもそれを見せびらかさず)、寛大な心を持っているにもかかわらず、親戚や友人には取るに足らない人物でしかないというところに焦点を当てたものになっている。戯曲は地方のいくつかの劇場で舞台にかけられた後、モスクワ芸術座で上演され、大成功を収めた。
3. 三人姉妹(1901年)

三人姉妹と兄弟は地方の町に住んでいる。4人は1年前に父親を亡くし、これからどうやって生きていこうかと考えている。長女のオリガは教師として働き、2番目のマーシャは不幸な結婚生活を送っている。そして末娘は自分の進むべき道も、結婚相手も見つけることもできずにいる。多くの男性が彼女に恋をするが、彼女は誰といても退屈なのであった。この知的な20代の3姉妹は、けして実現することのない計画を夢見て、空虚で無意味な生活を送っている。同時に、ごく普通の女性と結婚し、学問を諦めた兄弟には嫌気が差していた。芝居はオリガのこんなセリフで幕を閉じる。「もう少ししたら、何のためにわたしたちが生きているのか、何のために苦しんでいるのか、わかるような気がするわ。・・・それがわかったら、それがわかったらねぇ!」
戯曲はプロットがないように思われる(トルストイはこんな冗談を言っている。「もし酔っぱらいの治療師がソファに寝転んでいて、窓の外に雨が降っているのを、チェーホフなら戯曲にし、スタニスラフスキーならムードにする」)。しかし、「三人姉妹」は執筆されて以来、長年にわたり、世界の多くの国で上演され、愛され続けている。ロシア以外の国での初演は1901年にベルリンで行われた(今でもこの戯曲はドイツで人気を誇っている)。ジャンルをとっても、登場人物をとっても、戯曲はその当時革命的なものであったが、今でも、それぞれの演出家が、新たな解釈を試み、現代社会との関係性を見出そうとしている。
4. 桜の園(1904年)

リュボーフィ・ラネフスカヤは没落した貴族の女地主である。一時フランスで生活していたが、すべての資産を使い果たし、残ったのは、美しい桜の園がある広大な領地だけであった。しかし、桜の園は借金返済のために売りに出されている。一家は何世代にもわたってこの桜の園を所有し、彼女自身もそこで育ったことから、ラネフスカヤは絶望する。
そんなとき、商人のエルモライ・ロパーヒンが領地を分割し、一部を別荘地として貸し出し、収入を得て、借金を返せばいいと提案する。ロパーヒンはラネフスカヤ家に仕えてきた農奴の息子だったが、その後、裕福な商人になった。ラネフスカヤは大切な桜の園を分割することなど考えられず、ロパーヒンの提案を無視することにした。そして怠惰な生活を続けながらも、その状況に不満を漏らしていた。そしてある日のこと、ロパーヒンが現れ、自分が競売で桜の園を買ったと宣言する。彼はかつて祖父が農奴として暮らした土地を手に入れられたことに感動を覚える。そして戯曲は、桜の幹に斧を打ち込む音で終わる。
これはチェーホフが自身で「喜劇」と名づけた最後の戯曲である。またすべてのロシアの戯曲の中で、もっとも頻繁に上演されるものの一つである。これが1905年の第一次ロシア革命の前夜に書かれたのは象徴的なことである。当時、古い帝国ロシアの貴族は、新しい現実と変革と進歩に直面し、幻滅を感じていたのである。
「桜の園」はモスクワ芸術座で初演されたが、演出家のコンスタンチン・スタニスラフスキーはこの戯曲の意味について次のように語っている。「桜の園は、何の収入ももたらさない。その木と咲き誇る白い花の中にあるのはかつての貴族の生活についての詩である。そのような庭園や花はファッションのためであり、台無しになった美学のために作られている。それを壊すのは悲しいことであるが、必要なことでもある。なぜなら、国の経済発展のプロセスがそれを求めているからである」。