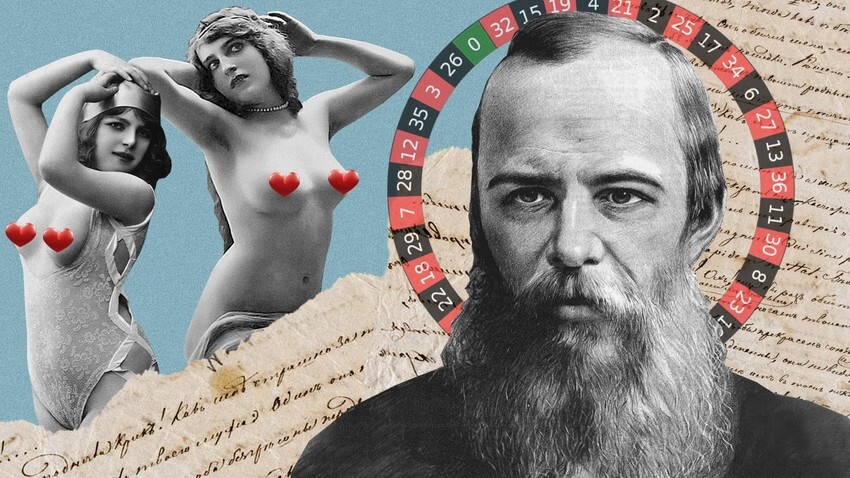短編の名手アントン・チェーホフの必読の名作はこれだ

チェーホフは、500以上の短編小説を書いたが、それらは深みと芸術性の点で、他の作家の長大な作品に勝るとも劣らない。彼は、たとえば、主人公の「いかに生きるべきか」の真剣な探求や波乱万丈なドラマといったものではなく、何よりも日常生活に目を向けた。
チェーホフの主人公たちは大抵、彼らが置かれた状況や日常生活にはまり込んでおり、はっきりした志向や意志をもっていない。
しかし、同時代の人々はこれを歓迎した。それらのキャラクターがリアルな「本当の」人物だからだ。チェーホフは、それらの人物に評価を下さず、非難せず、ただ沈着な観察者の目で捉えた。
作家マクシム・ゴーリキーはチェーホフにこう書き送っている。あなたほど単純なものごとを見事に描く人はいない、と。
「あなたの、一見ささやかな小品を読むと、他のあらゆる作品が粗雑に見え、まるでペンではなく丸太で書かれているように感じられる」。ここにチェーホフの、必読の10作品を挙げよう。
1.『カメレオン』、1884年
 「カメレオン」の挿絵
「カメレオン」の挿絵
N市のマーケット広場で小事件が起きる。犬が金細工職人フリューキンの指を噛んだ。彼は騒ぎ立てて、警察署長オチュメーロフが事件を解決すべくやって来る。
最初、「法の代表者」は憤慨し、逃げた犬をできるだけ早く始末し、飼い主に罰金を科さねばならん、と叫ぶ。ところが、将軍の飼い犬だと聞くと、彼の意見はころりと変わる。「どうしてそんな犬がお前を噛んだりするもんか?」。しかし後で、将軍の飼い犬ではないかもしれないと分かった。それじゃあ、始末しろ…。えっ、将軍の弟の犬だと!「じゃあ、やっぱり将軍家の犬か?いやあ、けっこうですなあ…」
『カメレオン』は、すべての学童がまず最初に読むチェーホフ作品の一つだ。この作品は、その人が誰を相手にしているかによって、いかにコロコロ意見を変えるかを見事に示している。上司か目上か、あるいは庶民かにより、まさにカメレオンみたいに変わるわけだ。
2.『ワーニカ』、1886年
 「初心者」、イワン・ボグダノフ
「初心者」、イワン・ボグダノフ
9歳のワーニカには父親も母親もいない。彼は靴職人に弟子入りしている。降誕祭前夜、みんなが仕事に出かけると、ワーニカは、しわくちゃの紙を取り出し、祖父に手紙を書き始める。少年は、靴職人が自分をどんなにひどく扱っているか、どんなに粗末な食事を与えられているか、ちょっとしたミスでもどんなにひどく殴られているか、そして他の徒弟たちがいかに自分をいじめているかを祖父に説明した。少年は祖父に、自分を引きとってほしいと頼み、何でも言うことを聞くから、と約束する。「僕は徒歩で村に逃げ出したかったんだけど、長靴がないので、寒さが怖いんだ」
クリスマスの奇跡は起こるだろうか?まあ、現実には、奇跡は滅多に起きない。正確な住所を知らなかったので、少年は封筒に「村のおじいさんへ」と書く。宛先が見つかる可能性は皆無に近い。この宛名は「人口に膾炙して」、住所の書いてない手紙、どこにも届かぬ小包の同義語になった。
3.『カシタンカ』、1887年
 「カシタンカ」の挿絵
「カシタンカ」の挿絵
ダックスフントと雑犬が混ざった小犬が迷子になった。飼い主が酔っぱらったせいで、見失ったのだ。通りで、見知らぬ人が犬を憐れんで自宅に連れて行き、餌を与えて飼うことにし、「カシタンカ」(栗)という名前をつけた。新しい飼い主は、サーカスのアーティストで、犬といっしょに芸をすることにした。そのデビューの際に、何者かが犬を昔の名で呼んだ。犬の前の主人がサーカスに来ていたのだった。
チェーホフは、ここでは犬とその思考をできるだけ「人間化」し、感情を与える。まさにそのことによって、犬と人間との違いが際立つのだ。犬は、前の主人に執着していて、新しい場所で満腹して眠りについたときでさえ、彼を恋しがり、その息子のいじめさえ懐かしがる。つまり、この犬は、快適さ、温かい食べ物、そしてサーカス芸人の栄光と、前の主人を取り換えようとは決してしない。だから、彼が名を呼ぶと、すぐさま駆け寄る。
4.『学生』、1894年
 「聖ペテロの否認」、レンブラント・ファン・レイン
「聖ペテロの否認」、レンブラント・ファン・レイン
神学校の学生が帰宅途中、突然、寒さが増し、強風が吹き始める。彼は暗い考えに捕らわれる。同じような風が、リューリク朝の始祖の時代にも、いやそれどころか、使徒ペテロの頃にも、もう千年も吹きすさんできた。そしてこの間、結局のところ、何も変わっていない。至るところ、相も変わらずの貧困、憂愁、無知蒙昧…。
途中で、学生は、自分の村の寡婦とその娘にたまたま出会った。退屈しのぎに彼は、二人に『聖書』の物語を語り始める。すなわち、いかにペテロがキリストを否認したか、そして、おそらくその夜も、同じようにひどく寒い夜だったろう、と話したのだった。
彼の話を聞いて、寡婦は泣く。学生は、彼女がペテロの苦悩に本当に同情しており、ペテロの身に起きたことが彼女に身近であることに気づく…。
この短編の中で、学生は非常な変化を体験する。『聖書』や教会の書物をただ読むことは、実は、彼には退屈だった。現実の人間たちとの触れ合いとその本物の苦悩に接して初めて、人生はその意味を彼にある程度開示し始める。
5.『中二階のある家』、1896年
 映画「中二階のある家」からのシーン
映画「中二階のある家」からのシーン
怠惰な生活をしている画家が、この作品の語り手となる。彼に興味があるのは散歩とお茶を飲むことくらいだ。ある日、彼は、隣家の、中二階のある家に住む未亡人とその二人の娘に出会う。妹は若くて夢見がちで、画家の絵を賞賛し、彼は彼女に惚れ込む。
姉のほうはまったく対照的に活動的で、学校で働き、農民の子供たちを教え、病人の世話をし、農民のための診療所をつくろうとしている…。しかし、彼女の活動ぶりと自信満々な様子は画家を苛立たせる。
チェーホフは、この物語の中で、二つのタイプをぶつけている。一方は、疑いを知らぬ、自信に満ちた活動的な人物であり、些細なことでも何でも、人々を助けることが重要だと思っている(チェーホフ自身、医師として農村で献身的に働き、自分の屋敷で病気の農民を無料で診療している)。もう一方は、何か根本的な変化が必要だと考えている観照的な哲学者タイプだ。そうした変化が起きぬ限り、結局は同じことなのであり、何かする意味はない。
6.『イオーヌイチ』、1898年
 「イオーヌイチ」に基づいた映画「In S. City」からのシーン
「イオーヌイチ」に基づいた映画「In S. City」からのシーン
若い医者ドミトリー・イオーヌイチは、農民をはした金で治療するという高貴な使命を抱いて、地方の町にやって来る。彼の唯一の娯楽は、夜にトゥルキン家を訪れることだ。彼らは芝居をやり、娘のカーチャがピアノを弾く。医者は娘に恋してプロポーズするが、「高尚な輝かしい目標」を目指している彼女は断る。
年とともに、医者は、腹は出っ張り、ぶくぶく太り、「現実的」になる。トゥルキン家の芝居はもはや、彼の興味をほとんど引かないが、お金や家庭のぬくぬくした快適さには目がない…。彼はもう歩かずに、自分の馬車に乗る(チェーホフにおいては、こうしたディテールは非常に重要だ)。さて、彼がカーチャに久々に再会したとき何が起きただろうか?
チェーホフはここでお気に入りのテーマを描いている。夢をもつ人々がいかにごく平凡な人間に変貌していくか、日常生活がいかに彼らを飲み込んでいくか。
7.『箱に入った男』、1898年
 映画「箱に入った男」からのシーン
映画「箱に入った男」からのシーン
ベリコフは、暖かい日でもコートを着て、傘をケースに入れてもっている。概して、彼の持ち物は何でも彼独特のケースに入っている。顔は襟の奥に隠している。いつでもどこでも秩序を好み、疑惑と不安に苛まれていた。そして、ようやく棺桶の中で初めて、彼はほとんど陽気な表情をしていた。「ついに彼は、ケースに入れられた。彼がそこから出ることはもはや決してない」
チェーホフは、自分の殻に閉じこもり全世界から身を隠そうとした孤独な男を見せてくれた。彼の人生は、周囲の目から隠れており、空虚で真の意味に乏しいものとなっていた。だから、彼が死んだときは誰も悲しまなかった…。
「箱(ケース)に入った男」は、否定的な意味をもつ、一般的なイディオムになった。慣れ親しんだ快適な環境(コンフォートゾーン)を抜け出して、世界に対して自らを開くことを恐れ、多くの可能性を空しく失う人々について、このように言われる。
8.『すぐり』、1898年
 映画「すぐり」からのシーン
映画「すぐり」からのシーン
この物語の主人公は事務所で働いているが、郊外に住み、土地を買うことを夢見ている。彼の考えでは、自分の土地には必ずセイヨウスグリ(グーズベリー)の茂みがなければならない。そこで彼はあらゆる物を節約し、びた一文とも無駄にしない。結婚も、お金のための打算的なものだった。その吝嗇のせいで妻は疲弊し、死んでしまう。が、数年後に夢が実現した。主人公は、不動産をもつ紳士になり、自分のスグリを貪り食う。
この話は、『箱に入った男』のテーマと関係し、度外れな自己中心性について語る。ひいてはこれは、人間の幸福についてのチェーホフの重要な考えを示す。
9.『可愛い女』、1898
 映画「可愛い女」からのシーン
映画「可愛い女」からのシーン
オーレンカは、とても物静かで気立てがやさしかったので、誰もが彼女を「可愛いひと(ドゥーシェチカ)」と呼んだ。彼女は、夫の仕事と心配事に完全に没入する。最初の夫は、芝居の興行主、次の夫は、材木置場の管理人、その次の夫は獣医…。彼女は夫の仕事に大いに興味をもって精通しただけでなく、有能な助手にもなる。夫の仕事と関心に応じて、彼女の話し方と言葉さえも変化する。彼女は、献身的な、あまりに献身的な妻だったが、なぜか夫たちは次々に死んでしまうのだった…。
これは、女性の本性とその役割についての最も重要な作品の一つだ。ロシアでは19世紀末に、女性たちは、もっぱら母と妻だけという存在ではなくなっていった。社会は、女性たちが教育を受け、働き、社会に利益をもたらすことを求め始める。チェーホフはその新しい役割について考えるが、あえて結論を保留にする。
10.『犬を連れた奥さん』、1899年
 映画「犬を連れた奥さん」からのシーン
映画「犬を連れた奥さん」からのシーン
二人の不幸せな既婚者が、クリミアで休暇中に出会い、避暑地のロマンスとなる。休暇の後、二人はそれぞれの家庭に戻るが、お互いに後ろ髪を引かれている。本当の愛に出会ったことに二人は気づき、密かに会い、いっしょに未来を夢見始める…。
この短編は何度も映画化されているが、様々な解釈の余地がある。チェーホフはここでも、幸福を求めて果敢に戦う英雄ではなく、人生の流れに身を委ねる人々について書いている。