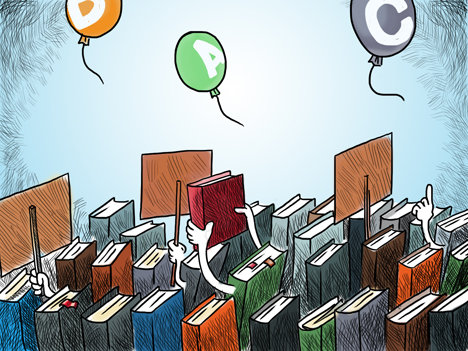
画像提供:K.Maler
画像提供:K.Maler |
文学はロシアにおいて、歴史的理由により、昔から哲学、報道の自由、政治、宗教といった文学らしからぬ性質を持っていた。ソ連が崩壊したから、作家がようやくしかるべき活動に没頭できると思われた。国には報道の自由、政治の自由、宗教の自由があり、教会が再開し、政党と国会があり、新聞は好きなことを書ける、作家は国と社会から離れて文学にいそしむことができる・・・。
15年が経過した後、ロシア政府は突然、文学の存在を思いだした。国の文化が低下している、教育システムが崩壊している、文学が危機的状況にある、出版社が苦戦している、図書館が困っているなどの話がひんぱんにでるようになり、もはや市場の力ではどうすることもできず、政府の関与が必要となったからだ。
文学の存在を思いだした政府
そしてもうひとつ、2000年代終わりに反政権派の活動が高まったからだ。モスクワとサンクトペテルブルクでは、さまざまなデモが行われ、作家も積極的に参加した。この影響力も大きかった。政府はふとこれに目を向け、ふむ、なるほど、文学はやっぱり存在するし、社会的意義がそこにあるんだなと感じ取った。
そして文学分野における融資規定、すなわちある作家には融資を行い、別の作家には行ってはいけないといったことを定めようという話になった。そうなると疑問がわいてくる。作家の自由、表現の自由の権利が制限されるのだろうかと。
きっとこれから作家に何を書くべきか、何を絶対に書いてはいけないかといった指示があるんだろう、と言われるようになった。ソ連時代みたいだ。だがソ連には今のロシアとは異なり、抽象的な愛国主義や政権(首脳)をののしることのタブーを除いて、国家的なイデオロギーがあった。ロシアには文学界を指導し、こうすべきとの厳しい要求をつきつけるようなイデオローグがまだいない。この点から考えれば、今のところ危険性はない。
明確な政治的イデオロギーは現代のロシア文学にはなく、政治的長編小説と呼べる作品はかなり限られている。政治的に活発な作家は、こっちは小説、こっちは政治活動といった具合にしっかりわけている。
イデオロギーがないと読まれない“伝統”
政治的イデオロギーはなくとも、世界観は当然ながら存在する。ロシアでは文学が社会とは切り離された美文学分野として、根付かないのである。トルストイやドストエフスキーの伝統がここには生きている。ロシア人読者にとって、世界観と実存的意味のない作品は、あまりおもしろくないし、純粋な美学や、芸術のための芸術と呼ばれるもののファンは少ない。文章に社会的意味や社会的立場があると、作品の芸術性にかかわらず、読者の関心を引く。
ザハル・プリレピンの物議をかもした長編小説『サニキャ』は傑作からはほど遠いが、若き革命家について書いている。アレクサンドル・テレホフの長編小説は長くてしつこいが、最新作『ドイツ人たち』はモスクワの役人根性に関するもので、とても時代にあったテーマとなっている。マクシム・カントルの叙事詩は過激な反リベラルで、それ以外には何もない。登場人物もあらすじも単純で稚拙だが、多くの人が、この作品には「意味がある」と思って読んでいる。
エラスト・ファンドリン刑事についての歴史シリーズを書いた、非常に政治的な人物であるボリス・アクーニンも例にあげてみよう。舞台は19世紀のロシア帝国。これは探偵小説だが、品行方正な人間が国に対してどうふるまうべきか、何が許されるのか、何が許されないのかを示している。このスタイルによってアクーニンの文章が一大事に変わるのである。
作風やあらすじの観点から、これらすべてが天才的な作品だとは思わないが、何よりもイデオロギー的な文章であるために、人々が読むのである。
*アンドレイ・ヴァシレフスキーは文芸評論家、「新世界」誌編集長
*ヤン・シェンクマンが記事化
ロシア・ビヨンドのニュースレター
の配信を申し込む
今週のベストストーリーを直接受信します。